自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
作/演出 わがぎえふ 出演 コング桑田 粟根まこと 八代進一
驚いた。大津事件のことだった。
もちろんそこはリリパだけあって、もう笑いに笑い。本当に面白かった。仕組まれた笑いと、作り上げた笑い。どちらもあってスゴいなあと思うのです。ゲストの粟根さんや八代さんが特に目立つというわけではなく、きちんと物語の中にすっぽり入っている。
もう5年以上見ていたなかったリリパだが若い役者さんが大勢育っていてそれがとても面白く発見だった。相変わらずコング桑田さんは圧倒的な存在感で面白い。何でもっとこの人は世の中に出て来ないのか不思議なくらいだ。
ラストシーンで意味もなく八代さんが半分かくれてそうな隠れていない、でも客席の半分くらいしか見えないところで延々とディープキスをしているのが面白かった。もてるなあ。八代さん!
すいません。ホントに感想だけだなあ。
俳優さん、身体にキレがあって、台詞もスコーンと空に抜けていて、客へのサービスも完璧で。いいですなあ。ホント、いいですねえ。

2008年3月20日(あまりにも面白かったので3月25日も)
下北沢 ザスズナリ
驚いた。大津事件のことだった。
もちろんそこはリリパだけあって、もう笑いに笑い。本当に面白かった。仕組まれた笑いと、作り上げた笑い。どちらもあってスゴいなあと思うのです。ゲストの粟根さんや八代さんが特に目立つというわけではなく、きちんと物語の中にすっぽり入っている。
もう5年以上見ていたなかったリリパだが若い役者さんが大勢育っていてそれがとても面白く発見だった。相変わらずコング桑田さんは圧倒的な存在感で面白い。何でもっとこの人は世の中に出て来ないのか不思議なくらいだ。
ラストシーンで意味もなく八代さんが半分かくれてそうな隠れていない、でも客席の半分くらいしか見えないところで延々とディープキスをしているのが面白かった。もてるなあ。八代さん!
すいません。ホントに感想だけだなあ。
俳優さん、身体にキレがあって、台詞もスコーンと空に抜けていて、客へのサービスも完璧で。いいですなあ。ホント、いいですねえ。
2008年3月20日(あまりにも面白かったので3月25日も)
下北沢 ザスズナリ
PR
作 ビフュナー
構成/演出/美術 佐藤信
出演 笛田宇一郎 KONTA
テアトルコンプリシテの芝居を初めて見た時、エッシャーの騙し絵を思いながら見ていた。佐藤信さんが演出したこの作品を見ていて思ったのは、マグリット、キリコ、エルンストの絵画である。どちらかというとベルギーぽいシュールレアリズムのアーチストのそれである。そういった視覚的な変化にとむそれが、市民革命前の時代感のある、が、すでに詩的に昇華されたテキストと。 黄金の紙の切り取られた舞台の上で繰り広げられるもの。本当に金のように値打ちのあるそれである。我々は過去のこと、舞台上のこととして見ていてはいけない。時にその枠は破られ観客もその中に巻き込まれて行くのだ。 肉体のムーブメントの面白さと、肉体の質感の面白さ。テキストで表現される一方で、リズムや音や光、叫びによって思いを表現したりする。それが、同時多発的に舞台にでてくるから比較しやすい。そんな2時間弱の世界。
難しい芝居なのかと思いきや、テアトルコンプリシテ同様に分かりやすく見ていて面白い。普段は映画もドラマも小説にもふれないゲームと断片的な映像ばかりの世代にも分かりやすく刺激的に作られている。テキストは詩的に昇華されているし、21世紀の時代のスピードにあった変化にとんだ舞台になっていた。
今回も笛田さんがメインでどかんと真ん中にいるんだろう…と。そこにKONTAさんが挑むって形かなあと想像していたら、違っていた。肉体的には、笛田さんは舞踏の竹内靖彦さんに激しく挑まれ拮抗する。そして、その肉体の座標軸。もうひとつ、バレエ、モダンダンスとストリップ、ポールダンス、AVなどに出演したことのある水無潤さんが別のベクトルで対抗する。3次元の関係なのだ。笛田さんのテキストは終始無言の竹内さん、音として多様な表現方法を繰り出して挑むKONTAさんに挑まれる。ここでも拮抗している。
革命は既存の権威が崩壊して行く、もしくはひっくり返されるそれだから、そうした、激しい存在が同じ舞台でどかーんと対峙していることで空気が自然と生まれるのだ。
きちんと稽古し仕組まれたものと、その場の偶然性にまかされる部分が混ざり合う。が、仕掛けがしっかりしているので壊れない。そして、それは常に新鮮な舞台となる。
対立が生まれ、空気がどんどん変化する直前のシーンが、つまり冒頭は静かなカードゲームによるシーンというのも、革命という表にすべてが露呈し、対立が露に生まれる前の不思議な空気を作るのに非常に適していて成功している。
最後に美術についてもう少し。本当にユニークなオブジェと単純なしかし本質的なそれが同じ舞台にあり、動かないものと動くものとがあり、非常に象徴的に表されている。終演後に佐藤信氏に尋ねたら、ユニークなオブジェは作ったものだよと言われて驚いたけれども、どこかでみたような感じだなあと思ったら、もう10年以上前の佐藤信氏演出の舞台で使われたそれときき、ああそうかと思った次第。
とにかく見ていて面白いので、多くの方に推薦したい。

シアターイワト
2008年3月20日
構成/演出/美術 佐藤信
出演 笛田宇一郎 KONTA
テアトルコンプリシテの芝居を初めて見た時、エッシャーの騙し絵を思いながら見ていた。佐藤信さんが演出したこの作品を見ていて思ったのは、マグリット、キリコ、エルンストの絵画である。どちらかというとベルギーぽいシュールレアリズムのアーチストのそれである。そういった視覚的な変化にとむそれが、市民革命前の時代感のある、が、すでに詩的に昇華されたテキストと。 黄金の紙の切り取られた舞台の上で繰り広げられるもの。本当に金のように値打ちのあるそれである。我々は過去のこと、舞台上のこととして見ていてはいけない。時にその枠は破られ観客もその中に巻き込まれて行くのだ。 肉体のムーブメントの面白さと、肉体の質感の面白さ。テキストで表現される一方で、リズムや音や光、叫びによって思いを表現したりする。それが、同時多発的に舞台にでてくるから比較しやすい。そんな2時間弱の世界。
難しい芝居なのかと思いきや、テアトルコンプリシテ同様に分かりやすく見ていて面白い。普段は映画もドラマも小説にもふれないゲームと断片的な映像ばかりの世代にも分かりやすく刺激的に作られている。テキストは詩的に昇華されているし、21世紀の時代のスピードにあった変化にとんだ舞台になっていた。
今回も笛田さんがメインでどかんと真ん中にいるんだろう…と。そこにKONTAさんが挑むって形かなあと想像していたら、違っていた。肉体的には、笛田さんは舞踏の竹内靖彦さんに激しく挑まれ拮抗する。そして、その肉体の座標軸。もうひとつ、バレエ、モダンダンスとストリップ、ポールダンス、AVなどに出演したことのある水無潤さんが別のベクトルで対抗する。3次元の関係なのだ。笛田さんのテキストは終始無言の竹内さん、音として多様な表現方法を繰り出して挑むKONTAさんに挑まれる。ここでも拮抗している。
革命は既存の権威が崩壊して行く、もしくはひっくり返されるそれだから、そうした、激しい存在が同じ舞台でどかーんと対峙していることで空気が自然と生まれるのだ。
きちんと稽古し仕組まれたものと、その場の偶然性にまかされる部分が混ざり合う。が、仕掛けがしっかりしているので壊れない。そして、それは常に新鮮な舞台となる。
対立が生まれ、空気がどんどん変化する直前のシーンが、つまり冒頭は静かなカードゲームによるシーンというのも、革命という表にすべてが露呈し、対立が露に生まれる前の不思議な空気を作るのに非常に適していて成功している。
最後に美術についてもう少し。本当にユニークなオブジェと単純なしかし本質的なそれが同じ舞台にあり、動かないものと動くものとがあり、非常に象徴的に表されている。終演後に佐藤信氏に尋ねたら、ユニークなオブジェは作ったものだよと言われて驚いたけれども、どこかでみたような感じだなあと思ったら、もう10年以上前の佐藤信氏演出の舞台で使われたそれときき、ああそうかと思った次第。
とにかく見ていて面白いので、多くの方に推薦したい。
シアターイワト
2008年3月20日
宮益坂編
作 中村呻明(JACROW)米内山陽子(トリコ劇場)櫻井智也(MCR)
演出 池田智哉
以前のように本当に若い劇団の芝居を積極的に観に行く余裕がない。今回は2月に出演してくれた酒巻君が出演するので観に行った。このお芝居は2バージョンあって、もう片方の道玄坂編にははらぺこペンギンやブラジルの作家などが作品を提供している。素舞台、照明なし、衣装なし。座席も40席くらいである。出演者が7名。当然のごとく知り合い関係者が大半となり、客席の空気は暖かい。それは羨ましかった。
先ずは作品。若い作家が自分の世界を見つけようとしてもがいているのを感じてとてもいいなあと思った。それぞれが20分ほどの作品なので、飽きる間もなく終盤に達する。この時間で芝居を成立させようとすると余計なものを削ぐという作業がどうしても必要になる。そこに見えてくるのは作劇の本質の部分だけになる。しかし、それでも自分のマーキングをしたくなってしまうのが作家なんだなと思った。大変失礼かもしれないが、客入れの時にちょっとした芝居があって、それは誰が書いたのか、どれくらい練習したのかも分からないのだが、それが非常に洗練されていて、人間関係も微妙で動いていて、意味もなく面白く感心した次第。
出演者はみな達者だったけれど、きっと得意分野で勝負しているような気がしてならない。芝居全体を見ていて、若い仲間な役者が、集まってノリで作り上げた感があるのだ。出演者がもっている空気が同じで、誰も壊さない。ククルカンの三瓶大介、エレファントムーンの酒巻誉洋、ダブルスチールの島田雅之が安定感があった。
何しろ70分。あっという間に終わるので退屈せずに観られる。見ておいて良かった。
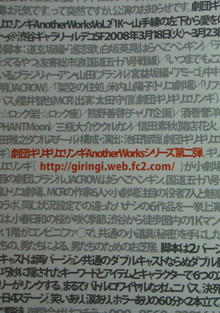
2008年3月19日
ギャラリールデコ5
作 中村呻明(JACROW)米内山陽子(トリコ劇場)櫻井智也(MCR)
演出 池田智哉
以前のように本当に若い劇団の芝居を積極的に観に行く余裕がない。今回は2月に出演してくれた酒巻君が出演するので観に行った。このお芝居は2バージョンあって、もう片方の道玄坂編にははらぺこペンギンやブラジルの作家などが作品を提供している。素舞台、照明なし、衣装なし。座席も40席くらいである。出演者が7名。当然のごとく知り合い関係者が大半となり、客席の空気は暖かい。それは羨ましかった。
先ずは作品。若い作家が自分の世界を見つけようとしてもがいているのを感じてとてもいいなあと思った。それぞれが20分ほどの作品なので、飽きる間もなく終盤に達する。この時間で芝居を成立させようとすると余計なものを削ぐという作業がどうしても必要になる。そこに見えてくるのは作劇の本質の部分だけになる。しかし、それでも自分のマーキングをしたくなってしまうのが作家なんだなと思った。大変失礼かもしれないが、客入れの時にちょっとした芝居があって、それは誰が書いたのか、どれくらい練習したのかも分からないのだが、それが非常に洗練されていて、人間関係も微妙で動いていて、意味もなく面白く感心した次第。
出演者はみな達者だったけれど、きっと得意分野で勝負しているような気がしてならない。芝居全体を見ていて、若い仲間な役者が、集まってノリで作り上げた感があるのだ。出演者がもっている空気が同じで、誰も壊さない。ククルカンの三瓶大介、エレファントムーンの酒巻誉洋、ダブルスチールの島田雅之が安定感があった。
何しろ70分。あっという間に終わるので退屈せずに観られる。見ておいて良かった。
2008年3月19日
ギャラリールデコ5
都はるみの座長公演は25年ぶりのことだという。昭和の大歌手があのだだっ広い新宿コマ劇場で数かすのショーを行い、多くの人を和ませてきた。まぎれもない事実。その新宿コマ劇場は舞台こそ華やかだけれど、客席から天井をみれば、すすけて一部は塗料がはがれてきており老朽化していることはごまかせない。立て替えが予定されているコマ劇場での最後の公演として都はるみは舞台に立ったのだ。
僕が観たのは後半の歌謡ショーの部分。テレビやラジオ、録音で聞き親しんだ都はるみの歌を聴けるものだと思った。しかし、アンコ椿は恋の花から、ちょっと違う。大阪しぐれも北の宿からも好きになった人も、録音できいたそれとは違うのだ。そこには、録音を再現すればいいという歌手の姿はなかった。
都はるみと言えば小節である。唸りである。それは存分に聞かせるのであるが、時にジャズのように軽く流してみたり、シャンソンの歌のそれのように語って聞かせたり、音量を極端に落としてみたり、兎に角いろんなことをしながら唄っている。僕のように日本を代表する歌手だから聞いてみようと言う適当な客でなく、この人のファンならそれにうんと気がついたはずだ。
途中のトークで「北の宿を出した時には賞を総なめし、唄いすぎて唄い方を忘れたくらいです」と語っていた。恩師市川昭介と辿り着いた歌唱法があるはずなのだ。しかし、それが違うのだ。
僕は勝手に思っているのだが、彼女はさらに歌の極みに達してみたいともう何千回と唄った歌の違う側面、もう一歩先はないものかと模索しているのではないかと思う。いい意味で遊んでいるのかもしれない。決して唄い流している感じはしないのだ。そこに、芸の極みを往く孤独な歌手の姿を観たのは僕だけだったのだろうか?

2008年3月17日
新宿コマ劇場
僕が観たのは後半の歌謡ショーの部分。テレビやラジオ、録音で聞き親しんだ都はるみの歌を聴けるものだと思った。しかし、アンコ椿は恋の花から、ちょっと違う。大阪しぐれも北の宿からも好きになった人も、録音できいたそれとは違うのだ。そこには、録音を再現すればいいという歌手の姿はなかった。
都はるみと言えば小節である。唸りである。それは存分に聞かせるのであるが、時にジャズのように軽く流してみたり、シャンソンの歌のそれのように語って聞かせたり、音量を極端に落としてみたり、兎に角いろんなことをしながら唄っている。僕のように日本を代表する歌手だから聞いてみようと言う適当な客でなく、この人のファンならそれにうんと気がついたはずだ。
途中のトークで「北の宿を出した時には賞を総なめし、唄いすぎて唄い方を忘れたくらいです」と語っていた。恩師市川昭介と辿り着いた歌唱法があるはずなのだ。しかし、それが違うのだ。
僕は勝手に思っているのだが、彼女はさらに歌の極みに達してみたいともう何千回と唄った歌の違う側面、もう一歩先はないものかと模索しているのではないかと思う。いい意味で遊んでいるのかもしれない。決して唄い流している感じはしないのだ。そこに、芸の極みを往く孤独な歌手の姿を観たのは僕だけだったのだろうか?
2008年3月17日
新宿コマ劇場
作 小幡欣治 演出 高橋清祐
出演 大滝秀治 奈良岡朋子 日色ともえ 小杉勇二 酒井源司 ほか
傑作。何てほのぼのとして生きる勇気が湧いてきて、人生はいろいろとあるのだけれど、どの人生も素晴らしい!そう感じさせてくれる作品だろう。奈良岡朋子の毅然とした佇まいは女性の強さを感じさせふと見せる弱さには、女の可愛さが滲みでる。酔いながら服の汚れを拭うシーンなど忘れられないだろう。そして、それに惚れてしまった大滝秀治のエロじじいぶり!まるでファルスタッフのような面白さ。真面目に真剣に惚れ込んでいるからこそのエロぶり!日色ともえさんのまともな主婦がそれに翻弄される。翻弄されながらどこか愛しているのであります。それだけでない細川ひさよの強さ、望月ゆかりは自分の役割を抑えながらきちんと芝居の中で足跡を残す。それは、ベテラン小杉勇二もそうで扉の向こうからラスト近くで叫ぶシーンは奈良岡の静の演技の心内を表現し、見事なコントラストで場内の涙を誘う。バーテン役の高橋征郎のツボをさずさないコメディのセンスも感服。安田政利、三浦威、渡辺えりかなどとともに民藝の劇団力を結集した作品だった。フランス映画のヌーベルたちのように、そういった人生を戦争がすべてを壊して行く。そう、こののどかな風景も戦争によって壊されてしまう歴史を暗示しながらも芝居は笑いのうちに終わる。まさに、民藝。抜群の演技力、隙のない演出、きれいな色が印象的な美術に、適切な音楽も良かった。唯一の欠点は暗転が長過ぎることか。圧倒的なこの作品の成功は、奈良岡にとっての「放浪記」となるであろう。

2008年3月16日
東京芸術劇場中ホール
出演 大滝秀治 奈良岡朋子 日色ともえ 小杉勇二 酒井源司 ほか
傑作。何てほのぼのとして生きる勇気が湧いてきて、人生はいろいろとあるのだけれど、どの人生も素晴らしい!そう感じさせてくれる作品だろう。奈良岡朋子の毅然とした佇まいは女性の強さを感じさせふと見せる弱さには、女の可愛さが滲みでる。酔いながら服の汚れを拭うシーンなど忘れられないだろう。そして、それに惚れてしまった大滝秀治のエロじじいぶり!まるでファルスタッフのような面白さ。真面目に真剣に惚れ込んでいるからこそのエロぶり!日色ともえさんのまともな主婦がそれに翻弄される。翻弄されながらどこか愛しているのであります。それだけでない細川ひさよの強さ、望月ゆかりは自分の役割を抑えながらきちんと芝居の中で足跡を残す。それは、ベテラン小杉勇二もそうで扉の向こうからラスト近くで叫ぶシーンは奈良岡の静の演技の心内を表現し、見事なコントラストで場内の涙を誘う。バーテン役の高橋征郎のツボをさずさないコメディのセンスも感服。安田政利、三浦威、渡辺えりかなどとともに民藝の劇団力を結集した作品だった。フランス映画のヌーベルたちのように、そういった人生を戦争がすべてを壊して行く。そう、こののどかな風景も戦争によって壊されてしまう歴史を暗示しながらも芝居は笑いのうちに終わる。まさに、民藝。抜群の演技力、隙のない演出、きれいな色が印象的な美術に、適切な音楽も良かった。唯一の欠点は暗転が長過ぎることか。圧倒的なこの作品の成功は、奈良岡にとっての「放浪記」となるであろう。
2008年3月16日
東京芸術劇場中ホール
「ワニの涙」 川村毅作演出
主演 手塚とおる 根岸季衣
芝居を見る理由は割と単純なことも多い。一生懸命考えて観に行くよりも軽く考えて出かけた方が面白い経験ができることは少なくない。今のところに引越した時に、児童劇の巡業公演をやっていた中村崇君がたまたま僕の友達の後輩で手伝ってくれた。20年以上前に根岸季衣さんと「海と毒薬」という現場で2週間ほどご一緒した。もちろん、向こうはメインキャストで、僕はなぜか参加していたエキストラのような役柄ではあったけれど。その人がやる芝居を観に行きたい。それが観劇の動機。
日本の演劇シーンを引っ張って来た第三エロチカの川村毅さんの作品はしばらく見ていなかったことも大きい理由。そして、主演はあの演劇キング、手塚とおるさんだ。第3エロチカのメンバーも大挙出演する。
観に行ってみたら、ガラガラの客席で驚いた。そして、そのガラガラの客席に芸術を見るぞという気迫が漂っている。まるで祝祭のような客席だった。どうもこの作品は3部作のトリを飾る作品らしかった。観客の多くはこの作品の行く末を見守って作家や出演社と辿り着いたのだろう。僕はそうではない。何の予備知識もない。
自由放送局の盲目のDJ役である手塚は自殺志願者や殺人志願者といった生死のぎりぎりの、さまざまな境界線上にいる人たちの電話を受付けて放送している。しかし、それに怒った一団に殺されてしまう前半。
ほとんど手塚の一人芝居だった。妖気漂う手塚の柔軟な肉体と精神と、あの何とも言えない周波数を出す声の魅力。衣装もすばらしく、美術もシンプルで、その世界観を表現していた。

この作品が好きか?と言われればそうではない。苦手だし、面白いとも思わない。しかし、手塚さんの演技力と川村さんの創りだす空気感は圧倒的であることも事実だ。社会と向き合う姿も素晴らしいが、どうもエンタティメント指向の僕にとって、哲学書のようなこのような作品は本当に苦手だった。
2008年3月12日
シアタートラム
主演 手塚とおる 根岸季衣
芝居を見る理由は割と単純なことも多い。一生懸命考えて観に行くよりも軽く考えて出かけた方が面白い経験ができることは少なくない。今のところに引越した時に、児童劇の巡業公演をやっていた中村崇君がたまたま僕の友達の後輩で手伝ってくれた。20年以上前に根岸季衣さんと「海と毒薬」という現場で2週間ほどご一緒した。もちろん、向こうはメインキャストで、僕はなぜか参加していたエキストラのような役柄ではあったけれど。その人がやる芝居を観に行きたい。それが観劇の動機。
日本の演劇シーンを引っ張って来た第三エロチカの川村毅さんの作品はしばらく見ていなかったことも大きい理由。そして、主演はあの演劇キング、手塚とおるさんだ。第3エロチカのメンバーも大挙出演する。
観に行ってみたら、ガラガラの客席で驚いた。そして、そのガラガラの客席に芸術を見るぞという気迫が漂っている。まるで祝祭のような客席だった。どうもこの作品は3部作のトリを飾る作品らしかった。観客の多くはこの作品の行く末を見守って作家や出演社と辿り着いたのだろう。僕はそうではない。何の予備知識もない。
自由放送局の盲目のDJ役である手塚は自殺志願者や殺人志願者といった生死のぎりぎりの、さまざまな境界線上にいる人たちの電話を受付けて放送している。しかし、それに怒った一団に殺されてしまう前半。
ほとんど手塚の一人芝居だった。妖気漂う手塚の柔軟な肉体と精神と、あの何とも言えない周波数を出す声の魅力。衣装もすばらしく、美術もシンプルで、その世界観を表現していた。
この作品が好きか?と言われればそうではない。苦手だし、面白いとも思わない。しかし、手塚さんの演技力と川村さんの創りだす空気感は圧倒的であることも事実だ。社会と向き合う姿も素晴らしいが、どうもエンタティメント指向の僕にとって、哲学書のようなこのような作品は本当に苦手だった。
2008年3月12日
シアタートラム
ロッシーニ作曲
アルベルトゼッダ指揮 デヴィデリヴァーモア演出
東京フィルハーモニー管弦楽団
出演 チンティアフォルテ アントニーノシラクーザ
ロッシーニの作品は四半世紀前までは「セヴィリアの理髪師」ばかりが上演されてそれ以外の作品はほとんど上演されなかった。もちろん「ウィリアムテル」などの有名な序曲はコンサートなどでは演奏され、ロッシーニは他にもいろんな作品を書いていることは知られている。
近年は「チェネレントラ(シンデレラ)」や「ランスへの旅」など他の作品も上演されるようになって来た。近年は言わばロッシーニルネサンス。今回上演された作品もその序曲は大変有名でさまざまなコンサートで聞いて来たし、アンコール曲としてラテン系の指揮者やオケがよく演奏してくれる作品。
しかし、作品を上演するのは今回が日本初演なのである。もちろん僕も初見。それも、シラクーザ初めとする名歌手が勤めることもあり楽しみにして言った。結果はまあまあ。
先ずはいつもは流暢なイタリアンサウンドをきかせる東京フィルの音が重たい。もちろん手探りで演奏するのは分かるし、欧米のオペラハウスだってそんなものなんだろうけれども、そこにロッシーニのばかばかしいほど明るいサウンドはなかった。それは、日本勢の歌手にも言えて、バス、バリトン以外の声の一部の人は、先ずは正確に唄おうということばかりに頭が言っていたようである。
その点、シラクーザとフォルテはレパートリーとして確立しているのだろう。危なげなく聞けた。
音楽はその程度の不満だったが、それ以上に退屈だったといいたいのが美術と演出である。どうでもいい演出。不必要な美術。へんなところにお金をかけてしまった作品になってしまった。
聞いておいて良かったけれども、それだけの出会いだった。

2008年3月9日
東京文化会館
アルベルトゼッダ指揮 デヴィデリヴァーモア演出
東京フィルハーモニー管弦楽団
出演 チンティアフォルテ アントニーノシラクーザ
ロッシーニの作品は四半世紀前までは「セヴィリアの理髪師」ばかりが上演されてそれ以外の作品はほとんど上演されなかった。もちろん「ウィリアムテル」などの有名な序曲はコンサートなどでは演奏され、ロッシーニは他にもいろんな作品を書いていることは知られている。
近年は「チェネレントラ(シンデレラ)」や「ランスへの旅」など他の作品も上演されるようになって来た。近年は言わばロッシーニルネサンス。今回上演された作品もその序曲は大変有名でさまざまなコンサートで聞いて来たし、アンコール曲としてラテン系の指揮者やオケがよく演奏してくれる作品。
しかし、作品を上演するのは今回が日本初演なのである。もちろん僕も初見。それも、シラクーザ初めとする名歌手が勤めることもあり楽しみにして言った。結果はまあまあ。
先ずはいつもは流暢なイタリアンサウンドをきかせる東京フィルの音が重たい。もちろん手探りで演奏するのは分かるし、欧米のオペラハウスだってそんなものなんだろうけれども、そこにロッシーニのばかばかしいほど明るいサウンドはなかった。それは、日本勢の歌手にも言えて、バス、バリトン以外の声の一部の人は、先ずは正確に唄おうということばかりに頭が言っていたようである。
その点、シラクーザとフォルテはレパートリーとして確立しているのだろう。危なげなく聞けた。
音楽はその程度の不満だったが、それ以上に退屈だったといいたいのが美術と演出である。どうでもいい演出。不必要な美術。へんなところにお金をかけてしまった作品になってしまった。
聞いておいて良かったけれども、それだけの出会いだった。
2008年3月9日
東京文化会館
古川オフィス「シェイクスピアの人々とロンドンミュージカル」〜アダルト編〜
銀座みゆき館で。先日の「ベゴニアと鈴らん」に出演してくださった岡田静さんが、4月の帝劇公演「ラマンチャの男」でカラスコ役を演じる福井貴一さん、東宝等のミュージカルのアンサンブルのトップクラスの人として出演している有希九美さんと3人でライブ。シェイクスピアのリーディングとロンドンミュージカルを唄うという嗜好。福井さんが朗読も歌も絶品で僕は思わずブラボーと言ってしまったくらいです。驚いたのはリチャード3世の第一幕ニ場のシーンでグロスター公を演じた福井さんは、悪漢なイメージを全く出さない、むしろ誠実な人間のような空気で演じられた。それがものすごい迫力なのだ。悪漢は自分の行う卑劣な行為を当然のこととしてやってしまうものだ。それに対するアンは感情むき出しでちょっと損でした。有希さんは、本当に少女みたいな方なんだと思ってしまいました。岡田さんにはきっと合わないマクベス夫人。それがテキストに身を委ね普通に演じられる。ものすごくマクベス夫人の恐ろしさが出ていた。
後半の歌。岡田さんは1曲目のオペラ座の怪人では高音の音程が怪しかったりするのだけれど、「私はイエスがわからない」「夢破れて」などもう完璧な美味さ。声は出るし味はあるし絶品だった。岡田さんに歌を書いたという大それたことを良く出来たようなあと思った次第。そして、驚いたのは福井さん。美味いとは思っていたけれど、ファントムのミュージックオブザナイトやキャッツの終幕に唄われる劇場猫なんかは、2時間半の芝居が見渡せるように唄って見せてくれた。福井さんと岡田さんにブラボーです。有希さんは、泣かないでアルゼンチーナ、メモリーなどを名曲を唄うから、どうしても名舞台のそれと比較してしまう。台本でも選曲でも損をされていたと思いました。ご自分の属するオフィスの主催公演なのだから、もっとわがままを言えばいいのにと思いました。
銀座みゆき館という小さな空間で福井さんや岡田さんらを見られるのは本当に贅沢です。
日本工学院専門学校 俳優/声優科卒業公演 「デンキ島」Bキャスト。6号館1階で有馬自由演出。これは、工学院の俳優声優課の卒業公演。これが良かった。蓬莱竜太さんの骨太な台本を若いひとならではのとにかく思い切り!で見せてくれた。面白かった。 何か泣けちゃいました。きっと、モダンスイマーズもワンオアエイトも学生時代はこんな勢いで芝居やっていたのだろうなと思ったのです。出演している人たちも来年になったら何人芝居やっているのかなとも思ったりしていたのだけれど、やっている本人は今の芝居をヤリきることだけを考えて疾走している。思い切り叫び、走り、身体を動かす。有馬自由は余計なことをさせない。この若者たちのもっている芯の部分だけで勝負させる。それがいいのです。美味く見せてやろうと思った瞬間に敗北してしまうのだから。 いやあ、良かったです。蒲田の街をしばらく離れたくなくてぶらぶらしてしまいました。みな良かったんだけれど、特に小森碧、多田聡、高橋昭伍、寺井慧、坂入絵里奈、桂木健之朗、高橋千絵が良かったです。
からっぽの湖
俳優力で見せた芝居。野間口湖にネッシーみたいなノッシーがいるいない?そんな話だけでもないか。もう別にストーリーにこだわる物語系お芝居を観に行った人は面食らったかもしれない。むしろ、それはどうでもいいくらい。登場する人間関係のあれそれで見せて行く。台本を元ネタに俳優たちが、そこに人間の何を発見するかを見いだすのだ。
ウェルメイドなコメディとか、いつものアガペなものを望んでいる人には不満なのかもしれないけどね。僕は松尾さんの芝居は、BIZシリーズがとにかく好きなんです。あと、地獄八景みたいな落語もの。一行レビューでの酷評はいったいなんなのか、良く分からないです。
http://www.g2produce.com/agape/12/com_matsuo.mov
恋はコメディ
加納幸和さんの品の良さが光った演出。何かヘンテコな山場などは作らないんですね。台本がしっかりしているからいいではないか!とそれだけで。見た直後はその良さに気がつかなかった。しかし、あとからじわりと来る舞台。王道なコメディ。正統な話。こういうお芝居は役者さんのものすごい集中力とアンサンブルの妙みたいなものが大切です。3人の女優も2人の男優もやはりプロの仕事。レベルは高いし、作品と俳優の良さを大切にする加納さんの演出も派手ではないけど見事なんです。こういうのって、実はヘタクソな著名な演出家っていますよね?
秋吉久美子さんの自由奔放さ、浅岡ルリ子さんがいろんなことを背負って演じ、渡辺えりさんがメチャクチャ可愛い。可愛いんです。天使だなあの方は!そういう素晴らしい女優3人のおかげで、男優二人はのびのびと美味しいところを取りまくり。
浅岡さんは帝国劇場で座長公演を何本もされた方だと思うと、9800円というチケ代も高くないと考えなくてはならないのか。これだけのキャストでガラガラの客席はやはりチケ代を受け入れてもらえなかったのか。劇場をPARCOでやったらもっと良かったのになと思いました。
ファミリー大戦争〜オヤジの嫁さん〜
キャスティングが素晴らしく、素晴らしいからこそ欠点も見えたものでした。先ずは赤井英和さんの演技が上手いのか下手なのかが良く分からないです。朝丘雪路さんが台詞を噛んでいるのかわざとやっているのか。台詞を間違えたのか、ふりをしているのか分かりません。役名まで(わざと?)間違え全部客席の笑いとして、どんどんどんどん和やかな客席になるのがスゴい。超魅力的な女性であり女優であることは間違いない。可愛いです。そういったエイリアンがトップ二人です。そんな中で正司花江さんをおくことで舞台をどかんと引き締めた。暴投かと思うものも受け取るキャッチャーす。大好きです。かしまし娘。
このお芝居には、今はなくなった藤山寛美さんや、でんすけさんがやっていた時代の芝居小屋での演劇の空気が残っていまして、そりゃあ古いタイプの芝居かもしれませんが、それが悪いわけではないのです.何しろお客さんが大喜びなんですから!
男3兄弟は内海光司さんが、ちょっと抑えたポジションになり、後輩の中村俊太さんと工藤大輔さんが目立つようにしていてデカイところを見せてました。が、女3姉妹がもう少し美人がいたり、太っていたりと個性が欲しい。何かダメでした。3人とも芝居もややヤバいしなあ。このキャスティングがイマイチでした。まあ、僕の好みってことかもしれませんけど。
知り合いの中村俊太さんは、こういう現場もこなせる力量があるのかと感心しました。あっ、言っちまった!って両手で口を抑えるところ。それをこの登場人物の癖としてやってるわけですが、これがね。もうスゴいのなんのって。ウォーキングスタッフのときとは別人のようで別人でないのです。芝居の中で肝になっていました。見事。
やっぱり猫が好き&恋愛日記
演出家和田憲明さんの勉強会の発表会です。ファミリー戦争の中で、これ、ホントにアドリブだというか、そういうシーンがあるんです。洗濯干しているシーンなんですけど、お客も湧くのですが、アドリブに見える。おそらくホントにアドリブ。朝丘さんがボケて、正司さんが見事に受ける。きっとアドリブでしょう。それが稽古して、アドリブに見えるくらいにしてしまうのが、こちら。いやあ、少しでも集中力が切れると何もかもぶちこわしな舞台なんですけど、それがね。上手く行っちまうんですよ。いやあ。広瀬麻衣ちゃん可愛いし、ますます上手く。見事。自分のハードルをあげて越えて行く人はホントにスゴいです。後半の女の子二人はメチャクチャ美人で嬉しくなるくらいでした。もうそれだけで見ている方は嬉しいのですが、芝居も見事。ただ、これって等身大でやってる感じなんです。向田邦子さんの台本なんかをやったらどうなるのか見てみたいと思いました。
僕らは今を変えられますか?
Nの2乗の公演です。永峰明さんはテレビや吉本の世界で大重鎮でスゴい人です。ものすごい人なのです。その人がうつ劇団なので、ものすごい期待をして観に行った。向田邦子級の、そういう出会いがあるのだと思って観に行きました。
芝居の作り方は誠実でした。台本に抑えが山ほどある。多くの登場人物をさばいて行く腕前も見事でやはりプロの仕事はすげえなあと思ってみてました。後半から芝居が展開して行くところは、この芝居に客がのめり込んでいないと、芝居がつく嘘を受け入れてもらえなくなります。ストーリーを追うように見て行くと、そんなことは起きない。起こらないとなってしまうことがあるのです。今回の芝居で、分かり易くいうと、人間は廻りで危険なことが起きていれば逃げるもの。避けるもの。自分が助かるために行動する。芝居ではそうならないことがある。誰ひとり逃げない。おかしいです。しかし、芝居にのめり込んでいると、そういうことを全部受け入れられます。演出はそういう嘘を客が許容してくれる空気を創りだせたら勝ちです。残念ながら僕はのめり込んでいけずに、そこに引っかかってついていけなくなりました。
それは、役者の力というかそういうことにも関係しているのかもしれません。このお芝居は設定した舞台の空気がどんどんと濃密になっていくことが絶対的に必要で、そのためには全員のアンサンブルが必要なんです。舞台にでている役者の何人かがそこから逸脱していると全部を壊してしまうのです。今回は田村通隆や比嘉礼子といったうまい役者もいましたが、そうでない人もいました。しかし、劇団なのでいろんな力量の人に舞台に立ってもらう必要もあるのだと思います。そういう人が、いたことでのめり込めなくなったのだと思います。僕は稽古していてちょっとでも空気が淀むなと思ったら、直ぐに台本をカットしてしまいます。永峰さんはどうなんだろうと思いながら見ていました。
芝居を観に行って、あの永峰さんが、いろいろと気を使いながら劇場にいたことがとてもびっくりしました。僕はちょっと挨拶しただけで直ぐに帰ってしまいましたが、今回のようにまた誘って頂けたらもう一度観に行ってみたいなというのと、稽古している現場を見てみたいです。気になる演劇集団です。
星屑の街 新宿歌舞伎町編
前川清さんの歌がスゴい!歌をきいてるだけで楽しめる!先ずはそこでした。星屑のメンバーの活躍の仕方がイマイチでファンとしては残念でした。コマという劇場はとても特殊な殿堂のような劇場です。いまや帝国劇場でもほとんどできなくなった座長芝居以外を受け入れる劇場ではないのです。いまや座長公演で1ヶ月お客を埋められる大スターはほとんどいないというか。観客がいなくなった。高齢化?劇場に行かない?まあ、そういうことです。今の若い観客は役者に魅力は求めるし、役者を追うけれど、それ以上に芝居自体を求める。アンサンブルを求めるようになったのだと思います。前川清さんはそういう意味で座長のできる数少ないスターです。その証拠に、梅沢富美男さんと長いことやっている明治座の公演は今でも大人気で、明治座の夏を彩る名番組です。そして、歌のスゴさ。僕は別にクールファイブのフアンでも前川さんのフアンでもありません。ラサール石井さんや小宮孝泰さん、星屑メンバーを見たくて劇場に行ったのです。しかし、聞いてみると、やはり、この芝居の一番の魅力は前川清さんの圧倒的な歌力でした。スゴいです。ああ、こういう大スターがコマには合うのだよと思った。星屑の街は、素晴らしいアンサンブルで作り上げて来た名シリーズです。小宮さんらは、それをしっかり守ろうと大活躍。一方で清水宏さんは、このコマ劇場っていう空間を楽しもうぜと、コマ劇場教に改宗したような光を放つ。いやあ、芝居って面白いですね。お願いは、星屑の街シリーズをこれで辞めるということだけはしないで欲しい。最後がコレはちょっと違うかなと思いました。あと、演劇ファンにS席12000円はちと高かったです。
銀座みゆき館で。先日の「ベゴニアと鈴らん」に出演してくださった岡田静さんが、4月の帝劇公演「ラマンチャの男」でカラスコ役を演じる福井貴一さん、東宝等のミュージカルのアンサンブルのトップクラスの人として出演している有希九美さんと3人でライブ。シェイクスピアのリーディングとロンドンミュージカルを唄うという嗜好。福井さんが朗読も歌も絶品で僕は思わずブラボーと言ってしまったくらいです。驚いたのはリチャード3世の第一幕ニ場のシーンでグロスター公を演じた福井さんは、悪漢なイメージを全く出さない、むしろ誠実な人間のような空気で演じられた。それがものすごい迫力なのだ。悪漢は自分の行う卑劣な行為を当然のこととしてやってしまうものだ。それに対するアンは感情むき出しでちょっと損でした。有希さんは、本当に少女みたいな方なんだと思ってしまいました。岡田さんにはきっと合わないマクベス夫人。それがテキストに身を委ね普通に演じられる。ものすごくマクベス夫人の恐ろしさが出ていた。
後半の歌。岡田さんは1曲目のオペラ座の怪人では高音の音程が怪しかったりするのだけれど、「私はイエスがわからない」「夢破れて」などもう完璧な美味さ。声は出るし味はあるし絶品だった。岡田さんに歌を書いたという大それたことを良く出来たようなあと思った次第。そして、驚いたのは福井さん。美味いとは思っていたけれど、ファントムのミュージックオブザナイトやキャッツの終幕に唄われる劇場猫なんかは、2時間半の芝居が見渡せるように唄って見せてくれた。福井さんと岡田さんにブラボーです。有希さんは、泣かないでアルゼンチーナ、メモリーなどを名曲を唄うから、どうしても名舞台のそれと比較してしまう。台本でも選曲でも損をされていたと思いました。ご自分の属するオフィスの主催公演なのだから、もっとわがままを言えばいいのにと思いました。
銀座みゆき館という小さな空間で福井さんや岡田さんらを見られるのは本当に贅沢です。
日本工学院専門学校 俳優/声優科卒業公演 「デンキ島」Bキャスト。6号館1階で有馬自由演出。これは、工学院の俳優声優課の卒業公演。これが良かった。蓬莱竜太さんの骨太な台本を若いひとならではのとにかく思い切り!で見せてくれた。面白かった。 何か泣けちゃいました。きっと、モダンスイマーズもワンオアエイトも学生時代はこんな勢いで芝居やっていたのだろうなと思ったのです。出演している人たちも来年になったら何人芝居やっているのかなとも思ったりしていたのだけれど、やっている本人は今の芝居をヤリきることだけを考えて疾走している。思い切り叫び、走り、身体を動かす。有馬自由は余計なことをさせない。この若者たちのもっている芯の部分だけで勝負させる。それがいいのです。美味く見せてやろうと思った瞬間に敗北してしまうのだから。 いやあ、良かったです。蒲田の街をしばらく離れたくなくてぶらぶらしてしまいました。みな良かったんだけれど、特に小森碧、多田聡、高橋昭伍、寺井慧、坂入絵里奈、桂木健之朗、高橋千絵が良かったです。
からっぽの湖
俳優力で見せた芝居。野間口湖にネッシーみたいなノッシーがいるいない?そんな話だけでもないか。もう別にストーリーにこだわる物語系お芝居を観に行った人は面食らったかもしれない。むしろ、それはどうでもいいくらい。登場する人間関係のあれそれで見せて行く。台本を元ネタに俳優たちが、そこに人間の何を発見するかを見いだすのだ。
ウェルメイドなコメディとか、いつものアガペなものを望んでいる人には不満なのかもしれないけどね。僕は松尾さんの芝居は、BIZシリーズがとにかく好きなんです。あと、地獄八景みたいな落語もの。一行レビューでの酷評はいったいなんなのか、良く分からないです。
http://www.g2produce.com/agape/12/com_matsuo.mov
恋はコメディ
加納幸和さんの品の良さが光った演出。何かヘンテコな山場などは作らないんですね。台本がしっかりしているからいいではないか!とそれだけで。見た直後はその良さに気がつかなかった。しかし、あとからじわりと来る舞台。王道なコメディ。正統な話。こういうお芝居は役者さんのものすごい集中力とアンサンブルの妙みたいなものが大切です。3人の女優も2人の男優もやはりプロの仕事。レベルは高いし、作品と俳優の良さを大切にする加納さんの演出も派手ではないけど見事なんです。こういうのって、実はヘタクソな著名な演出家っていますよね?
秋吉久美子さんの自由奔放さ、浅岡ルリ子さんがいろんなことを背負って演じ、渡辺えりさんがメチャクチャ可愛い。可愛いんです。天使だなあの方は!そういう素晴らしい女優3人のおかげで、男優二人はのびのびと美味しいところを取りまくり。
浅岡さんは帝国劇場で座長公演を何本もされた方だと思うと、9800円というチケ代も高くないと考えなくてはならないのか。これだけのキャストでガラガラの客席はやはりチケ代を受け入れてもらえなかったのか。劇場をPARCOでやったらもっと良かったのになと思いました。
ファミリー大戦争〜オヤジの嫁さん〜
キャスティングが素晴らしく、素晴らしいからこそ欠点も見えたものでした。先ずは赤井英和さんの演技が上手いのか下手なのかが良く分からないです。朝丘雪路さんが台詞を噛んでいるのかわざとやっているのか。台詞を間違えたのか、ふりをしているのか分かりません。役名まで(わざと?)間違え全部客席の笑いとして、どんどんどんどん和やかな客席になるのがスゴい。超魅力的な女性であり女優であることは間違いない。可愛いです。そういったエイリアンがトップ二人です。そんな中で正司花江さんをおくことで舞台をどかんと引き締めた。暴投かと思うものも受け取るキャッチャーす。大好きです。かしまし娘。
このお芝居には、今はなくなった藤山寛美さんや、でんすけさんがやっていた時代の芝居小屋での演劇の空気が残っていまして、そりゃあ古いタイプの芝居かもしれませんが、それが悪いわけではないのです.何しろお客さんが大喜びなんですから!
男3兄弟は内海光司さんが、ちょっと抑えたポジションになり、後輩の中村俊太さんと工藤大輔さんが目立つようにしていてデカイところを見せてました。が、女3姉妹がもう少し美人がいたり、太っていたりと個性が欲しい。何かダメでした。3人とも芝居もややヤバいしなあ。このキャスティングがイマイチでした。まあ、僕の好みってことかもしれませんけど。
知り合いの中村俊太さんは、こういう現場もこなせる力量があるのかと感心しました。あっ、言っちまった!って両手で口を抑えるところ。それをこの登場人物の癖としてやってるわけですが、これがね。もうスゴいのなんのって。ウォーキングスタッフのときとは別人のようで別人でないのです。芝居の中で肝になっていました。見事。
やっぱり猫が好き&恋愛日記
演出家和田憲明さんの勉強会の発表会です。ファミリー戦争の中で、これ、ホントにアドリブだというか、そういうシーンがあるんです。洗濯干しているシーンなんですけど、お客も湧くのですが、アドリブに見える。おそらくホントにアドリブ。朝丘さんがボケて、正司さんが見事に受ける。きっとアドリブでしょう。それが稽古して、アドリブに見えるくらいにしてしまうのが、こちら。いやあ、少しでも集中力が切れると何もかもぶちこわしな舞台なんですけど、それがね。上手く行っちまうんですよ。いやあ。広瀬麻衣ちゃん可愛いし、ますます上手く。見事。自分のハードルをあげて越えて行く人はホントにスゴいです。後半の女の子二人はメチャクチャ美人で嬉しくなるくらいでした。もうそれだけで見ている方は嬉しいのですが、芝居も見事。ただ、これって等身大でやってる感じなんです。向田邦子さんの台本なんかをやったらどうなるのか見てみたいと思いました。
僕らは今を変えられますか?
Nの2乗の公演です。永峰明さんはテレビや吉本の世界で大重鎮でスゴい人です。ものすごい人なのです。その人がうつ劇団なので、ものすごい期待をして観に行った。向田邦子級の、そういう出会いがあるのだと思って観に行きました。
芝居の作り方は誠実でした。台本に抑えが山ほどある。多くの登場人物をさばいて行く腕前も見事でやはりプロの仕事はすげえなあと思ってみてました。後半から芝居が展開して行くところは、この芝居に客がのめり込んでいないと、芝居がつく嘘を受け入れてもらえなくなります。ストーリーを追うように見て行くと、そんなことは起きない。起こらないとなってしまうことがあるのです。今回の芝居で、分かり易くいうと、人間は廻りで危険なことが起きていれば逃げるもの。避けるもの。自分が助かるために行動する。芝居ではそうならないことがある。誰ひとり逃げない。おかしいです。しかし、芝居にのめり込んでいると、そういうことを全部受け入れられます。演出はそういう嘘を客が許容してくれる空気を創りだせたら勝ちです。残念ながら僕はのめり込んでいけずに、そこに引っかかってついていけなくなりました。
それは、役者の力というかそういうことにも関係しているのかもしれません。このお芝居は設定した舞台の空気がどんどんと濃密になっていくことが絶対的に必要で、そのためには全員のアンサンブルが必要なんです。舞台にでている役者の何人かがそこから逸脱していると全部を壊してしまうのです。今回は田村通隆や比嘉礼子といったうまい役者もいましたが、そうでない人もいました。しかし、劇団なのでいろんな力量の人に舞台に立ってもらう必要もあるのだと思います。そういう人が、いたことでのめり込めなくなったのだと思います。僕は稽古していてちょっとでも空気が淀むなと思ったら、直ぐに台本をカットしてしまいます。永峰さんはどうなんだろうと思いながら見ていました。
芝居を観に行って、あの永峰さんが、いろいろと気を使いながら劇場にいたことがとてもびっくりしました。僕はちょっと挨拶しただけで直ぐに帰ってしまいましたが、今回のようにまた誘って頂けたらもう一度観に行ってみたいなというのと、稽古している現場を見てみたいです。気になる演劇集団です。
星屑の街 新宿歌舞伎町編
前川清さんの歌がスゴい!歌をきいてるだけで楽しめる!先ずはそこでした。星屑のメンバーの活躍の仕方がイマイチでファンとしては残念でした。コマという劇場はとても特殊な殿堂のような劇場です。いまや帝国劇場でもほとんどできなくなった座長芝居以外を受け入れる劇場ではないのです。いまや座長公演で1ヶ月お客を埋められる大スターはほとんどいないというか。観客がいなくなった。高齢化?劇場に行かない?まあ、そういうことです。今の若い観客は役者に魅力は求めるし、役者を追うけれど、それ以上に芝居自体を求める。アンサンブルを求めるようになったのだと思います。前川清さんはそういう意味で座長のできる数少ないスターです。その証拠に、梅沢富美男さんと長いことやっている明治座の公演は今でも大人気で、明治座の夏を彩る名番組です。そして、歌のスゴさ。僕は別にクールファイブのフアンでも前川さんのフアンでもありません。ラサール石井さんや小宮孝泰さん、星屑メンバーを見たくて劇場に行ったのです。しかし、聞いてみると、やはり、この芝居の一番の魅力は前川清さんの圧倒的な歌力でした。スゴいです。ああ、こういう大スターがコマには合うのだよと思った。星屑の街は、素晴らしいアンサンブルで作り上げて来た名シリーズです。小宮さんらは、それをしっかり守ろうと大活躍。一方で清水宏さんは、このコマ劇場っていう空間を楽しもうぜと、コマ劇場教に改宗したような光を放つ。いやあ、芝居って面白いですね。お願いは、星屑の街シリーズをこれで辞めるということだけはしないで欲しい。最後がコレはちょっと違うかなと思いました。あと、演劇ファンにS席12000円はちと高かったです。
文化の日。サントリーホールへ。この秋、東京の音楽ファンから最大の期待をもって迎えられたミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の演奏会だ。この楽団はマーラーなどの名曲を世界初演した楽団であるとともに、ルドルフケンペとチェリビダッケという二大指揮者で戦後の楽壇をリードしてきた。僕は幸いにもチェリビダッケのコンサートは何回も聴いたことがある。最初の機会の時、驚いた。名曲「展覧会の絵」が真新しく聞こえた。新曲のようなのだ。そして、100人以上の一流の演奏者の綿密なアンサンブル!続いて聴いたシューマンの交響曲。つまらないと思っていた楽曲がこれほど豊かな楽想に紡がれているのだと驚いた。東京でチケットを取るのが不可能だと思うと、アジアツアーの時に香港まで演奏会を聞きにもいった。一生忘れないであろうチャイコフスキーの5番の交響曲は極限までテンポを遅くし、ひとつひとつの音符の魅力、フレ−ジングの素晴らしさを丁寧に披露してくれた。ミュンヘンフィルは、著名なカラヤンに率いられたベルリンフィルハーモニー管弦楽団と並ぶドイツを代表するオーケストラなのだ。むしろ、南の首都バイエルン地方の代表として音楽ファンの中には、ベルリンフィルよりも高く評価する人も少なくないオーケストラだった。しかし、偉大なチェリビダッケがなくなって、つまり偉大なリーダーを失いこの楽壇は輝きを失う。
そこに登場したのがクリスチャンティーレマンなのだ。1959年生まれ。まだ40代という若さだ。ドイツの地方オペラなどで経験を積み出てきたのだ。僕はもうコンサートには30年以上も通いつめていて、19世紀生まれの、もしくは、20世紀初頭に生まれた大指揮者を山ほどきいてきたものだから、今の指揮者の器の小ささ、商業主義、おもねる音楽、軽い音楽にあまり興味を示さなかった。演劇が僕の芸術に関する興味の中心になったこともあり、どんどんとコンサート通いは減り、本当に素晴らしい演奏会と思える時以外はいかなくなってしまったのだ。
ティーレマンは何回かオペラの来日公演の時にきいていたが、正直あんまりピンとこなかった。しかし、2003年にNHK交響楽団やバイエン国立歌劇場の指揮者として何回もきいた高齢なウォルフガングサバリッシュとウィーンフィルハーモニー管弦楽団との演奏会を楽しみにしていた。しかし、来日はキャンセル。代役がティーレマン。その時の素晴らしさ。ええ、何だこいつ!と思ったのだ。聞き慣れた楽曲を洗い直し音楽を組み立てていた。伝統を大切にしつつも、自らの音楽の芯をもっている。
もう大指揮者はいないのだと思っていたのだが、ドイツのヨーロッパの文化は、こうして若く新しい大指揮者を生んだのだ。文化の厚みが生んだのだと思う。
ミュンヘンフィルの音楽監督にティーレマンが2004年に就任した時に誰もが楽しみにしたものだ。どんな音楽を聴かせるのかと!そして、3年という時を経て満を持しての来日。
今日はブラームスの交響曲第一番。そして、リヒャルトシュトラウスの「死と変容」と「ドンファン」。素晴らしかった。アンコールではワーグナーの「ニュールンベルグのマイスタージンガー」の前奏曲。ドイツオーストリア音楽文化の最高峰の演奏だった。
会場にはなかにし礼さんや小泉前首相もきていた。ま、どうでもいいんだけど。素晴らしい演奏に心を打たれ、年齢のことも考えると、おそらく僕の人生の最後までこの新たな巨匠の音楽を聴き続けるのだろうな。その今日は第二回目だったんだなと思った次第。
明日も聴く。あしたはブルックナーの交響曲第5番。2001年に亡くなったギュンターワントの死の直前の来日公演で取り上げられた大曲だ。僕は同じプログラムを2回聴きに行き、感動に打ち震えた。それと同じ曲。もうあれ以上の感動はないのだと思っていたのだが、楽しみにしている。
2007年11月3日
サントリーホール
最新記事
(01/06)
(12/25)
(08/05)
(06/30)
(12/16)
(08/21)
(04/10)
(09/25)
(11/30)
(11/18)
(11/03)
(10/04)
(09/19)
(08/28)
(06/25)
(06/10)
(12/30)
(02/21)
(12/31)
(09/28)
(06/09)
(05/12)
(12/31)
(09/08)
(06/02)
プロフィール
HN:
佐藤治彦 Haruhiko SATO
HP:
性別:
男性
職業:
演劇ユニット経済とH 主宰
趣味:
海外旅行
自己紹介:
演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員
カテゴリー
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
フリーエリア
最新CM
[08/24 おばりーな]
[02/18 清水 悟]
[02/12 清水 悟]
[10/17 栗原 久美]
[10/16 うさきち]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(12/05)
(12/07)
(12/08)
(12/09)
(12/10)
(12/11)
(12/29)
(01/03)
(01/10)
(01/30)
(02/13)
(03/09)
(03/12)
(03/16)
(03/17)
(03/19)
(03/20)
(03/20)
(03/22)
(03/22)
(03/23)
(03/24)
(03/28)
(04/01)
(04/01)
カウンター
