自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
パッパーノ指揮 聖チェチーリア音楽院管弦楽団
ボリスベレゾフスキー ピアノ
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」シンフォニア
リスト ピアノ協奏曲第1番
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
(Pf:ボリス・ベレゾフスキー/アンコール)
サン=サーンス(ゴドフスキ編曲):白鳥
チャイコフスキー:四季~10月
(アンコール)プッチーニ:マノン・レスコー~間奏曲
ポンキエッリ:歌劇「ジョコンダ」-「時の踊り」から(最後の部分)


「突っ走る悲愴。パッパーノは21世紀のカラヤン」
とても分かりやすい演奏だった。去年来日するまでイギリスのロイヤルオペラは18年くらい来日しなかったのだが、その理由は明らか。オケが酷かったのだ。ロンドンで(特にバレエの公演)なと聴くと、下手すると、これ日本のアマチュアオケ以下かもと思うような演奏を聴かされて驚いたものだ。それが昨年の来日で聴かせたロイヤルオペラのオケ。全盛期とまでは言わないが確実に復活したのは間違いない。その立役者がアントニオ・パッツパーノだ。自ら故郷はイギリスというが、両親ともイタリア人なので国際的なイタリア人というのが正しいのでは?
このイタリアのオケも聴くのは始めてではないのだが、前に聴いたときの印象がほとんどない。その程度の演奏だったのだろう。しかし今宵の演奏は心に残る演奏だ。それは、音が溌剌としていてどこまでもハイテンションで観客をぐいぐい引っ張っていく演奏だからだ。イタリア的にカンタービレも抜群に聴かせてメロディを歌いまくることも特徴。何かそのノリはロックのそれに近いものがあった。
リストのピアノ協奏曲は、丁々発止の演奏というのは、こういうのだよね?と言われたら大きくうなづきたくなるような演奏。ベレゾフスキーの俺は技術力すげえんだというのが、俺は二枚目だ、抱いてやるよ!みたいな傲慢な感じもちょっと感じるくらいのグイグイ感。アンコールの白鳥などはさらっとしていて好感。いやリストのピアノ協奏曲第一番の生演奏ではきっと生涯で一番いいものだったと思う。
速めのテンポ、輪郭がくっきりとした音色とリズム。悲愴でもそれは変わらなかった。突っ走る悲愴といったらいいのだろうか?出だしから暗さというよりはグイグイ感。観客は大喝采だったし、僕もたまにはこういう演奏を聴かされるのは嫌じゃない。ただ、先日きいたNHK交響楽団/ブロムシュテットのチャイコフスキー第5番の名演と比べると、いい意味で幼稚な演奏といってもいいんだと思う。
きっとあまりオーケストラの演奏会を多く聴いてない人は、こういう演奏会から入るのが理想的だ。きっとカラヤンが21世紀に生きていたらこんな演奏をしたのだと思う。パッパーノのライバルは、きっとドゥダメルだろう。
2011年10月3日@NHKホール
ボリスベレゾフスキー ピアノ
ヴェルディ 歌劇「アイーダ」シンフォニア
リスト ピアノ協奏曲第1番
チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
(Pf:ボリス・ベレゾフスキー/アンコール)
サン=サーンス(ゴドフスキ編曲):白鳥
チャイコフスキー:四季~10月
(アンコール)プッチーニ:マノン・レスコー~間奏曲
ポンキエッリ:歌劇「ジョコンダ」-「時の踊り」から(最後の部分)
「突っ走る悲愴。パッパーノは21世紀のカラヤン」
とても分かりやすい演奏だった。去年来日するまでイギリスのロイヤルオペラは18年くらい来日しなかったのだが、その理由は明らか。オケが酷かったのだ。ロンドンで(特にバレエの公演)なと聴くと、下手すると、これ日本のアマチュアオケ以下かもと思うような演奏を聴かされて驚いたものだ。それが昨年の来日で聴かせたロイヤルオペラのオケ。全盛期とまでは言わないが確実に復活したのは間違いない。その立役者がアントニオ・パッツパーノだ。自ら故郷はイギリスというが、両親ともイタリア人なので国際的なイタリア人というのが正しいのでは?
このイタリアのオケも聴くのは始めてではないのだが、前に聴いたときの印象がほとんどない。その程度の演奏だったのだろう。しかし今宵の演奏は心に残る演奏だ。それは、音が溌剌としていてどこまでもハイテンションで観客をぐいぐい引っ張っていく演奏だからだ。イタリア的にカンタービレも抜群に聴かせてメロディを歌いまくることも特徴。何かそのノリはロックのそれに近いものがあった。
リストのピアノ協奏曲は、丁々発止の演奏というのは、こういうのだよね?と言われたら大きくうなづきたくなるような演奏。ベレゾフスキーの俺は技術力すげえんだというのが、俺は二枚目だ、抱いてやるよ!みたいな傲慢な感じもちょっと感じるくらいのグイグイ感。アンコールの白鳥などはさらっとしていて好感。いやリストのピアノ協奏曲第一番の生演奏ではきっと生涯で一番いいものだったと思う。
速めのテンポ、輪郭がくっきりとした音色とリズム。悲愴でもそれは変わらなかった。突っ走る悲愴といったらいいのだろうか?出だしから暗さというよりはグイグイ感。観客は大喝采だったし、僕もたまにはこういう演奏を聴かされるのは嫌じゃない。ただ、先日きいたNHK交響楽団/ブロムシュテットのチャイコフスキー第5番の名演と比べると、いい意味で幼稚な演奏といってもいいんだと思う。
きっとあまりオーケストラの演奏会を多く聴いてない人は、こういう演奏会から入るのが理想的だ。きっとカラヤンが21世紀に生きていたらこんな演奏をしたのだと思う。パッパーノのライバルは、きっとドゥダメルだろう。
2011年10月3日@NHKホール
PR
脚本・演出・出演/澤田育子
主演/藤田記子
特別友情出演/MINAKO(米米CLUB)
/千代田 信一(拙者ムニエル)、松山 尚子(宝井プロジェクト)
遠藤 かおる(吉本新喜劇)、石川 伸一郎(ねじリズム )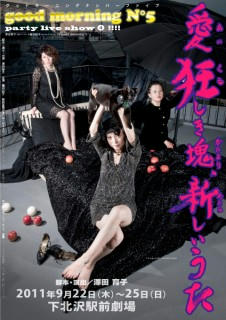

「観客を元気にしてくれる粒よりの俳優たち」
澤田育子は10年ほど前に名前を公表せずに「ゴキブリコンビナート」で青あざを作りながら芝居をしていた人である。元々の華やかで派手な顔からはちょっと距離感のあることをするのは昔からの嗜好である。それがすごくいい意味で作品作りに反映されていて面白かった。上手い役者が最高のテンションで、自分の演技の力と得意芸をトレーディングカードを切るように出してくる。
最初はちょっとひいてしまったが、だんだんと引き込まれていくから不思議だ。遠藤かおる(男)のMr.ビーンの真似も米米クラブのMINAKOのはじけつ内田裕也の真似も面白い。いやあ、笑ったし楽しんだ。90分があっという間だった。二枚目の石川さんは身を投げ出して頑張っていて好感。松山尚子さんは初見だか力のあるコメディアンヌであった。役者の質も粒ぞろいだね。美術もチープ感はあるが実は相当凝っていた。
2011年9月23日 駅前劇場
主演/藤田記子
特別友情出演/MINAKO(米米CLUB)
/千代田 信一(拙者ムニエル)、松山 尚子(宝井プロジェクト)
遠藤 かおる(吉本新喜劇)、石川 伸一郎(ねじリズム )
「観客を元気にしてくれる粒よりの俳優たち」
澤田育子は10年ほど前に名前を公表せずに「ゴキブリコンビナート」で青あざを作りながら芝居をしていた人である。元々の華やかで派手な顔からはちょっと距離感のあることをするのは昔からの嗜好である。それがすごくいい意味で作品作りに反映されていて面白かった。上手い役者が最高のテンションで、自分の演技の力と得意芸をトレーディングカードを切るように出してくる。
最初はちょっとひいてしまったが、だんだんと引き込まれていくから不思議だ。遠藤かおる(男)のMr.ビーンの真似も米米クラブのMINAKOのはじけつ内田裕也の真似も面白い。いやあ、笑ったし楽しんだ。90分があっという間だった。二枚目の石川さんは身を投げ出して頑張っていて好感。松山尚子さんは初見だか力のあるコメディアンヌであった。役者の質も粒ぞろいだね。美術もチープ感はあるが実は相当凝っていた。
2011年9月23日 駅前劇場
作・田村孝裕 演出・上村聡史
出演 金内喜久夫、中村彰男、高橋克明、浅野雅博、木津誠之、亀田佳明
倉野章子、金沢映子、山崎美貴、片渕忍、上田桃子、吉野実紗

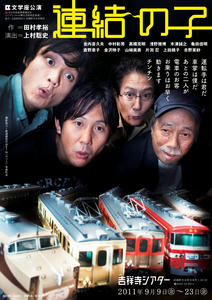
「田村作品/文学座だからこそ求めたい水準は、もっと何もない芝居」
美術、照明、衣装、もちろん演技は大変うまくて安心してみていられる。日本の演劇の最高峰である。しかし、この演出はどうだろう。若い上村さんの演出はスピード感を保つために無理して急いでいるところはないだろうか?特に転換などでその意識がものすごく感じられた。役者さんの演技がそのスピード感の中でも自然で、テンポやリズムを意識している事を感じないだけに、少し残念。
田村作品だけに高い水準にあるのだけれど、ここでも本当に鉄道マニアであることが必要だったのかが分からない。そこに作者の技巧を感じてしまうのだ。まあ、こういう高いレベルの芝居だからこその戯れ言ではあるが…。中村さんが年を取ったなあと思った。金内さんはドンキホーテのときと同じく最高に笑える。亀田さんは、また違った味わいで面白い。倉野さんは可愛い。しかし、本当の悪人が誰もでてこない。特に隣人にもう少し悪意のある人がいてもいいのではとも思った。
2011年9月20日@吉祥寺シアター
出演 金内喜久夫、中村彰男、高橋克明、浅野雅博、木津誠之、亀田佳明
倉野章子、金沢映子、山崎美貴、片渕忍、上田桃子、吉野実紗
「田村作品/文学座だからこそ求めたい水準は、もっと何もない芝居」
美術、照明、衣装、もちろん演技は大変うまくて安心してみていられる。日本の演劇の最高峰である。しかし、この演出はどうだろう。若い上村さんの演出はスピード感を保つために無理して急いでいるところはないだろうか?特に転換などでその意識がものすごく感じられた。役者さんの演技がそのスピード感の中でも自然で、テンポやリズムを意識している事を感じないだけに、少し残念。
田村作品だけに高い水準にあるのだけれど、ここでも本当に鉄道マニアであることが必要だったのかが分からない。そこに作者の技巧を感じてしまうのだ。まあ、こういう高いレベルの芝居だからこその戯れ言ではあるが…。中村さんが年を取ったなあと思った。金内さんはドンキホーテのときと同じく最高に笑える。亀田さんは、また違った味わいで面白い。倉野さんは可愛い。しかし、本当の悪人が誰もでてこない。特に隣人にもう少し悪意のある人がいてもいいのではとも思った。
2011年9月20日@吉祥寺シアター
ボローニャ歌劇場は来日公演の度に魅力的な演目を提供してくれる。そして、歌手もなかなか通好み。ミラノスカラ座よりも時にイタリア的な頂点を極める最高峰のオペラハウスだ。2011年は3演目!チケットも確保済み!

ビゼー作曲「カルメン」
「カルメンのいないカルメン」
何回もみた「カルメン」だが、メトロポリタンオペラとの来日はキャンセルしたカウフマンが歌うのかがポイントだったのだがやはりキャンセル。2011年はメトロポリタンオペラ、バイエルン、ボローニャと3大オペラハウスの来日でメインを唄う予定だったカウフマンイヤーになるはずだった。それが…。原発事故で吹っ飛んだのだ。さらに、美術が面白そうで楽しみだ。

「カルメンのいないカルメン」結局主要4役のうち、カルメン以外はキャストチェンジ。ある人が言っていたが、ボローニャ歌劇場は欧米の一流の次に属する2流の歌劇場。しかし、フジテレビが提示するチケット価格は超一流劇場並。それでも、私たちがお金を払うのは魅力的なスター歌手を呼ぶと宣伝するからだ。歌劇場に対してよりも歌手に対してお金を払う。それが、キャストチェンジとは…。ネット上では、原発事故の後でも来てくれているんだから感謝しろという意見が多いのですが、ボランティアで彼らは来ているのでしょうか?違います。主催者が相応のギャラを払ってビジネスとして来日しているのです。もはや日本のオペラシーンにおいては文化交流の側面が多いわけでもありません。ビジネスです。ですから5万円以上のチケット代を払って観に行っている以上、それ相応のことを求めるのは当たり前です。今回は、主催者は歌劇場よりも、各オペラの主演テノールをメインにして売ってきました。それが全員キャンセルです(リチートラの悲劇もありますが)。当日は招待券が山のようにでていることも知ってましたし、ネット上をちょっと検索するだけで、招待で行って来たという書き込みが多く、そのような人にとっては、来てくれただけでありがたいでしょう。僕も招待で見たのなら、少なくともありがたいと思います。でも僕は正規の価格を払ってますので言わせて頂きたい。このオペラ公演には憤慨しました。これはカルメンではありません。
マルセロアルバレス(ドンホセ)ヴァレンティーナコッツラディティ(ミカエラ)カイルケテルセン(エスカミーリョ)スルグラーゼ(カルメン)という布陣となった。スルグラーゼは、強音を出せる音域がとても狭い。艶やかな声は出せるのだが、強音になるととたんに弱くなる。自分の出せる能力も分かっているから、フレーズの一部だけが強音だったり、何かね穴ぼこだらけの歌手です。作り上げるカルメン像は面白いので女優としては合格なのだが、歌手としては2流である。カルメン歌いでもない。この人こそ、ミカエラでもやればいいのにと思った。魅力的なカルメンの楽曲がすべてつまらなかったし、終幕のドラマは顔では怒った顔をしているが、声が怒ってないのでなんかね。
リリアスバンチェスでの悪巧みや3幕のカルタのシーンでも5人で唄っていると、フラスキータの方が声が出ていたりするわけで、もう白けることこの上ないのです。
歌がダメだから、懸命に演技でカバーしようとする。だから大げさな演技になっていく。ああ、これじゃカルメンじゃない。彼女自壊というわけです。ルックス100点、歌30点というカルメンで、このカルメンには最後までカルメンは出てきませんでした。このカルメンをいいという人、知らなさすぎます。
ただ、スクルラーゼをちょっとだけ擁護するとすると、カルメンというのは本当に難しいオペラだし、カルメンは難しい役柄だということです。例えば、メトロポリタンオペラがヨハンナマイヤーをカルメンにして日本に持って来た。ドイツオペラの最高峰のスターではありますが、ラテンの血を感じさせるカルメンではなかった。ゲルギレフがマリンスキー歌劇場の来日公演で取り上げた。しかし、全員が怒ってる?わけではないけれど、声を出しているだけのカルメンで、これもカルメンとしては魅力がないなあと思った次第。日本では1980年代にロイヤルオペラの来日で、バルツアとカレーラスで上演があった。このカルメンは素晴らしかった。2回見たけれど圧倒的。バルツアはその後、藤原歌劇団でカルメンを唄ったんだけど、もうダメだった。難しいんだなあと思った。このロイヤルオペラの公演以降で、日本でこれは!と思えるカルメンを聴けたのは、2004年に藤原歌劇団がオランジュ音楽祭と共同制作したカルメンで、この時はチョンミンフン指揮、フランス国立フィルハーモニー管弦楽団がピットに入るという豪華版。歌手もドンホセがスコーラだった。カルメンはセメンチュクという人だったけれども中々良かった事を覚えている。この時も実はキャストが3人入れ替わったんだけれど、チョンがきちんと連れて来たんだろうと思う。
と、記憶を辿っていくと、カルメンを欧米のそこそこいいオペラハウスが来日公演に持ってくる事はないのです。危険すぎるんでしょうね。さて、このボローニャ版、カルメンのいない「カルメン」にも歌手はいました。ミカエラのコッツラディティとドンホセのアルバレスは、細かい事は目をつむりますが、声が出ているしやりたいことも分かります。ただ、アルバレスは役作りが雑。そして、二人ともカルメンが美しくエロ光線を出しているのに対して、ルックスがいま3くらいなんですよ。
エスカミーリョのカイルケルセンは、ボクサー役で裸もみせなくちゃいけないので、ルックスも合格だし、演技もいいし、歌も声がいいので、いちばんバランスが取れていたと思う。しかし、歌が歌を歌うだけで、歌で演技をしている感じがしないんだよな。何かね、いい声を聞かせてもらったという感じで。そう、演技と歌がバラバラ。ちょっと悪な演技と、超優等生な歌って感じ。
演出は、1990年代のキューバが舞台となり、タバコ工場は葉巻工場に、フラメンコはサルサに、闘牛士はボクサーに、山賊はボートピープルで脱出する人にと読み替えての上演です。でも、それがただ読み替えただけで、何も現代とつながってこない。何をやりたいのか全く伝わってきません。当日会場に来ていた、新聞で音楽評も書かれる僕の恩師とちょこっと話したんですけど、同意見。
オケは酷かった。歌手とあってない。オケ自体も統率が取れず、ぐらぐら。マリオッティなる指揮者は遅めのテンポで通すのですが、そのテンポでは勢いでごまかす事ができません。もっと緻密なアンサンブルを聞かせてくれないと、もっと艶やかなフレージングで音を紡いでくれないとと思います。先ずはスコアの縦の音がきちんと揃うように指揮して下さいと申し上げたい。
私の結論はカルメンを聴く限り、イタリア政府の文化予算カットの流れで、ボローニャは今までいたような一流の指揮者を置く余裕もなくなり、新演出も作れなく、(このカルメンは、ラトビア・オペラの演出の舞台装置を借りての上演。)ただいま急降下中ということだと思います。がっかし。
2011年9月13日 東京文化会館
ヴェルディ作曲「エルナーニ」
来日オペラハウスの初演になる。僕も生で見るのは初めての作品。

「歌声は満喫。1960年代のような演出に唖然」
アロニカ(エルナーニ)フロンターリ(ドンカルロ=スペイン国王)。フルラネットら男性陣はイタリアオペラを聴く、声の喜びを与えてくれた。しかし、前から思うのだが日本ではギリシア出身であることなどから第二のマリアカラスなどと持ち上げるテオドッツシュウが、必要以上に多いビブラート、得意不得意の音域があることなど、やはり超一流の歌手とは思えない歌唱でちょっとがっかり。別に彼女は不調というほどではないのではないか?彼女は10年ほど前のフェニーチェ歌劇場来日時の歌唱から4回ほど聞いているがいつもこんなものだから。
オケは相変わらずだがマリオッティよりは数段良かった。ちゃんとオケがコントロールされ、きちんと合って演奏しているからという決して高いレベルでの評価ではないが。今宵の指揮はパルンボ。演奏直後に会場を離れたが、今宵はアンコール「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗っ て」が唄われたとのこと。
2011年9月25日 東京文化会館
ベルリーニ作曲「清教徒」
藤原歌劇団などで見た事はあるものの、ピンと来なかった作品。最上の上演で自分の中にうまくインプットされるかな?

「ランカトーレ唯一の欠点に泣く」
ピューリタン革命時の悲劇を描くベッリーニのオペラ。「カルメン」に比べると天国と地獄ほどの差のある演奏でちょっと安心した。デジレランカトーレはヒロインのエルヴィーラ(輿入れした先よりも若い男がいいと走る)は狂乱の場を初めとして見事な歌唱。ただし、この人、破裂音の低い声になると発声がめちゃくちゃ変わって、そこだけアヒルのような音になってしまう。何とかそこを克服して欲しい。何かいけない地雷を踏んでしまったように興ざめしてしまうポイントだ。ジョルジョ(ニコラウリヴィエーリ)は2幕の最後の二重唱できちんと聞かせ、シラクーザは超名演とは言えないが、安定感のある声を聞かせてくれた。シラクーザの声はしかし特徴がありすぎで、何となくロッシーニにやっぱりあうなと思った。何か声が変なのだ。というより面白い声なのだ。
清教徒、エルナーニのどちらにも言えるのだが、演出も美術もあまりにも普通過ぎ。どちらもそこそこ奇麗なのだが、それだけ。そして、合唱もソロも、何か立ち止まって客席目線で浪々と唄うだけ。
イタリアオペラで声を楽しむということに徹すればいいし、それでほぼ満足なのだが、歌劇の劇の部分に関しては、1960年代のそれと変わっていないのではないかと思う。マリオッティの指揮はやはり傷だらけで、オケが合わないのが絶対的にダメで、聞かせようとくっきりずっしりやればやるほど、歌手が濃い表現しすぎなくらいの歌唱をしているので、しつこくもなるのだ。もうすこし、あっさりした方がいい。もしも、歌を聴かせる事で勝負したいと思うのならと思った。
2011年9月24日 東京文化会館
ビゼー作曲「カルメン」
「カルメンのいないカルメン」
何回もみた「カルメン」だが、メトロポリタンオペラとの来日はキャンセルしたカウフマンが歌うのかがポイントだったのだがやはりキャンセル。2011年はメトロポリタンオペラ、バイエルン、ボローニャと3大オペラハウスの来日でメインを唄う予定だったカウフマンイヤーになるはずだった。それが…。原発事故で吹っ飛んだのだ。さらに、美術が面白そうで楽しみだ。
「カルメンのいないカルメン」結局主要4役のうち、カルメン以外はキャストチェンジ。ある人が言っていたが、ボローニャ歌劇場は欧米の一流の次に属する2流の歌劇場。しかし、フジテレビが提示するチケット価格は超一流劇場並。それでも、私たちがお金を払うのは魅力的なスター歌手を呼ぶと宣伝するからだ。歌劇場に対してよりも歌手に対してお金を払う。それが、キャストチェンジとは…。ネット上では、原発事故の後でも来てくれているんだから感謝しろという意見が多いのですが、ボランティアで彼らは来ているのでしょうか?違います。主催者が相応のギャラを払ってビジネスとして来日しているのです。もはや日本のオペラシーンにおいては文化交流の側面が多いわけでもありません。ビジネスです。ですから5万円以上のチケット代を払って観に行っている以上、それ相応のことを求めるのは当たり前です。今回は、主催者は歌劇場よりも、各オペラの主演テノールをメインにして売ってきました。それが全員キャンセルです(リチートラの悲劇もありますが)。当日は招待券が山のようにでていることも知ってましたし、ネット上をちょっと検索するだけで、招待で行って来たという書き込みが多く、そのような人にとっては、来てくれただけでありがたいでしょう。僕も招待で見たのなら、少なくともありがたいと思います。でも僕は正規の価格を払ってますので言わせて頂きたい。このオペラ公演には憤慨しました。これはカルメンではありません。
マルセロアルバレス(ドンホセ)ヴァレンティーナコッツラディティ(ミカエラ)カイルケテルセン(エスカミーリョ)スルグラーゼ(カルメン)という布陣となった。スルグラーゼは、強音を出せる音域がとても狭い。艶やかな声は出せるのだが、強音になるととたんに弱くなる。自分の出せる能力も分かっているから、フレーズの一部だけが強音だったり、何かね穴ぼこだらけの歌手です。作り上げるカルメン像は面白いので女優としては合格なのだが、歌手としては2流である。カルメン歌いでもない。この人こそ、ミカエラでもやればいいのにと思った。魅力的なカルメンの楽曲がすべてつまらなかったし、終幕のドラマは顔では怒った顔をしているが、声が怒ってないのでなんかね。
リリアスバンチェスでの悪巧みや3幕のカルタのシーンでも5人で唄っていると、フラスキータの方が声が出ていたりするわけで、もう白けることこの上ないのです。
歌がダメだから、懸命に演技でカバーしようとする。だから大げさな演技になっていく。ああ、これじゃカルメンじゃない。彼女自壊というわけです。ルックス100点、歌30点というカルメンで、このカルメンには最後までカルメンは出てきませんでした。このカルメンをいいという人、知らなさすぎます。
ただ、スクルラーゼをちょっとだけ擁護するとすると、カルメンというのは本当に難しいオペラだし、カルメンは難しい役柄だということです。例えば、メトロポリタンオペラがヨハンナマイヤーをカルメンにして日本に持って来た。ドイツオペラの最高峰のスターではありますが、ラテンの血を感じさせるカルメンではなかった。ゲルギレフがマリンスキー歌劇場の来日公演で取り上げた。しかし、全員が怒ってる?わけではないけれど、声を出しているだけのカルメンで、これもカルメンとしては魅力がないなあと思った次第。日本では1980年代にロイヤルオペラの来日で、バルツアとカレーラスで上演があった。このカルメンは素晴らしかった。2回見たけれど圧倒的。バルツアはその後、藤原歌劇団でカルメンを唄ったんだけど、もうダメだった。難しいんだなあと思った。このロイヤルオペラの公演以降で、日本でこれは!と思えるカルメンを聴けたのは、2004年に藤原歌劇団がオランジュ音楽祭と共同制作したカルメンで、この時はチョンミンフン指揮、フランス国立フィルハーモニー管弦楽団がピットに入るという豪華版。歌手もドンホセがスコーラだった。カルメンはセメンチュクという人だったけれども中々良かった事を覚えている。この時も実はキャストが3人入れ替わったんだけれど、チョンがきちんと連れて来たんだろうと思う。
と、記憶を辿っていくと、カルメンを欧米のそこそこいいオペラハウスが来日公演に持ってくる事はないのです。危険すぎるんでしょうね。さて、このボローニャ版、カルメンのいない「カルメン」にも歌手はいました。ミカエラのコッツラディティとドンホセのアルバレスは、細かい事は目をつむりますが、声が出ているしやりたいことも分かります。ただ、アルバレスは役作りが雑。そして、二人ともカルメンが美しくエロ光線を出しているのに対して、ルックスがいま3くらいなんですよ。
エスカミーリョのカイルケルセンは、ボクサー役で裸もみせなくちゃいけないので、ルックスも合格だし、演技もいいし、歌も声がいいので、いちばんバランスが取れていたと思う。しかし、歌が歌を歌うだけで、歌で演技をしている感じがしないんだよな。何かね、いい声を聞かせてもらったという感じで。そう、演技と歌がバラバラ。ちょっと悪な演技と、超優等生な歌って感じ。
演出は、1990年代のキューバが舞台となり、タバコ工場は葉巻工場に、フラメンコはサルサに、闘牛士はボクサーに、山賊はボートピープルで脱出する人にと読み替えての上演です。でも、それがただ読み替えただけで、何も現代とつながってこない。何をやりたいのか全く伝わってきません。当日会場に来ていた、新聞で音楽評も書かれる僕の恩師とちょこっと話したんですけど、同意見。
オケは酷かった。歌手とあってない。オケ自体も統率が取れず、ぐらぐら。マリオッティなる指揮者は遅めのテンポで通すのですが、そのテンポでは勢いでごまかす事ができません。もっと緻密なアンサンブルを聞かせてくれないと、もっと艶やかなフレージングで音を紡いでくれないとと思います。先ずはスコアの縦の音がきちんと揃うように指揮して下さいと申し上げたい。
私の結論はカルメンを聴く限り、イタリア政府の文化予算カットの流れで、ボローニャは今までいたような一流の指揮者を置く余裕もなくなり、新演出も作れなく、(このカルメンは、ラトビア・オペラの演出の舞台装置を借りての上演。)ただいま急降下中ということだと思います。がっかし。
2011年9月13日 東京文化会館
ヴェルディ作曲「エルナーニ」
来日オペラハウスの初演になる。僕も生で見るのは初めての作品。
「歌声は満喫。1960年代のような演出に唖然」
アロニカ(エルナーニ)フロンターリ(ドンカルロ=スペイン国王)。フルラネットら男性陣はイタリアオペラを聴く、声の喜びを与えてくれた。しかし、前から思うのだが日本ではギリシア出身であることなどから第二のマリアカラスなどと持ち上げるテオドッツシュウが、必要以上に多いビブラート、得意不得意の音域があることなど、やはり超一流の歌手とは思えない歌唱でちょっとがっかり。別に彼女は不調というほどではないのではないか?彼女は10年ほど前のフェニーチェ歌劇場来日時の歌唱から4回ほど聞いているがいつもこんなものだから。
オケは相変わらずだがマリオッティよりは数段良かった。ちゃんとオケがコントロールされ、きちんと合って演奏しているからという決して高いレベルでの評価ではないが。今宵の指揮はパルンボ。演奏直後に会場を離れたが、今宵はアンコール「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗っ て」が唄われたとのこと。
2011年9月25日 東京文化会館
ベルリーニ作曲「清教徒」
藤原歌劇団などで見た事はあるものの、ピンと来なかった作品。最上の上演で自分の中にうまくインプットされるかな?
「ランカトーレ唯一の欠点に泣く」
ピューリタン革命時の悲劇を描くベッリーニのオペラ。「カルメン」に比べると天国と地獄ほどの差のある演奏でちょっと安心した。デジレランカトーレはヒロインのエルヴィーラ(輿入れした先よりも若い男がいいと走る)は狂乱の場を初めとして見事な歌唱。ただし、この人、破裂音の低い声になると発声がめちゃくちゃ変わって、そこだけアヒルのような音になってしまう。何とかそこを克服して欲しい。何かいけない地雷を踏んでしまったように興ざめしてしまうポイントだ。ジョルジョ(ニコラウリヴィエーリ)は2幕の最後の二重唱できちんと聞かせ、シラクーザは超名演とは言えないが、安定感のある声を聞かせてくれた。シラクーザの声はしかし特徴がありすぎで、何となくロッシーニにやっぱりあうなと思った。何か声が変なのだ。というより面白い声なのだ。
清教徒、エルナーニのどちらにも言えるのだが、演出も美術もあまりにも普通過ぎ。どちらもそこそこ奇麗なのだが、それだけ。そして、合唱もソロも、何か立ち止まって客席目線で浪々と唄うだけ。
イタリアオペラで声を楽しむということに徹すればいいし、それでほぼ満足なのだが、歌劇の劇の部分に関しては、1960年代のそれと変わっていないのではないかと思う。マリオッティの指揮はやはり傷だらけで、オケが合わないのが絶対的にダメで、聞かせようとくっきりずっしりやればやるほど、歌手が濃い表現しすぎなくらいの歌唱をしているので、しつこくもなるのだ。もうすこし、あっさりした方がいい。もしも、歌を聴かせる事で勝負したいと思うのならと思った。
2011年9月24日 東京文化会館
ベルリオーズ/劇的交響曲〈ロミオとジュリエット〉作品17


指揮:シルヴァン・カンブルラン(読売日響常任指揮者)
メゾ・ソプラノ:カタリーナ・カルネウス(当初予定のベアトリス・ユリア=モンゾンから変更)
テノール:ジャン=ポール・フシェクール
バス:ローラン・ナウリ
合唱:新国立劇場合唱団 合唱指揮:三澤洋史
「読売日本交響楽団じゃなかった」
先ず僕は劇的交響曲「ロミオとジュリエット」という曲をほとんど知らない。生演奏を聴いたのは生まれて初めてだ。この作品、100分の大作で、ベルリオーズのアバンギャルドなところが随所に観られる作品で、この作曲家がこの時代に既に未来の音楽に手を伸ばしていた事が良くわかる。作品も標題音楽のように思っていたのだが、ドラマの本質に迫ろうとするもので、物語を順繰りに聞かせる作品とは全く違っていた。「ファウストの刧罰」のような大きな作品で、もっともっと内面に入り込んでいく作品だった。
それだけに、演奏がぼやけていると魅力は半減する。強い統率力でひとつの方向に向かっていく音楽が求められるのだ。今宵の読売日本交響楽団は目をつむっていたら、私は読響だ!とは決して言わなかったと思う。アメリカのオケのような機能性も、時おり地方のフランスのオケが魅せる個性もあった。特に第二部あたりから、音はどんどん研ぎすまされていき、鋭角な尖った音が聞こえて来たのには驚いた。
若干はいる不協和音的な音も、まるで20世紀の音楽を予感させるように響いた。
唯一残念だったのは、新国立劇場の合唱団の合唱がフランス語独特の日本語にはない発音で迫って来なかったところだ。フランス語は分からないが、フランス語に聞こえなかった。
2011年9月12日@サントリーホール 2階C5列とてもいい席で聞けた。
2011年9月12日@サントリーホール大ホール
指揮:シルヴァン・カンブルラン(読売日響常任指揮者)
メゾ・ソプラノ:カタリーナ・カルネウス(当初予定のベアトリス・ユリア=モンゾンから変更)
テノール:ジャン=ポール・フシェクール
バス:ローラン・ナウリ
合唱:新国立劇場合唱団 合唱指揮:三澤洋史
「読売日本交響楽団じゃなかった」
先ず僕は劇的交響曲「ロミオとジュリエット」という曲をほとんど知らない。生演奏を聴いたのは生まれて初めてだ。この作品、100分の大作で、ベルリオーズのアバンギャルドなところが随所に観られる作品で、この作曲家がこの時代に既に未来の音楽に手を伸ばしていた事が良くわかる。作品も標題音楽のように思っていたのだが、ドラマの本質に迫ろうとするもので、物語を順繰りに聞かせる作品とは全く違っていた。「ファウストの刧罰」のような大きな作品で、もっともっと内面に入り込んでいく作品だった。
それだけに、演奏がぼやけていると魅力は半減する。強い統率力でひとつの方向に向かっていく音楽が求められるのだ。今宵の読売日本交響楽団は目をつむっていたら、私は読響だ!とは決して言わなかったと思う。アメリカのオケのような機能性も、時おり地方のフランスのオケが魅せる個性もあった。特に第二部あたりから、音はどんどん研ぎすまされていき、鋭角な尖った音が聞こえて来たのには驚いた。
若干はいる不協和音的な音も、まるで20世紀の音楽を予感させるように響いた。
唯一残念だったのは、新国立劇場の合唱団の合唱がフランス語独特の日本語にはない発音で迫って来なかったところだ。フランス語は分からないが、フランス語に聞こえなかった。
2011年9月12日@サントリーホール 2階C5列とてもいい席で聞けた。
2011年9月12日@サントリーホール大ホール
チェリーブロッサムハイスクール メロス
脚本:荒川修寺 演出:柴田雄平 出演 柴田雄平 渡部ラム 野田政虎 荒川修寺 山咲広美 池上武蔵 もなみのりこ
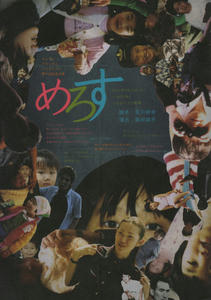

劇団のロゴが、ゴッドファーザーの字体と極似。ということで気になっていた劇団の初見。走れメロスだった。八百屋の素舞台、廻りに椅子、高度な照明、映像とリズムと音楽を使って90分の作品を肉体を酷使してつないでいく。一人が何十もの役をやりつつ、スピーディな展開。そう、惑星ピスタチオの手法に似すぎているのだ。それならば、もっとスケールのでかい。もっと巧い役者の、もっと肉体を酷使したそれを、もう20年以上前に観ている。
最初の10分で飽きてしまい、90分が長くてたまらなかった。ただし、役者は、渡部ラム、柴田雄平が良かった。真面目に肉体を使いユーモアが溢れていた。照明がムービングなんかも使っていて幾らの予算なんだろうと思うくらいに羨ましかった。
2011年9月11日 こまばアゴラ劇場
脚本:荒川修寺 演出:柴田雄平 出演 柴田雄平 渡部ラム 野田政虎 荒川修寺 山咲広美 池上武蔵 もなみのりこ
劇団のロゴが、ゴッドファーザーの字体と極似。ということで気になっていた劇団の初見。走れメロスだった。八百屋の素舞台、廻りに椅子、高度な照明、映像とリズムと音楽を使って90分の作品を肉体を酷使してつないでいく。一人が何十もの役をやりつつ、スピーディな展開。そう、惑星ピスタチオの手法に似すぎているのだ。それならば、もっとスケールのでかい。もっと巧い役者の、もっと肉体を酷使したそれを、もう20年以上前に観ている。
最初の10分で飽きてしまい、90分が長くてたまらなかった。ただし、役者は、渡部ラム、柴田雄平が良かった。真面目に肉体を使いユーモアが溢れていた。照明がムービングなんかも使っていて幾らの予算なんだろうと思うくらいに羨ましかった。
2011年9月11日 こまばアゴラ劇場
ヘルベルトブロムシュテット/NHK交響楽団定期演奏会 2011年9月

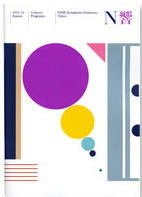
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ドヴォルザーク/交響曲 第9番 ホ短調 作品95「新世界から」
指揮: ヘルベルト・ブロムシュテット
ヴァイオリン: 竹澤恭子

2011/12のシーズンを期待させる最上の演奏。スコアをもう一度見直したからこそ聞こえてくる新しい新世界。
素晴らしいホールが多くある東京においてNHKホールは決して演奏するのに有利なホールではない。25年前にサントリーホールができた時に、同じNHK交響楽団がまったく違った音で聞こえるのに愕然としたほどだ。今でもNHK交響楽団の定期会員はサントリーホールが人気で、年間の定期会員の全席が完売になることでもその理由が分かる。今宵、私はこの交響楽団の音をきいて、愕然とした。かつてこのホールでベルリンフィルもパリ管弦楽団もウィーンフィルも、こんな素晴らしい音をこのホールで聞かせただろうか?もちろんホームグラウンドであるからホールを知り尽くしている事はあるだろう。しかし、例えば、今や80代となり巨匠となったブロムシュテットの十八番とはいえ、シベリウスの弦楽合奏が、3楽章のあの大地をゆらるようなリズムをきくと、私は生きながら天界にいるのではないかと思うほどの美しさを感じるのだ。管楽器も打楽器も、、、、35年も聞いているオーケストラだから、ほとんどのメンバーは入れ替わっているけれども。本当に素晴らしいオーケストラになった。
竹澤恭子は急遽の代役であるが、彼女にとってもシベリウスの協奏曲は十八番。私は、20年ほど前に、アンネゾフィームターとプレヴィンの録音を聞いた時に、チョンミュンファの録音を高校の時に聞いた時に魅せられたこの協奏曲だが、今宵の竹澤の演奏は自分の個性をむき出しにしてオーケストラと競奏するのではなく、音楽の中にお互いが無我の境地で陥って演奏する狂想のように思えて仕方なかった。
後半のもはや曲には何の興味ももてない新世界交響曲だが、演奏が良かったのは当たり前だが、ブロムシュテットは垢のつくほど演奏したオーケストラのメンバーにスコアにもう一度真摯に当たるように求めたのか。いつもと音色が違う。いや新世界ってこんな感じだよね?という演奏が全くない。国民学派の民謡のメロディ頼りの演奏ではなく、きっちしとした交響楽の構築美を聞かせてくれた。面白かった。
2011年9月10日 午後6時 NHKホール
Cプロ
ラフマニノフ/ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
チャイコフスキー/交響曲 第5番 ホ短調 作品64
指揮: ヘルベルト・ブロムシュテット
カラヤン/ベルリンフィルの最盛期を思わせる鉄壁な演奏。
驚いた。こんなすごい演奏が35年以上聞いて来たNHK交響楽団の、それもNHKホールでの定期演奏会で聞けるとは夢にも思っていなかった。
プログラムの前半、ラフマニノフのピアノ協奏曲は41才のノルウェー生まれのレイフ・オヴェ・アンスネスを招いての演奏。この演奏は高校のころだったか、ホロヴィッツのライブ盤が発売されて話題になった。アンスネスの演奏はそれとは違うが音の粒をひとつひとつおざなりにしない彼の演奏はホロヴィッツの音作りと共通するところがある。ただ、アンスネスは抜群の技術をもちながらも、それを華麗で豊麗な音で埋め尽くして圧倒するような演奏にはしないことだ。知性と品性のある演奏なのだ。だからこそ、カデンツアで超絶技巧を聞かせるときの聞き手の興奮は頂点に達する。この協奏曲は何回か生演奏をきいてきたけれど、NHK交響楽団の見事なアンサンブルもあって、この曲のライブ演奏ではベストのものとして長く記憶に残るだろう。
正直、前半で疲れきってしまう程驚いた。しかし、当夜のメインディッシュは後半にあったのだ。
チャイコフスキーの5番交響曲。第一楽章が始まった時に、これとてつもない演奏になるかもしれないぞと思ったのだが、前の週のブロムシュテットの新世界の時と同じく、先ずは世界の超一流のオケにひけを取らない見事な弦楽アンサンブルが心を鷲掴みにしていく。そして、奇跡は第二楽章に決定的なものとなった。そのアンサンブルに、ホルンがテーマを吹いたとき、その格調の高さとメランコリックに流れない知性のある演奏が、ロシアのオケでは演奏できない、かつてのカラヤン/ベルリンフィルが栄華を極めた時代の演奏のそれに匹敵する完璧さで迫って来たのだ。ホルンはオーボエなどと絡みながら他の楽器に主題を譲っていくわけだが、それぞれが見事としかいいようのない音楽を聴く楽しみを再認識させてくれる名演だ。
中間部でのクラリネットと弦の呼応の見事さ。ブロムシュテットは北欧生まれのアメリカ人だ。カラヤンの演奏に比べるともう少し淡白ですきっと聞かせる。真ん中で弦のピチカートが入り、弦が再びオーボエなんかと唄うところがあるけれども、そのピチカートのくっくりさと、弦の唄わせ方がカラヤンよりも品がいいんだよなあ。特にここの第一バイオリン。こんな音をベルリンフィル、シカゴ交響楽団、ウィーンフィルといった世界のトップオブトップ以外から聞いた事がなかった。それが、あなた、NHKホール(最悪音響空間)のNHK交響楽団から聞けたんで驚いたわけですよ。
3楽章は、乱れとまでは言わないが、二楽章の奇跡的な演奏に比べるとやや普通の演奏だったけれども、4楽章はまたまた奇跡がおきた。終幕の大合奏のすごかった事。ブロムシュテットはやや遅めのテンポで始めてたっぷり唄わせて、終幕にむけて通常のテンポくらいまで微妙に変えていく。いやあ、80代なのに、格調は高いのに若い。枯れていない。そこがいいところですなあ。ベームは晩年、チャイコフスキーを録音したけれど、もう枯れていて何かね、艶やかな魅力がなかったからな。
この演奏はオーケストラ音楽の極みへ聴衆を連れて行ってくれました。まさに見事。見事。NHK交響楽団、いま世界でももっとも旬な演奏団体になったようです。
この文章を書く時にカラヤン/ウィーンフィルのCDを聞きながら書いているのだが、正直、NHK交響楽団の演奏の方がいいなあ。
2011年9月16日 NHKホール
Bプロ
シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」
ブルックナー/交響曲 第7番 ホ長調(ノヴァーク版)
台風のため未完成は聞けなかった。客席は2割ほどの入りしかなく、どうもいつものサントリーホールよりも残響が良かった感じ。それが、ブルックナーの演奏にぴったり。第二楽章はワーグナーの死に捧げたとも言われる楽章であるが、そこでのホルンの見事なこと。おったまげ。これがN響の弦楽合奏かと驚いた次第。2楽章で火がついた演奏は最終楽章まで衰える事なく続く。ブロムシュテットは、感情でぐいぐいおしていくのではなく、あくまでも冷静にテンポも強弱もコントロールしていたように思う。なんだろう。僕は、オイゲンヨッフムがコンセルトヘボウやバンベルグ響とやったもの、ハイティンクなどの名指揮者が演奏したウィーンフィルとの演奏がブルックナーの名演奏として心に残っているのだが、少なくともそれと並ぶ名演だったと思う。とにかくオケから聞こえてくる音が日本のオケとは思えないのだ。すごい。
指揮: ヘルベルト・ブロムシュテット
2011年9月21日 サントリーホール
シベリウス/ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47
ドヴォルザーク/交響曲 第9番 ホ短調 作品95「新世界から」
指揮: ヘルベルト・ブロムシュテット
ヴァイオリン: 竹澤恭子
2011/12のシーズンを期待させる最上の演奏。スコアをもう一度見直したからこそ聞こえてくる新しい新世界。
素晴らしいホールが多くある東京においてNHKホールは決して演奏するのに有利なホールではない。25年前にサントリーホールができた時に、同じNHK交響楽団がまったく違った音で聞こえるのに愕然としたほどだ。今でもNHK交響楽団の定期会員はサントリーホールが人気で、年間の定期会員の全席が完売になることでもその理由が分かる。今宵、私はこの交響楽団の音をきいて、愕然とした。かつてこのホールでベルリンフィルもパリ管弦楽団もウィーンフィルも、こんな素晴らしい音をこのホールで聞かせただろうか?もちろんホームグラウンドであるからホールを知り尽くしている事はあるだろう。しかし、例えば、今や80代となり巨匠となったブロムシュテットの十八番とはいえ、シベリウスの弦楽合奏が、3楽章のあの大地をゆらるようなリズムをきくと、私は生きながら天界にいるのではないかと思うほどの美しさを感じるのだ。管楽器も打楽器も、、、、35年も聞いているオーケストラだから、ほとんどのメンバーは入れ替わっているけれども。本当に素晴らしいオーケストラになった。
竹澤恭子は急遽の代役であるが、彼女にとってもシベリウスの協奏曲は十八番。私は、20年ほど前に、アンネゾフィームターとプレヴィンの録音を聞いた時に、チョンミュンファの録音を高校の時に聞いた時に魅せられたこの協奏曲だが、今宵の竹澤の演奏は自分の個性をむき出しにしてオーケストラと競奏するのではなく、音楽の中にお互いが無我の境地で陥って演奏する狂想のように思えて仕方なかった。
後半のもはや曲には何の興味ももてない新世界交響曲だが、演奏が良かったのは当たり前だが、ブロムシュテットは垢のつくほど演奏したオーケストラのメンバーにスコアにもう一度真摯に当たるように求めたのか。いつもと音色が違う。いや新世界ってこんな感じだよね?という演奏が全くない。国民学派の民謡のメロディ頼りの演奏ではなく、きっちしとした交響楽の構築美を聞かせてくれた。面白かった。
2011年9月10日 午後6時 NHKホール
Cプロ
ラフマニノフ/ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 作品30
チャイコフスキー/交響曲 第5番 ホ短調 作品64
指揮: ヘルベルト・ブロムシュテット
カラヤン/ベルリンフィルの最盛期を思わせる鉄壁な演奏。
驚いた。こんなすごい演奏が35年以上聞いて来たNHK交響楽団の、それもNHKホールでの定期演奏会で聞けるとは夢にも思っていなかった。
プログラムの前半、ラフマニノフのピアノ協奏曲は41才のノルウェー生まれのレイフ・オヴェ・アンスネスを招いての演奏。この演奏は高校のころだったか、ホロヴィッツのライブ盤が発売されて話題になった。アンスネスの演奏はそれとは違うが音の粒をひとつひとつおざなりにしない彼の演奏はホロヴィッツの音作りと共通するところがある。ただ、アンスネスは抜群の技術をもちながらも、それを華麗で豊麗な音で埋め尽くして圧倒するような演奏にはしないことだ。知性と品性のある演奏なのだ。だからこそ、カデンツアで超絶技巧を聞かせるときの聞き手の興奮は頂点に達する。この協奏曲は何回か生演奏をきいてきたけれど、NHK交響楽団の見事なアンサンブルもあって、この曲のライブ演奏ではベストのものとして長く記憶に残るだろう。
正直、前半で疲れきってしまう程驚いた。しかし、当夜のメインディッシュは後半にあったのだ。
チャイコフスキーの5番交響曲。第一楽章が始まった時に、これとてつもない演奏になるかもしれないぞと思ったのだが、前の週のブロムシュテットの新世界の時と同じく、先ずは世界の超一流のオケにひけを取らない見事な弦楽アンサンブルが心を鷲掴みにしていく。そして、奇跡は第二楽章に決定的なものとなった。そのアンサンブルに、ホルンがテーマを吹いたとき、その格調の高さとメランコリックに流れない知性のある演奏が、ロシアのオケでは演奏できない、かつてのカラヤン/ベルリンフィルが栄華を極めた時代の演奏のそれに匹敵する完璧さで迫って来たのだ。ホルンはオーボエなどと絡みながら他の楽器に主題を譲っていくわけだが、それぞれが見事としかいいようのない音楽を聴く楽しみを再認識させてくれる名演だ。
中間部でのクラリネットと弦の呼応の見事さ。ブロムシュテットは北欧生まれのアメリカ人だ。カラヤンの演奏に比べるともう少し淡白ですきっと聞かせる。真ん中で弦のピチカートが入り、弦が再びオーボエなんかと唄うところがあるけれども、そのピチカートのくっくりさと、弦の唄わせ方がカラヤンよりも品がいいんだよなあ。特にここの第一バイオリン。こんな音をベルリンフィル、シカゴ交響楽団、ウィーンフィルといった世界のトップオブトップ以外から聞いた事がなかった。それが、あなた、NHKホール(最悪音響空間)のNHK交響楽団から聞けたんで驚いたわけですよ。
3楽章は、乱れとまでは言わないが、二楽章の奇跡的な演奏に比べるとやや普通の演奏だったけれども、4楽章はまたまた奇跡がおきた。終幕の大合奏のすごかった事。ブロムシュテットはやや遅めのテンポで始めてたっぷり唄わせて、終幕にむけて通常のテンポくらいまで微妙に変えていく。いやあ、80代なのに、格調は高いのに若い。枯れていない。そこがいいところですなあ。ベームは晩年、チャイコフスキーを録音したけれど、もう枯れていて何かね、艶やかな魅力がなかったからな。
この演奏はオーケストラ音楽の極みへ聴衆を連れて行ってくれました。まさに見事。見事。NHK交響楽団、いま世界でももっとも旬な演奏団体になったようです。
この文章を書く時にカラヤン/ウィーンフィルのCDを聞きながら書いているのだが、正直、NHK交響楽団の演奏の方がいいなあ。
2011年9月16日 NHKホール
Bプロ
シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」
ブルックナー/交響曲 第7番 ホ長調(ノヴァーク版)
台風のため未完成は聞けなかった。客席は2割ほどの入りしかなく、どうもいつものサントリーホールよりも残響が良かった感じ。それが、ブルックナーの演奏にぴったり。第二楽章はワーグナーの死に捧げたとも言われる楽章であるが、そこでのホルンの見事なこと。おったまげ。これがN響の弦楽合奏かと驚いた次第。2楽章で火がついた演奏は最終楽章まで衰える事なく続く。ブロムシュテットは、感情でぐいぐいおしていくのではなく、あくまでも冷静にテンポも強弱もコントロールしていたように思う。なんだろう。僕は、オイゲンヨッフムがコンセルトヘボウやバンベルグ響とやったもの、ハイティンクなどの名指揮者が演奏したウィーンフィルとの演奏がブルックナーの名演奏として心に残っているのだが、少なくともそれと並ぶ名演だったと思う。とにかくオケから聞こえてくる音が日本のオケとは思えないのだ。すごい。
指揮: ヘルベルト・ブロムシュテット
2011年9月21日 サントリーホール
TRASHMASTERS『背水の孤島』
作演出・中津留章仁 出演 カゴシマジロー ひわだこういち 吹上タツヒロ 阿部薫 林田麻里 木下智恵 大友陸 ほか

「重量オーバー」
前に観たのは数年前。今回も分け合ってみせてもらった。だからこそできるだけポジティブに書きたいなとも思う。作者の力量は分かる。既に商業ベースに乗っている作家だ。
震災後のメディアの現状を「説明台詞」でつなぐ「プロローグ」に、震災後のバラックのようなところで過ごす家族の物語「蠅」と、数年後の東京でのテロ事件にまつわる話「背水の孤島」の3部構成。と内容をまとめてしまうと乱暴すぎるか。
多少甘ったるいなあと思う台詞はあるけれども、第一部の「蠅」は77分で飽きずにみることができた。林田麻里がうまい。しかし、プロローグや第二部の「背水の孤島」は正直観るのが辛い。役者がうまいので聞けるが「説明台詞」が多すぎ、政治経済の情報や考え方もちょっと無理があるところもあり、如何なものかと思うところもアリ辛い。何で財務大臣がこんな都会のベンチャー企業の社長の小さなオフィスみたいなところにいるのか?と思っただけで…。さらに、上演時間3時間20分越えて疲労困憊。金払っていってたら正直、途中で帰ったと思う。役者は巧い。すごい。
演出もいいです。ただ、本が長い。長すぎる事が全ての…
2011年9月9日@笹塚ファクトリー
作演出・中津留章仁 出演 カゴシマジロー ひわだこういち 吹上タツヒロ 阿部薫 林田麻里 木下智恵 大友陸 ほか
「重量オーバー」
前に観たのは数年前。今回も分け合ってみせてもらった。だからこそできるだけポジティブに書きたいなとも思う。作者の力量は分かる。既に商業ベースに乗っている作家だ。
震災後のメディアの現状を「説明台詞」でつなぐ「プロローグ」に、震災後のバラックのようなところで過ごす家族の物語「蠅」と、数年後の東京でのテロ事件にまつわる話「背水の孤島」の3部構成。と内容をまとめてしまうと乱暴すぎるか。
多少甘ったるいなあと思う台詞はあるけれども、第一部の「蠅」は77分で飽きずにみることができた。林田麻里がうまい。しかし、プロローグや第二部の「背水の孤島」は正直観るのが辛い。役者がうまいので聞けるが「説明台詞」が多すぎ、政治経済の情報や考え方もちょっと無理があるところもあり、如何なものかと思うところもアリ辛い。何で財務大臣がこんな都会のベンチャー企業の社長の小さなオフィスみたいなところにいるのか?と思っただけで…。さらに、上演時間3時間20分越えて疲労困憊。金払っていってたら正直、途中で帰ったと思う。役者は巧い。すごい。
演出もいいです。ただ、本が長い。長すぎる事が全ての…
2011年9月9日@笹塚ファクトリー
ヨーロッパ企画「ロベルトの操縦」
作演出・上田誠
出演 石田剛太 酒井善史 永野宗典 西村直子 本多力 山脇唯 山本真由美 中山祐一朗(阿佐ヶ谷スパイダース)ほか

「ロードムービーのような」
海外に派兵された日本の若者の話。砂漠の中の駐屯地?では今日も大きな事件はなく暇を持て余している。整備していたロベルトという乗り物で、最初は手に入らないコーラー、そして、海へと遊びにいっちゃおう!そしたら、レイア姫とおぼしき人とであってしまって…というまさにロードムービー。でかいサンダーバードに出てきそうな大きなセット。フライング、巧い役者などが相まって良質な作品になっている。中山祐一朗などは、その持ち味が十分に発揮されていた。そして、思うのだが永野宗典という俳優は本当にいいなあと思う。100分でまとめてくれたのも嬉しい。2011年9月8日@本多劇場
作演出・上田誠
出演 石田剛太 酒井善史 永野宗典 西村直子 本多力 山脇唯 山本真由美 中山祐一朗(阿佐ヶ谷スパイダース)ほか
「ロードムービーのような」
海外に派兵された日本の若者の話。砂漠の中の駐屯地?では今日も大きな事件はなく暇を持て余している。整備していたロベルトという乗り物で、最初は手に入らないコーラー、そして、海へと遊びにいっちゃおう!そしたら、レイア姫とおぼしき人とであってしまって…というまさにロードムービー。でかいサンダーバードに出てきそうな大きなセット。フライング、巧い役者などが相まって良質な作品になっている。中山祐一朗などは、その持ち味が十分に発揮されていた。そして、思うのだが永野宗典という俳優は本当にいいなあと思う。100分でまとめてくれたのも嬉しい。2011年9月8日@本多劇場
最新記事
(01/06)
(12/25)
(08/05)
(06/30)
(12/16)
(08/21)
(04/10)
(09/25)
(11/30)
(11/18)
(11/03)
(10/04)
(09/19)
(08/28)
(06/25)
(06/10)
(12/30)
(02/21)
(12/31)
(09/28)
(06/09)
(05/12)
(12/31)
(09/08)
(06/02)
プロフィール
HN:
佐藤治彦 Haruhiko SATO
HP:
性別:
男性
職業:
演劇ユニット経済とH 主宰
趣味:
海外旅行
自己紹介:
演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員
カテゴリー
カレンダー
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新CM
[08/24 おばりーな]
[02/18 清水 悟]
[02/12 清水 悟]
[10/17 栗原 久美]
[10/16 うさきち]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(12/05)
(12/07)
(12/08)
(12/09)
(12/10)
(12/11)
(12/29)
(01/03)
(01/10)
(01/30)
(02/13)
(03/09)
(03/12)
(03/16)
(03/17)
(03/19)
(03/20)
(03/20)
(03/22)
(03/22)
(03/23)
(03/24)
(03/28)
(04/01)
(04/01)
カウンター
