自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
作 横内謙介
演出 杉田成道
出演 藤本美貴 山本亨 川西佑佳 高木トモユキ ほか
この作品は何回か観劇しているし、三木さつき、山中崇の初演が良かったと思っていたので、なかなかなじめなかったが、今回の上演はこの作品の良さと、そして、小劇場作品を大劇場で上演する場合の変更の仕方がとても上手くいっていて楽しめる作品となった。
主役のハカナのミキティの台詞廻しや演技について批判をする人が少なくない。確かに、彼女は彼女のままだし、少なくても明治以前の日本の女の雰囲気はほとんどない。ミキティが恋人に泣きついたり、ミキティが悲しんだり、愛したりするときのそのままでやっているのだろう。しかし、それでいいのである。彼女にこの舞台の稽古でスタイルを短い稽古期間で教え、トレーニングし演技してもらったら、気持ちの入らない型だけのものになってしまう可能性がでかい。そういう偽物を客は望んでいないのである。それよりは、ミキティのままで構わないから気持ち、感情を大切に演技を作ってもらう方がいいのだ。杉田成道さんの演出家としての選択の正しさがここに集約されている。そして、これは主役だけに許された特権だと思う。
一方、大口兼吾は台詞もスタイルもきちんとこなしていて、うまくミキティの相手役を務めたと思う。あっぱれだ。少し線が細いのが気になるが、あれだけ一本調子の分かりやすい演技をしながら、客に飽きさせないというのは大したものだ。昨年、新宿のシアターサンモールで、牧田明宏の不可思議な芝居をしていたのと同じ男が演技しているとは思えないほど、劇場というものを知っている。才能ってこういうことだろう。ベテランの山本亨や、村杉蝉之助といった俳優もこうした大劇場の舞台の溶け込み方をしっていてなるほどなあと思った。
こうした武器と制約のあるなかで、杉田成道さんの演出は王道で、美しかった。ホリヒロシの人形を導入したアイデアも秀逸だ。この作品はいつの間にか横内謙介の代表作として、何度も再演される演目に育ってきた。次はだれがどのような形で上演するのか、大変楽しみにしている。

2008年4月26日
明治座
演出 杉田成道
出演 藤本美貴 山本亨 川西佑佳 高木トモユキ ほか
この作品は何回か観劇しているし、三木さつき、山中崇の初演が良かったと思っていたので、なかなかなじめなかったが、今回の上演はこの作品の良さと、そして、小劇場作品を大劇場で上演する場合の変更の仕方がとても上手くいっていて楽しめる作品となった。
主役のハカナのミキティの台詞廻しや演技について批判をする人が少なくない。確かに、彼女は彼女のままだし、少なくても明治以前の日本の女の雰囲気はほとんどない。ミキティが恋人に泣きついたり、ミキティが悲しんだり、愛したりするときのそのままでやっているのだろう。しかし、それでいいのである。彼女にこの舞台の稽古でスタイルを短い稽古期間で教え、トレーニングし演技してもらったら、気持ちの入らない型だけのものになってしまう可能性がでかい。そういう偽物を客は望んでいないのである。それよりは、ミキティのままで構わないから気持ち、感情を大切に演技を作ってもらう方がいいのだ。杉田成道さんの演出家としての選択の正しさがここに集約されている。そして、これは主役だけに許された特権だと思う。
一方、大口兼吾は台詞もスタイルもきちんとこなしていて、うまくミキティの相手役を務めたと思う。あっぱれだ。少し線が細いのが気になるが、あれだけ一本調子の分かりやすい演技をしながら、客に飽きさせないというのは大したものだ。昨年、新宿のシアターサンモールで、牧田明宏の不可思議な芝居をしていたのと同じ男が演技しているとは思えないほど、劇場というものを知っている。才能ってこういうことだろう。ベテランの山本亨や、村杉蝉之助といった俳優もこうした大劇場の舞台の溶け込み方をしっていてなるほどなあと思った。
こうした武器と制約のあるなかで、杉田成道さんの演出は王道で、美しかった。ホリヒロシの人形を導入したアイデアも秀逸だ。この作品はいつの間にか横内謙介の代表作として、何度も再演される演目に育ってきた。次はだれがどのような形で上演するのか、大変楽しみにしている。
2008年4月26日
明治座
PR
作演出 田村孝裕
出演 田中直樹(ココリコ)小林隆 関川太郎 和田ひろ子 ほか
田村孝裕は既に大御所の域にあり、業界の注目やチェックも既にきびしいものになりつつある。業界は残酷だから、取りあえず持ち上げるところまでは持ち上げる。いまはその過程にある。そう言う中で、田村は、絶賛を受けた前回公演の「ゼブラ」のような作品など、向田邦子の世界を思わせる力作を書くかと思えば、そこに安住せずに、今回のような作品や、「パレード」のような作品も発表する。まだまだ、俺の守備範囲は広がるはずだと頑張っているのだ。その意気込みはスゴい。
今回は劇団公演ではあるが、表記の4人の出演者を中心に描かれる10数年の年月の話は、時に良く分からなかったりもするし、この作品って面白いのか?と思ったりもする。田村が書きたいことはこれなのだろうからそれでいい。もう観客に分かりやすく理解してもらうことだけを書く作家ではないのだ。特に劇団公演では。しかし、プロだからやり過ぎ、行き過ぎは抑えるのだろう。今回も、話がちょいだれそうになると、出番の少ない表記以外の劇団員がワンシーンづつ出てきて、渾身の力を込めてシーンを盛り上げて去って行く。素敵だなあ、劇団ってよーと思うのだ。
小林隆さんはパレードのような作品で見たかったなあとか、関川太郎には、もっとドロドロとした嫌な人間を書いてもらいたいと思うのだが、それはそれで、僕の希望というだけなのでどうでもいい。気になったのは、田中直樹の演技だ。もちろん、舞台人であるから、上手いのだが、時々演技者から芸人になってしまうことがあり、田中自身もぎりぎりのところでやろうと思っているのも伝わってくるのだが、ぎりぎりのところで留まりきれず、やりすぎてしまった部分があるような感じがして仕方がない。映画の場合は上手く編集されるけれど、舞台はそうはいかない。
引きこもりの役柄で、言わば自らを縛り付けるような、囲いの中に入って、そこから出て来ない窮屈な部分が大切なのだろう思うのだが、1時間50分、ほぼ出ずっぱりで演技している身としては、時々解放されてぇと思うのだろうなあ、と、思えて仕方がないのだ。それが、漏れてくるのはいいが、あからさまにしてしまってはいけないと思うのだが。どうだろう。的外れかな?
僕はこの劇団員の演技がとても好きだし、好感をもってる。恩田隆一や冨田直美、冨塚智など、観る度に上手くなってる。スゴいなあと思うのだ。

2008年4月24日
THEATER TOPS
出演 田中直樹(ココリコ)小林隆 関川太郎 和田ひろ子 ほか
田村孝裕は既に大御所の域にあり、業界の注目やチェックも既にきびしいものになりつつある。業界は残酷だから、取りあえず持ち上げるところまでは持ち上げる。いまはその過程にある。そう言う中で、田村は、絶賛を受けた前回公演の「ゼブラ」のような作品など、向田邦子の世界を思わせる力作を書くかと思えば、そこに安住せずに、今回のような作品や、「パレード」のような作品も発表する。まだまだ、俺の守備範囲は広がるはずだと頑張っているのだ。その意気込みはスゴい。
今回は劇団公演ではあるが、表記の4人の出演者を中心に描かれる10数年の年月の話は、時に良く分からなかったりもするし、この作品って面白いのか?と思ったりもする。田村が書きたいことはこれなのだろうからそれでいい。もう観客に分かりやすく理解してもらうことだけを書く作家ではないのだ。特に劇団公演では。しかし、プロだからやり過ぎ、行き過ぎは抑えるのだろう。今回も、話がちょいだれそうになると、出番の少ない表記以外の劇団員がワンシーンづつ出てきて、渾身の力を込めてシーンを盛り上げて去って行く。素敵だなあ、劇団ってよーと思うのだ。
小林隆さんはパレードのような作品で見たかったなあとか、関川太郎には、もっとドロドロとした嫌な人間を書いてもらいたいと思うのだが、それはそれで、僕の希望というだけなのでどうでもいい。気になったのは、田中直樹の演技だ。もちろん、舞台人であるから、上手いのだが、時々演技者から芸人になってしまうことがあり、田中自身もぎりぎりのところでやろうと思っているのも伝わってくるのだが、ぎりぎりのところで留まりきれず、やりすぎてしまった部分があるような感じがして仕方がない。映画の場合は上手く編集されるけれど、舞台はそうはいかない。
引きこもりの役柄で、言わば自らを縛り付けるような、囲いの中に入って、そこから出て来ない窮屈な部分が大切なのだろう思うのだが、1時間50分、ほぼ出ずっぱりで演技している身としては、時々解放されてぇと思うのだろうなあ、と、思えて仕方がないのだ。それが、漏れてくるのはいいが、あからさまにしてしまってはいけないと思うのだが。どうだろう。的外れかな?
僕はこの劇団員の演技がとても好きだし、好感をもってる。恩田隆一や冨田直美、冨塚智など、観る度に上手くなってる。スゴいなあと思うのだ。
2008年4月24日
THEATER TOPS
作/演出 中島淳彦
出演
福島まり子 小林美江 ほか
昨年に続いて二度目のハートランド。中島淳彦さんのお芝居はそれこそ何もおきないし、偉そうな台詞はないのに、人生の真髄がどかーんと伝わるし、笑いと愛情に満ちていて嬉しくなる。ものすごい技術とハートの凝縮である。しかし、この芝居は、名うての役者さんでないときっと見てられない。役者に高度な演技力とセンスを求める、とても難しい台本なのである。言ってみれば、フォアグラとか、イベリコ豚、インドマグロ。良く分からないけれど、最高の食材だが、上手に調理しないと、不味くて食えなくなってしまう。そんな台本なのだ。だから、中島淳彦の見事な台本と演出もスゴいのだが、役者さんたちのスゴさを上げたい。
先ずは、福島まり子がべらぼうに上手い。歩く、顔を向ける、息を止める。それぞれが、自然なのにべらぼうにナイスなタイミングと量である。もちろん小林美江さんもそうである。テーブルに隠れる。出てくる。その出る時のスピード。タイミング。どんな顔で出てくるか。全てが素晴らしい。もう本当にビーンズを早くやって欲しいなあ。
そして、大西多摩恵さん。高度に作り上げたキャラを一糸乱れぬ見事な力と心で演じきった。誰もが面白いと思っただろう。さすが永井愛さんの秘蔵っ子だ。素晴らしい、ホントに素晴らしい。
保谷果菜子さん、高橋亜矢子さんは去年を上回る見事な演技。保谷さんは大西さん同様にキャラを作り上げ、その人物を掘り下げた。高橋さんは、気持ちの切り替えのタイミングが気持ちよく、笑いを誘う。渡辺由紀子さんは、不思議な色気があって物語の中軸でスゴくいい仕事をし、神田繁子さんも不思議な女性を上手く演じていた。万引きした商品を差し出すところなんか、ただ洋服から隠した商品を出すだけ、それも、客はネタも分かっているのに笑える。スゴい!!!
江原里実のでかい声も間違うと毎回大しらけになる危険性があるのに、外さない。冒険をし成功した。本当に面白かった。本当に楽しかった。見事な役者さんの演技が本当にこの芝居を成功に導いたのだ!
美術は無駄もなく、レジの位置やカウンターの座席数。テーブルの位置や椅子の形状などに粋で微妙な配慮があって、美術が芝居の演技を大いに盛りたてた。衣装もこだわりもあって、それでいて華美になりすぎずにセンスの良さを感じさせた。
こういう一級の芝居はなかなか観られない。このメンバーなら、ぜひとも「8人の女たち」舞台版を見てみたいものだ。

ザスズナリ
2008年4月21日
出演
福島まり子 小林美江 ほか
昨年に続いて二度目のハートランド。中島淳彦さんのお芝居はそれこそ何もおきないし、偉そうな台詞はないのに、人生の真髄がどかーんと伝わるし、笑いと愛情に満ちていて嬉しくなる。ものすごい技術とハートの凝縮である。しかし、この芝居は、名うての役者さんでないときっと見てられない。役者に高度な演技力とセンスを求める、とても難しい台本なのである。言ってみれば、フォアグラとか、イベリコ豚、インドマグロ。良く分からないけれど、最高の食材だが、上手に調理しないと、不味くて食えなくなってしまう。そんな台本なのだ。だから、中島淳彦の見事な台本と演出もスゴいのだが、役者さんたちのスゴさを上げたい。
先ずは、福島まり子がべらぼうに上手い。歩く、顔を向ける、息を止める。それぞれが、自然なのにべらぼうにナイスなタイミングと量である。もちろん小林美江さんもそうである。テーブルに隠れる。出てくる。その出る時のスピード。タイミング。どんな顔で出てくるか。全てが素晴らしい。もう本当にビーンズを早くやって欲しいなあ。
そして、大西多摩恵さん。高度に作り上げたキャラを一糸乱れぬ見事な力と心で演じきった。誰もが面白いと思っただろう。さすが永井愛さんの秘蔵っ子だ。素晴らしい、ホントに素晴らしい。
保谷果菜子さん、高橋亜矢子さんは去年を上回る見事な演技。保谷さんは大西さん同様にキャラを作り上げ、その人物を掘り下げた。高橋さんは、気持ちの切り替えのタイミングが気持ちよく、笑いを誘う。渡辺由紀子さんは、不思議な色気があって物語の中軸でスゴくいい仕事をし、神田繁子さんも不思議な女性を上手く演じていた。万引きした商品を差し出すところなんか、ただ洋服から隠した商品を出すだけ、それも、客はネタも分かっているのに笑える。スゴい!!!
江原里実のでかい声も間違うと毎回大しらけになる危険性があるのに、外さない。冒険をし成功した。本当に面白かった。本当に楽しかった。見事な役者さんの演技が本当にこの芝居を成功に導いたのだ!
美術は無駄もなく、レジの位置やカウンターの座席数。テーブルの位置や椅子の形状などに粋で微妙な配慮があって、美術が芝居の演技を大いに盛りたてた。衣装もこだわりもあって、それでいて華美になりすぎずにセンスの良さを感じさせた。
こういう一級の芝居はなかなか観られない。このメンバーなら、ぜひとも「8人の女たち」舞台版を見てみたいものだ。
ザスズナリ
2008年4月21日
チャイコフスキー作曲
小沢征爾指揮 東京のオペラの森管弦楽団
東京のクラシック音楽のファンから小沢征爾の評判はすこぶる良くない。ワシリーゲルギレフと並んで、音楽ビジネス界との乖離が目立つ有名指揮者の二人である。そして、今回の作品でその評価は決定づけられるだろう。なぜなら、チャイコフスキーの「スペードの女王」と「エフゲニーオネーギン」は小沢征爾にとっての十八番。古典派の正統的なドイツ音楽で世界の頂点に立つことは日本人である小沢征爾にはあまりにも壁が高い。そこで、小沢征爾は、マーラーやストラヴィンスキー、バルトークといった複雑なオーケストレーションで豊麗なサウンドが求められるものに活路をもとめて評価を得たのだ。そして、チャイコフスキーやドヴォルジャークのような民族の薫りの高いものもそれに入る。特にオペラに関しては、このチャイコフスキーの二作品はパリでもウィーンでも圧倒的な評価を得たはずである。
しかし、今宵の演奏は本当にがっかりした。サウンドが淡白なのだ。いぶし銀の枯れた良さではない。1週間前にロシア人指揮者のベートベーンをきいたばかりだが、何と豊麗なサウンドでよわせてくれたことか。この作品の音楽からはロシアの大地と気候の厳しさ、そこに過ごす人々とその文化を思わせるような深みがなければならない。舞台はシンプルで大量の雪がそれこそ美しく1時間以上も降り続け、舞台には雪が積もっていくのだが、それ以外には特に舞台装置はない。ロシアを表現することは美術でも照明でもなく音楽に託されているのだ。それが、深みのないさらっとした音楽だった。時折大げさにテンポを動かしてみたり、アクセントをつけてみたり、フォルテにしてみたりするのだが、それこそ不要の産物なのである。
僕らの敬愛した小沢征爾はいったいどうなってしまったのか?もう、十八番でこのレベルなのか?
正直申し上げる。今回の小沢征爾の音楽で感動できなかったら、これが小沢征爾を生で聴く最後の機会だろうと思って出かけた。そして、そうなってしまった。もう36000円も払ってこんなつまらない音楽にお金も時間もつかいたくない。僕は、「エフゲニーオネーギン」は日本でも世界中で何本も見ているが、もっとも酷いものだった。
歌手は一幕はひやひやしたりもした。タチアーナのプリバンはフルボイスで歌わないし、オネーギンのイェルスも制御していた。まあ、後半は素晴らしかったけれど。マリウス・プレンチウのレンスキーは良く、グレーミン公爵のシュテファン・コツァンは絶妙のユーモアを交えて歌っていた。
コーラスは良く、ダンスを踊った若い日本人たちも魅力的だった。歌手たちがどんどんロシア的になっていくのに、小沢サウンドは追いついていくのに必死だった。
かつて小沢征爾といえば、日本を代表するというよりも、世界的な名匠として一世を風靡した。ヘルベルトフォンカラヤンとシャルルミュンシュの直弟子を標榜し絶大な政治力もあって音楽界に君臨した。30年以上在籍したボストン交響楽団のあと、手に入れたウィーン国立歌劇場の音楽監督も再任されることなく、いったいこれから何をするのだろう。
いづれにせよ、自分の財布から大枚をだしてこの指揮者をきくのは、特別のことがない限り、これが最後となると思う。秋のウィーン国立歌劇場の公演で「フィデリオ」を公演するが辞めておいた方がいい。今の小澤が一般の人にも深みのない音楽しか出来ないことがばれてしまうのではないか?
特に、「フィデリオ」は、この10年あまりの間にクラウディオアバドがイースター音楽祭の来日公演と称してベルリンフィルで素晴らしい演奏をしている。それ以外にもバイエルン国立歌劇場も、新国立歌劇場でさえ名演を残している。歌手とオケは最高の布陣=ウィーン国立歌劇場で振る限りは言い訳は許されない。小沢征爾。ああ、あの生きる活力に満ちていた小澤さん。そのかつてのアイドルが墜ちていくのを観るのが本当に辛い。


2008年4月18日
東京文化会館大ホール
小沢征爾指揮 東京のオペラの森管弦楽団
東京のクラシック音楽のファンから小沢征爾の評判はすこぶる良くない。ワシリーゲルギレフと並んで、音楽ビジネス界との乖離が目立つ有名指揮者の二人である。そして、今回の作品でその評価は決定づけられるだろう。なぜなら、チャイコフスキーの「スペードの女王」と「エフゲニーオネーギン」は小沢征爾にとっての十八番。古典派の正統的なドイツ音楽で世界の頂点に立つことは日本人である小沢征爾にはあまりにも壁が高い。そこで、小沢征爾は、マーラーやストラヴィンスキー、バルトークといった複雑なオーケストレーションで豊麗なサウンドが求められるものに活路をもとめて評価を得たのだ。そして、チャイコフスキーやドヴォルジャークのような民族の薫りの高いものもそれに入る。特にオペラに関しては、このチャイコフスキーの二作品はパリでもウィーンでも圧倒的な評価を得たはずである。
しかし、今宵の演奏は本当にがっかりした。サウンドが淡白なのだ。いぶし銀の枯れた良さではない。1週間前にロシア人指揮者のベートベーンをきいたばかりだが、何と豊麗なサウンドでよわせてくれたことか。この作品の音楽からはロシアの大地と気候の厳しさ、そこに過ごす人々とその文化を思わせるような深みがなければならない。舞台はシンプルで大量の雪がそれこそ美しく1時間以上も降り続け、舞台には雪が積もっていくのだが、それ以外には特に舞台装置はない。ロシアを表現することは美術でも照明でもなく音楽に託されているのだ。それが、深みのないさらっとした音楽だった。時折大げさにテンポを動かしてみたり、アクセントをつけてみたり、フォルテにしてみたりするのだが、それこそ不要の産物なのである。
僕らの敬愛した小沢征爾はいったいどうなってしまったのか?もう、十八番でこのレベルなのか?
正直申し上げる。今回の小沢征爾の音楽で感動できなかったら、これが小沢征爾を生で聴く最後の機会だろうと思って出かけた。そして、そうなってしまった。もう36000円も払ってこんなつまらない音楽にお金も時間もつかいたくない。僕は、「エフゲニーオネーギン」は日本でも世界中で何本も見ているが、もっとも酷いものだった。
歌手は一幕はひやひやしたりもした。タチアーナのプリバンはフルボイスで歌わないし、オネーギンのイェルスも制御していた。まあ、後半は素晴らしかったけれど。マリウス・プレンチウのレンスキーは良く、グレーミン公爵のシュテファン・コツァンは絶妙のユーモアを交えて歌っていた。
コーラスは良く、ダンスを踊った若い日本人たちも魅力的だった。歌手たちがどんどんロシア的になっていくのに、小沢サウンドは追いついていくのに必死だった。
かつて小沢征爾といえば、日本を代表するというよりも、世界的な名匠として一世を風靡した。ヘルベルトフォンカラヤンとシャルルミュンシュの直弟子を標榜し絶大な政治力もあって音楽界に君臨した。30年以上在籍したボストン交響楽団のあと、手に入れたウィーン国立歌劇場の音楽監督も再任されることなく、いったいこれから何をするのだろう。
いづれにせよ、自分の財布から大枚をだしてこの指揮者をきくのは、特別のことがない限り、これが最後となると思う。秋のウィーン国立歌劇場の公演で「フィデリオ」を公演するが辞めておいた方がいい。今の小澤が一般の人にも深みのない音楽しか出来ないことがばれてしまうのではないか?
特に、「フィデリオ」は、この10年あまりの間にクラウディオアバドがイースター音楽祭の来日公演と称してベルリンフィルで素晴らしい演奏をしている。それ以外にもバイエルン国立歌劇場も、新国立歌劇場でさえ名演を残している。歌手とオケは最高の布陣=ウィーン国立歌劇場で振る限りは言い訳は許されない。小沢征爾。ああ、あの生きる活力に満ちていた小澤さん。そのかつてのアイドルが墜ちていくのを観るのが本当に辛い。
2008年4月18日
東京文化会館大ホール
わがぎえふ脚本 マキノノゾミ演出
出演 沢田研二 加納幸和 土居裕子 土田早苗 木下政治 有馬自由 野田晋市 小椋あずき

こういう芝居を待っていた。王道の台本、現代の王道としての演出。華のある看板役者、個性的で芝居の上手い出演社たち、衣装も踊りも美術もよくて、そして、その上に音楽がある。
昭和に消えた大阪船場の若旦那。二枚目、粋、格好良く遊ぶ、女にモテて女に優しい。義理人情にあつく、ちょいとのことではへこたれない。うるさい祖母と妻にライバルたち。かつて花登筺が書いた関西の商売ものの流れもあって、これ王道ものなのだ。もちろん作品は山崎豊子原作だし、こちらは、第二次世界大戦で破壊された大阪とそこから希望をもち再起を誓う姿で終わるところなどは、もうコテコテと言ってもいいくらいで、こうした小さな劇場で観られる贅沢さを感じるのだ。
沢田研二は少し太ったかなと思うけれど、見事な歌唱と、志村けんさん風の肉体を使ったギャグを仕込んでお客さんに大サービス。大金持ちの旦那で加納さんが、品格ある立ち振る舞い。踊りも仕草も一日二日でできないものを披露している。わかぎえふさんだけに、加納さん、有馬自由さん、野田さん、木下さんの見せ場の作り方を心得ていらっしゃる。出演者全員が主要な役所がある暖かい台本だ。そして、それらは全部沢田研二さんが得になるようにできているのだ。
土田早苗さんや、小椋あずきさんの見事な意地悪女の役も、細腕繁盛記の正子のように、微笑ましく楽しい。また、美術がキレイで、衣装が豪華で驚いた。
2時間40分飽きさせない、日本の王道エンタティメントはここにある。
2008年4月15日
紀伊国屋サザンシアター
出演 沢田研二 加納幸和 土居裕子 土田早苗 木下政治 有馬自由 野田晋市 小椋あずき
こういう芝居を待っていた。王道の台本、現代の王道としての演出。華のある看板役者、個性的で芝居の上手い出演社たち、衣装も踊りも美術もよくて、そして、その上に音楽がある。
昭和に消えた大阪船場の若旦那。二枚目、粋、格好良く遊ぶ、女にモテて女に優しい。義理人情にあつく、ちょいとのことではへこたれない。うるさい祖母と妻にライバルたち。かつて花登筺が書いた関西の商売ものの流れもあって、これ王道ものなのだ。もちろん作品は山崎豊子原作だし、こちらは、第二次世界大戦で破壊された大阪とそこから希望をもち再起を誓う姿で終わるところなどは、もうコテコテと言ってもいいくらいで、こうした小さな劇場で観られる贅沢さを感じるのだ。
沢田研二は少し太ったかなと思うけれど、見事な歌唱と、志村けんさん風の肉体を使ったギャグを仕込んでお客さんに大サービス。大金持ちの旦那で加納さんが、品格ある立ち振る舞い。踊りも仕草も一日二日でできないものを披露している。わかぎえふさんだけに、加納さん、有馬自由さん、野田さん、木下さんの見せ場の作り方を心得ていらっしゃる。出演者全員が主要な役所がある暖かい台本だ。そして、それらは全部沢田研二さんが得になるようにできているのだ。
土田早苗さんや、小椋あずきさんの見事な意地悪女の役も、細腕繁盛記の正子のように、微笑ましく楽しい。また、美術がキレイで、衣装が豪華で驚いた。
2時間40分飽きさせない、日本の王道エンタティメントはここにある。
2008年4月15日
紀伊国屋サザンシアター
ドミトリーキタエンコ指揮
アンドレイ・ガヴリーロフ ピアノ独奏
クロアチアを代表するオケ、ザグレブフィルハーモニー管弦楽団の演奏会をホームグラウンドであるザグレブのレシンスキーホールできいた。このホールは2000人以上入る大ホールである。音の轟は決して悪くはないが、残響が少なく豊潤な音がきけるホールではない。しかし、各オケは自らのホームグラウンドを熟知している。そして、僕はこの夜、とてもいい演奏を聴けたのである。
クロアチアは、ユーゴ時代に、社会主義を標榜しながらもソビエト連邦との距離感を持っていた歴史はあるが、大枠ではソビエトの影響を受けていないわけがない。現存するロシア人指揮者としては最高峰のひとりドミトリーキタエンコを迎えてのベートーベンプロ。
ロシアの演奏でいつも思うのだが、良く鳴るのである。音の固まりが客席にガンガン跳んでくるのだ。現代的かどうかは別として、一寸無骨なベートーヴェンにはマッチしているから不思議だ。
さて、ピアノ協奏曲。かつてガブリーロフは1974年にチャイコフスキーコンクールで優勝したソビエト期待のピアニストであった。当時18歳だったはず。超絶技巧でドイツグラモフォンにも数々の録音を入れ、名実共にリヒテル後のロシア人ピアニストの筆頭になるはずの人だった。そのプレッシャーからか、薬物中毒になりしばらく演奏から遠ざかったのだった。近年復帰。
そして、今宵もそのピアノは荒れたものだった。数多くのミスタッチ。感情が不安定なのが良く分かるフレージング。時折見せる美しい音も、意味もなく叩き付けられた鍵盤から響く音も、何か無意味に怒っている良く分からない人のようで怖くなってしまう。無意味に腕とか手を高くあげたりするんです。パフォーマンス?
アンコールで、ショパンを弾いたがこれもイマイチだった。ところが、その次に弾いたプロコフィエフは、曲そのものが感情が行ったり来たり、急に爆発したりする音楽だったのでぴったりだった。これだけはブラボーもの。
いづれにせよ、コンチェルトはオケが良いだけにちょいと残念だった。
後半の7番交響曲は、オケが落ち着いてたっぷりと聞かせてくれた。弦の音が美しくアンサンブルもピッチの合い方がとても良く素晴らしい出来。金管木管系も良く期待以上の出来でした。
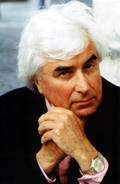
ベートーベン エグモンド序曲
ピアノ協奏曲3番
交響曲第7番
http://www.zgf.hr/en/news.php

2008年4月11日
リシンスキー・ホール (ザグレブ/クロアチア)
アンドレイ・ガヴリーロフ ピアノ独奏
クロアチアを代表するオケ、ザグレブフィルハーモニー管弦楽団の演奏会をホームグラウンドであるザグレブのレシンスキーホールできいた。このホールは2000人以上入る大ホールである。音の轟は決して悪くはないが、残響が少なく豊潤な音がきけるホールではない。しかし、各オケは自らのホームグラウンドを熟知している。そして、僕はこの夜、とてもいい演奏を聴けたのである。
クロアチアは、ユーゴ時代に、社会主義を標榜しながらもソビエト連邦との距離感を持っていた歴史はあるが、大枠ではソビエトの影響を受けていないわけがない。現存するロシア人指揮者としては最高峰のひとりドミトリーキタエンコを迎えてのベートーベンプロ。
ロシアの演奏でいつも思うのだが、良く鳴るのである。音の固まりが客席にガンガン跳んでくるのだ。現代的かどうかは別として、一寸無骨なベートーヴェンにはマッチしているから不思議だ。
さて、ピアノ協奏曲。かつてガブリーロフは1974年にチャイコフスキーコンクールで優勝したソビエト期待のピアニストであった。当時18歳だったはず。超絶技巧でドイツグラモフォンにも数々の録音を入れ、名実共にリヒテル後のロシア人ピアニストの筆頭になるはずの人だった。そのプレッシャーからか、薬物中毒になりしばらく演奏から遠ざかったのだった。近年復帰。
そして、今宵もそのピアノは荒れたものだった。数多くのミスタッチ。感情が不安定なのが良く分かるフレージング。時折見せる美しい音も、意味もなく叩き付けられた鍵盤から響く音も、何か無意味に怒っている良く分からない人のようで怖くなってしまう。無意味に腕とか手を高くあげたりするんです。パフォーマンス?
アンコールで、ショパンを弾いたがこれもイマイチだった。ところが、その次に弾いたプロコフィエフは、曲そのものが感情が行ったり来たり、急に爆発したりする音楽だったのでぴったりだった。これだけはブラボーもの。
いづれにせよ、コンチェルトはオケが良いだけにちょいと残念だった。
後半の7番交響曲は、オケが落ち着いてたっぷりと聞かせてくれた。弦の音が美しくアンサンブルもピッチの合い方がとても良く素晴らしい出来。金管木管系も良く期待以上の出来でした。
ベートーベン エグモンド序曲
ピアノ協奏曲3番
交響曲第7番
http://www.zgf.hr/en/news.php
2008年4月11日
リシンスキー・ホール (ザグレブ/クロアチア)
監督 デンゼルワシントン
脚本 ロバートアイズル
出演 デンゼルワシントン フォレストウィットテーカー
アメリカという国のユニークさはこういう素晴らしい映画作品が生まれてくることだ。時に政権のあまりにもの身勝手さや横暴さにアメリカ全体を否定してしたくなることもあるだろう。しかし、それを批判し新たな動きを導きだすのもアメリカなのである。デンゼルワシントン監督第二作目になるこの作品はまぎれもない感動大作になっており、暴力でなく心と言葉と思想で世の中を変えていけるというメッセージが含まれている作品である。もちろんハリウッド映画である。決して押し付けがましくもなく、自然に、ひとりの人間の生き方、成長を通して訴えかけてくるのである。
1930年代の南部アメリカを舞台に素晴らしい映画が出来上がった。久々に泣きながら見た作品となった。真面目にデンゼルワシントンにファンレターを出したくなったくらいだ。そんな感想しか持てません。あ、音楽もいいです。正統派の映画音楽でした。

公式ホームページ http://www.thegreatdebatersmovie.com/
日本語解説 http://www.blackmovie-jp.com/movie/greatdebaters.php
脚本 ロバートアイズル
出演 デンゼルワシントン フォレストウィットテーカー
アメリカという国のユニークさはこういう素晴らしい映画作品が生まれてくることだ。時に政権のあまりにもの身勝手さや横暴さにアメリカ全体を否定してしたくなることもあるだろう。しかし、それを批判し新たな動きを導きだすのもアメリカなのである。デンゼルワシントン監督第二作目になるこの作品はまぎれもない感動大作になっており、暴力でなく心と言葉と思想で世の中を変えていけるというメッセージが含まれている作品である。もちろんハリウッド映画である。決して押し付けがましくもなく、自然に、ひとりの人間の生き方、成長を通して訴えかけてくるのである。
1930年代の南部アメリカを舞台に素晴らしい映画が出来上がった。久々に泣きながら見た作品となった。真面目にデンゼルワシントンにファンレターを出したくなったくらいだ。そんな感想しか持てません。あ、音楽もいいです。正統派の映画音楽でした。
公式ホームページ http://www.thegreatdebatersmovie.com/
日本語解説 http://www.blackmovie-jp.com/movie/greatdebaters.php
Brian Friel 作
Jaltska igra
言語学については何も知識がないので何ともいえないが、スラブ系の言語には独特の響きがあり、低音の魅力に富んでいる。かつてモスクワ芸術座を初めとするロシアの舞台を見た時も、ああ、チェホフの言葉はこんな響きなんだと思った次第。それでなくても、古い英語のシェイクスピアも、ベルリナーアンサンブルのドイツ語も、ミラノピッコロ座のイタリア語も、フランス太陽劇団のフランス語も独特のものがあるそれ。特に外国の劇場で観る時には、現地の観客の反応も見られるわけだから興味を引くに決まっている。旅行で訪れたスロベニア。オーストリアとイタリアに国境を接した国。その首都のリュブリアナ随一の劇場 MALADRAMA劇場に足を運んでみた。この劇場はチェホフも、ワイルドも、テネシーウィリアムズも、三島もやっているのだ。
旅行中の夜に何もすることがなくて、劇場に行ってみた。チケットを手に入れようとしたのだが、売切れ。キャンセル待ちをしていたら、僕がチケットを売ってくれと声をかけているのをみたスケボー少年共々、無料で劇場に入れてくれた。
この劇場の小劇場は100人強のキャパの劇場だが、奥行きのある舞台に、椅子とテーブルがおかれているだけのシンプルな舞台。そこでの二人芝居。恋の駆け引きをする中年男と若い女の恋の話だった。言葉は分からないが、何となく関係性は分かる。
台本は心情吐露のシーンで繋いでいくのかよ!と思うくらいにいろいろと、これでもかって二人に語らせる。二人の会話と心情吐露で繋いでいくって感じなのだが、特にベテランの男がとても上手くて魅入ってしまう。観客は平均年齢50歳ってところか。週末にちょいとシニカルで知的な芝居をみにきた人がクスクス笑いを連発していた。きっと一生に一度しかこの劇場には来ないのだろうけど、親切にも無料で見せてくれてありがとうございました。


劇場公式ホームページ http://www.drama.si/eng/
マラ ドラマ劇場 小劇場(リュブリアーナ/スロベニア)
2008年4月5日
Jaltska igra
言語学については何も知識がないので何ともいえないが、スラブ系の言語には独特の響きがあり、低音の魅力に富んでいる。かつてモスクワ芸術座を初めとするロシアの舞台を見た時も、ああ、チェホフの言葉はこんな響きなんだと思った次第。それでなくても、古い英語のシェイクスピアも、ベルリナーアンサンブルのドイツ語も、ミラノピッコロ座のイタリア語も、フランス太陽劇団のフランス語も独特のものがあるそれ。特に外国の劇場で観る時には、現地の観客の反応も見られるわけだから興味を引くに決まっている。旅行で訪れたスロベニア。オーストリアとイタリアに国境を接した国。その首都のリュブリアナ随一の劇場 MALADRAMA劇場に足を運んでみた。この劇場はチェホフも、ワイルドも、テネシーウィリアムズも、三島もやっているのだ。
旅行中の夜に何もすることがなくて、劇場に行ってみた。チケットを手に入れようとしたのだが、売切れ。キャンセル待ちをしていたら、僕がチケットを売ってくれと声をかけているのをみたスケボー少年共々、無料で劇場に入れてくれた。
この劇場の小劇場は100人強のキャパの劇場だが、奥行きのある舞台に、椅子とテーブルがおかれているだけのシンプルな舞台。そこでの二人芝居。恋の駆け引きをする中年男と若い女の恋の話だった。言葉は分からないが、何となく関係性は分かる。
台本は心情吐露のシーンで繋いでいくのかよ!と思うくらいにいろいろと、これでもかって二人に語らせる。二人の会話と心情吐露で繋いでいくって感じなのだが、特にベテランの男がとても上手くて魅入ってしまう。観客は平均年齢50歳ってところか。週末にちょいとシニカルで知的な芝居をみにきた人がクスクス笑いを連発していた。きっと一生に一度しかこの劇場には来ないのだろうけど、親切にも無料で見せてくれてありがとうございました。
劇場公式ホームページ http://www.drama.si/eng/
マラ ドラマ劇場 小劇場(リュブリアーナ/スロベニア)
2008年4月5日
監督 中村義洋
脚本 斎藤ひろし ほか
出演 竹内結子 阿部寛 吉川晃司 國村隼 平泉成 山口良一 野際陽子 ほか
大変優れた知的エンタティメント。物語は冒頭から核心から始まる。すぐに犯人探しが始まるのだ。映画で良くある冒頭の人物紹介のシークエンスなどは、竹内結子が事情聴取をするときに全て処理がされるので無駄がまったくない。ステージもののように、舞台は病院内にしぼられていて、非常に濃密な空気となる。クールな空気が流れている映画の中に、「エグイ」手術のシーンや山口良一さんのトチ狂ったロック中年の歌や死んだ後のMRIのシーンなどが放り込まれる現代的なセンスは、ケラリーノサンドロビッチの芝居のごとくである。キャラが強い阿部寛を冒頭から出さないので、きちんと登場人物ひとりひとりを観客に紹介し分からせた後で出したのも成功。脚本がいいのだ。手術のシーンなどは緊迫感もあり細部にまでこだわっていることが伺い知れる。後半は竹内、阿部と観客も謎解きに参加できるようになっており、いやはや良く出来ている。
台本で唯一残念なのは、犯人がその殺人の動機を「面白そうだったので殺した」みたいな理由をいうだけで終わってしまうこと。それは、それでいいのだが、それまでが、すべてクールな感じだったので、急にいわれて夢落ちみたいな感じになってしまった。そんな結末なら何でもありじゃん。
犯人がもう人間として壊れていることを前半で暗示するようなシーンがあったら良かったのにと思った次第。

公式ホームページ http://www.team-b.jp/index.html
脚本 斎藤ひろし ほか
出演 竹内結子 阿部寛 吉川晃司 國村隼 平泉成 山口良一 野際陽子 ほか
大変優れた知的エンタティメント。物語は冒頭から核心から始まる。すぐに犯人探しが始まるのだ。映画で良くある冒頭の人物紹介のシークエンスなどは、竹内結子が事情聴取をするときに全て処理がされるので無駄がまったくない。ステージもののように、舞台は病院内にしぼられていて、非常に濃密な空気となる。クールな空気が流れている映画の中に、「エグイ」手術のシーンや山口良一さんのトチ狂ったロック中年の歌や死んだ後のMRIのシーンなどが放り込まれる現代的なセンスは、ケラリーノサンドロビッチの芝居のごとくである。キャラが強い阿部寛を冒頭から出さないので、きちんと登場人物ひとりひとりを観客に紹介し分からせた後で出したのも成功。脚本がいいのだ。手術のシーンなどは緊迫感もあり細部にまでこだわっていることが伺い知れる。後半は竹内、阿部と観客も謎解きに参加できるようになっており、いやはや良く出来ている。
台本で唯一残念なのは、犯人がその殺人の動機を「面白そうだったので殺した」みたいな理由をいうだけで終わってしまうこと。それは、それでいいのだが、それまでが、すべてクールな感じだったので、急にいわれて夢落ちみたいな感じになってしまった。そんな結末なら何でもありじゃん。
犯人がもう人間として壊れていることを前半で暗示するようなシーンがあったら良かったのにと思った次第。
公式ホームページ http://www.team-b.jp/index.html
監督 平川雄一朗
脚本 金子ありさ
出演 岡田准一 西田敏行 平山あや 三浦友和 ほか
昨年岡田准一さんと仕事をしたこともあるし、売れない頃の劇団ひとりのステージを見ていたものとして、ちょっと見てしまったらぐいぐい引き込まれた。先ずは台本がスゴくいい。原作は短編小説集なのだが、それを上手く縦横無尽に折込んだ。西田敏行が相変わらず面白いし、三浦友和が社会の底辺で生きるどうしようもない鬱積感を静かに表現している。頑張れよ!って簡単に言っちゃいけないなと思ってしまった。人間は歯車が上手く行かないとなかなか這い上がれないものなのです。
また、多くの人の善意を感じながらもそれに応えられない岡田准一のダメ男ぶりがとてもいいです。見た人が、他人に対してもっと優しくなれる映画だと思いました。
こういう秀作が今の日本映画には生まれているということを、すごく羨ましく思う。僕の中学高校時代は、ホントごく限られた人以外の作品は、大人の鑑賞に堪えうるものが少なかったし。

公式ホームページ http://www.kage-hinata.jp/index.html
脚本 金子ありさ
出演 岡田准一 西田敏行 平山あや 三浦友和 ほか
昨年岡田准一さんと仕事をしたこともあるし、売れない頃の劇団ひとりのステージを見ていたものとして、ちょっと見てしまったらぐいぐい引き込まれた。先ずは台本がスゴくいい。原作は短編小説集なのだが、それを上手く縦横無尽に折込んだ。西田敏行が相変わらず面白いし、三浦友和が社会の底辺で生きるどうしようもない鬱積感を静かに表現している。頑張れよ!って簡単に言っちゃいけないなと思ってしまった。人間は歯車が上手く行かないとなかなか這い上がれないものなのです。
また、多くの人の善意を感じながらもそれに応えられない岡田准一のダメ男ぶりがとてもいいです。見た人が、他人に対してもっと優しくなれる映画だと思いました。
こういう秀作が今の日本映画には生まれているということを、すごく羨ましく思う。僕の中学高校時代は、ホントごく限られた人以外の作品は、大人の鑑賞に堪えうるものが少なかったし。
公式ホームページ http://www.kage-hinata.jp/index.html
最新記事
(01/06)
(12/25)
(08/05)
(06/30)
(12/16)
(08/21)
(04/10)
(09/25)
(11/30)
(11/18)
(11/03)
(10/04)
(09/19)
(08/28)
(06/25)
(06/10)
(12/30)
(02/21)
(12/31)
(09/28)
(06/09)
(05/12)
(12/31)
(09/08)
(06/02)
プロフィール
HN:
佐藤治彦 Haruhiko SATO
HP:
性別:
男性
職業:
演劇ユニット経済とH 主宰
趣味:
海外旅行
自己紹介:
演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員
カテゴリー
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
フリーエリア
最新CM
[08/24 おばりーな]
[02/18 清水 悟]
[02/12 清水 悟]
[10/17 栗原 久美]
[10/16 うさきち]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(12/05)
(12/07)
(12/08)
(12/09)
(12/10)
(12/11)
(12/29)
(01/03)
(01/10)
(01/30)
(02/13)
(03/09)
(03/12)
(03/16)
(03/17)
(03/19)
(03/20)
(03/20)
(03/22)
(03/22)
(03/23)
(03/24)
(03/28)
(04/01)
(04/01)
カウンター
