自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
作演出 柿ノ木タケヲ

お客さんは喜んでいたし、個々の俳優はとても魅力的な人たちがいるのだが、自分の心が動かないのはなぜだろう。それは、例えば、お客の受けはいいものの、途中で物語を寸断してコント系の空気に換えてしまうからか。それをするには、新感線級の技量が必要とされるのではないか。ホント、全編に新感線の影響を強く感じた。僕が感心したのは芝居以上に、折り込みに入っていたそのアンケートだった。精密な調査項目が並べられていた。書き込めば景品をくれるというのだけれど、景品よりもこのアンケート用紙をもらって帰る方がいいなと思ったくらい。このデータをどう集計し、劇団活動に生かすのか。とても気になった。
2008年6月25日
下北沢OFFOFFシアター
お客さんは喜んでいたし、個々の俳優はとても魅力的な人たちがいるのだが、自分の心が動かないのはなぜだろう。それは、例えば、お客の受けはいいものの、途中で物語を寸断してコント系の空気に換えてしまうからか。それをするには、新感線級の技量が必要とされるのではないか。ホント、全編に新感線の影響を強く感じた。僕が感心したのは芝居以上に、折り込みに入っていたそのアンケートだった。精密な調査項目が並べられていた。書き込めば景品をくれるというのだけれど、景品よりもこのアンケート用紙をもらって帰る方がいいなと思ったくらい。このデータをどう集計し、劇団活動に生かすのか。とても気になった。
2008年6月25日
下北沢OFFOFFシアター
PR
作 ごまのはえ
演出 天野天街
出演 藤井びん 阪井香奈美 流山児祥 甲津拓平 小林七緒 ほか
脚本ができあがったのが6月に入ってからという噂もありどうなることかと思っていた。稽古場を覗きにいくと流山児さんがダンスシーンでぶつかったりしていて、大変なのかなあと思いきや、本番を観劇したところとても面白く演劇的な悦びに満ちた作品だった。大雨で増水し浸水を逃れた民家に移り住んだ人々は団地の出身者や市役所の人、生きてる人も死んだ人も入り混じり、幻想と現実が入り混じり。めくるめく万華鏡のような芝居が続く。疾走する芝居であり、火事場の?アンサンブルの勝利である。古めかしく壁紙がはがれた室内は昭和の匂い、ダンスはテクノぽく、愛憎劇はさまざまで、愛情や追慕が中心となり進んで行く。特にリフレインの中で徐々に起きたことが解体されて行く様は記憶の中で過去の出来事が自分なりに変造されていく様を描いているようでもあった。
とにかく見ていて面白い。美術、音楽、照明、役者が一体となって作り上げる芝居だ。4200円というチケット代に躊躇するかもしれないが、大丈夫。見ておくべき芝居はここにある。ああ、面白かった。伊藤弘子のキレ方が、演技のドライブの掛け方が、アングラの歴史を綿々と伝える。小林七緒が素晴らしく、阪井香奈美が面白い。やはり、さとうこうじが絶妙のテクニックで芝居の根幹と流山児さんとのアンサンブルを支える。この前まで出ていた壱組印と同じ俳優かと思うくらい自由自在。ダンスもうまい。ファンになってしまった。今回の最大の収穫は平野直美か。平野が途中で交通整理するところはこの作品の最高潮になっていた感じがする。上田和弘や甲津拓平も相変わらず存在感があり作品にかかせない。

2008年6月13日
下北沢 ザ・スズナリ
演出 天野天街
出演 藤井びん 阪井香奈美 流山児祥 甲津拓平 小林七緒 ほか
脚本ができあがったのが6月に入ってからという噂もありどうなることかと思っていた。稽古場を覗きにいくと流山児さんがダンスシーンでぶつかったりしていて、大変なのかなあと思いきや、本番を観劇したところとても面白く演劇的な悦びに満ちた作品だった。大雨で増水し浸水を逃れた民家に移り住んだ人々は団地の出身者や市役所の人、生きてる人も死んだ人も入り混じり、幻想と現実が入り混じり。めくるめく万華鏡のような芝居が続く。疾走する芝居であり、火事場の?アンサンブルの勝利である。古めかしく壁紙がはがれた室内は昭和の匂い、ダンスはテクノぽく、愛憎劇はさまざまで、愛情や追慕が中心となり進んで行く。特にリフレインの中で徐々に起きたことが解体されて行く様は記憶の中で過去の出来事が自分なりに変造されていく様を描いているようでもあった。
とにかく見ていて面白い。美術、音楽、照明、役者が一体となって作り上げる芝居だ。4200円というチケット代に躊躇するかもしれないが、大丈夫。見ておくべき芝居はここにある。ああ、面白かった。伊藤弘子のキレ方が、演技のドライブの掛け方が、アングラの歴史を綿々と伝える。小林七緒が素晴らしく、阪井香奈美が面白い。やはり、さとうこうじが絶妙のテクニックで芝居の根幹と流山児さんとのアンサンブルを支える。この前まで出ていた壱組印と同じ俳優かと思うくらい自由自在。ダンスもうまい。ファンになってしまった。今回の最大の収穫は平野直美か。平野が途中で交通整理するところはこの作品の最高潮になっていた感じがする。上田和弘や甲津拓平も相変わらず存在感があり作品にかかせない。
2008年6月13日
下北沢 ザ・スズナリ
作 妹尾 夫
演出 伊東四朗 三宅裕司
出演 伊東四朗 ラサール石井 渡辺正行 三宅裕司 戸田恵子 春風亭昇太 小椋久寛 東貴博
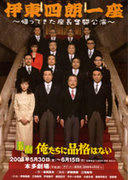
もちろん面白かった。しかし、昨年の伊東さんの舞台「社長放浪記」のようなお芝居というよりはコントとギャグの連続という感じだった。お客さんも笑い待ちをしているし。伊東さんがもっと活躍するのかなと思いきや、割と一座の中のアンサンブル的な存在。僕は「追いつ追われつ」みたいなすり抜けを延々とやるのが好きなんですよね。何でだろう。
今回、従来の古典的な笑いを追求していたのは東さんのような気がする。あの身体を張った自然の笑いはやっていることをひたすら信じてやり続けることから生まれる。きっと孤独なんだろうなあと思う。また、伊東四朗さんの円周率記憶シーンもそれ。古典的な笑いの王道を行くもので見ていて面白い。ちゃんとオチもある。小椋さんの立ち位置も王道なそれで貫禄がある。そういう意味で渡辺正行さんの世界はご自分で確立したそれである。とことん楽しんでやっていることで廻りまで楽しくさせてしまうという勢い笑いである。ラサールさんはそう言う中で縦横無尽に対応。さすが劇作家であり演出家である。見ていてホントに面白かった。というよりも、その技、自由さが怖かった。
2008年6月12日
本多劇場
演出 伊東四朗 三宅裕司
出演 伊東四朗 ラサール石井 渡辺正行 三宅裕司 戸田恵子 春風亭昇太 小椋久寛 東貴博
もちろん面白かった。しかし、昨年の伊東さんの舞台「社長放浪記」のようなお芝居というよりはコントとギャグの連続という感じだった。お客さんも笑い待ちをしているし。伊東さんがもっと活躍するのかなと思いきや、割と一座の中のアンサンブル的な存在。僕は「追いつ追われつ」みたいなすり抜けを延々とやるのが好きなんですよね。何でだろう。
今回、従来の古典的な笑いを追求していたのは東さんのような気がする。あの身体を張った自然の笑いはやっていることをひたすら信じてやり続けることから生まれる。きっと孤独なんだろうなあと思う。また、伊東四朗さんの円周率記憶シーンもそれ。古典的な笑いの王道を行くもので見ていて面白い。ちゃんとオチもある。小椋さんの立ち位置も王道なそれで貫禄がある。そういう意味で渡辺正行さんの世界はご自分で確立したそれである。とことん楽しんでやっていることで廻りまで楽しくさせてしまうという勢い笑いである。ラサールさんはそう言う中で縦横無尽に対応。さすが劇作家であり演出家である。見ていてホントに面白かった。というよりも、その技、自由さが怖かった。
2008年6月12日
本多劇場
作/演出 本多 誠人

芸達者な人たちが見せるお芝居だった。本田さん初め、とにかく皆さん身体のキレがいい!そして全員が独特の間合いと演技法を共有している感じだった。登場人物がひとりひとり同じ希望と、同じ絶望と、同じ再起をしていく。それが、割と定式化されて繰り返される。だから、先が読めてしまうのだが、それが、凡庸と見えるのか、安心感につながるのかは微妙なところなのであります。
また、内容はてんこもりで、ミュージカルシーンが入ったりサービス満点だが、詰め込み過ぎと思う人もいるだろう。そうはいってもペテカンはすでに14年という月日を重ねた。作品の中では、「何とかなるさ!」「ありのままの自分を受け入れる」といったことがキーワードなのだが、劇団としては、もっと多くの人に認められたい、先に行きたいという思いがひしひしと伝わって来た。観客に有無を言わせず納得させたいと、もっともっと!的な内容につながっているのかも。押しまくり引くところが少ない感じがした。役者全員が魅力的だが、羽柴真希を初め女子部3人と斎田さん、濱田さんは特に魅力的だった。僕自身が演劇をしているので、色んな事を感じてしまうのだが、作品として好感のもてる公演であった事は間違いない。何しろものすごく丁寧に稽古も積み重ねて一生懸命に練り上げられた作品だからだ。
2008年6月11日
シアタートップス
芸達者な人たちが見せるお芝居だった。本田さん初め、とにかく皆さん身体のキレがいい!そして全員が独特の間合いと演技法を共有している感じだった。登場人物がひとりひとり同じ希望と、同じ絶望と、同じ再起をしていく。それが、割と定式化されて繰り返される。だから、先が読めてしまうのだが、それが、凡庸と見えるのか、安心感につながるのかは微妙なところなのであります。
また、内容はてんこもりで、ミュージカルシーンが入ったりサービス満点だが、詰め込み過ぎと思う人もいるだろう。そうはいってもペテカンはすでに14年という月日を重ねた。作品の中では、「何とかなるさ!」「ありのままの自分を受け入れる」といったことがキーワードなのだが、劇団としては、もっと多くの人に認められたい、先に行きたいという思いがひしひしと伝わって来た。観客に有無を言わせず納得させたいと、もっともっと!的な内容につながっているのかも。押しまくり引くところが少ない感じがした。役者全員が魅力的だが、羽柴真希を初め女子部3人と斎田さん、濱田さんは特に魅力的だった。僕自身が演劇をしているので、色んな事を感じてしまうのだが、作品として好感のもてる公演であった事は間違いない。何しろものすごく丁寧に稽古も積み重ねて一生懸命に練り上げられた作品だからだ。
2008年6月11日
シアタートップス
アンドリューロイドウエッバー作曲

何回目のキャッツだろう。1980年代にロンドンのニューロンドンシアターで見たのが最初。次はブロードウェイのウィンターガーデンシアター。もちろん、劇団四季のキャッツも見た。でも20年くらい前。おそらく品川で見た。そして、実は昨年、バンコクでロンドンからのカンパニーが来ていたので見た。それがホントに久しぶりで、ああ,面白かったと思ったのだ。
4月に劇団四季のウィキッドを見て、ものすごい力に圧倒されて、まったく新しい四季像をもって、今回約20年ぶりに見た。先ずは20年前と違うところ。身体能力がものすごく上がっていた。軽く踊っている。もう、だれもナンバーが終わったときの決めポーズで息が切れていない。スゴいなと思った。身体も良くなったし見栄えもする。そして、これほどまで日本語の言葉をきちんと伝えてくれて、今までもやもやと20年間も引っ張って来た部分も解消。
でもさ、何かダメなのだ。何かね80点をきちんと取ることを考えてしているようで、全力感がないんです。危なさがないんです。だからドキドキ感がない。役者にドキドキ感がないんです。慎重さはあっても。
根本的な問題は、未だにカラオケで歌っていることじゃないかなあ。あれカラオケだよね?生オケじゃないよね?
芝居って、その日のノリでほんの極僅かなものかもしれないけれど、違ってくるのが当たり前。
役者の呼吸やノリを考えて、オケも微妙に変わったりする。だから指揮者がいる。だから生演奏でやる。金が掛かる。でも、それ、それ、それが大切!!!!
生の人間が機械の出す録音に合わせるのじゃダメだよ。それが問題の根本だと思うんだよなあ。
何か合わせることばかりしているからか、音が大きく外れたひとが二人もいた。それ以上に、何か新鮮な気持ちで役をクリエイトしているのではなく、それよりも、段取りに合わせることに集中しているように思えて仕方がない。ウソの笑顔、ウソのテンポって感じ。もちろん、カラオケのテンポで気持ちが毎日がピタッとあって、いまそこで起きているように再現できればいいのだけれど、できないよ。いや、あれだけ段取りが多ければ無理?先ずは失敗しないように、段取りをはずさないようにと守りの芝居になる。攻めじゃなくなる!
もちろん素晴らしいんですよ。でも、一番重要なハートがね。段取りの次の2番目じゃダメなんです。もちろん稽古で目標とするものがあってそれを基準にしてやっていいんだけれど、オケがこのテンポで出てくるって、万分の1も狂わないって分かっているからそれに対する緊張はゼロじゃないですか?合わせる緊張感だよね。もしも、その日の体調や気持ちで万分の1でも昨日と違っていたら、プロの指揮者は気がついて併せたり、併せようとしたり、そこに緊張感が生まれて生になる。生の演技になる。でもね、録音だとそうではなく、機械、録音、記憶に合わせるしか方法がないんだよね。
僕の隣の親子が1幕の終わりに、ああ、中だるみするなあといって帰っていたのですが、それは、それが原因ではないかなあ。何しろ、メモリーにまでそういう思いを持ってしまったから。
それから、あの発声。前述したように日本語はきちんと届きます。でも、きちんとテキストを伝えることにあまりにも専念していないか?テキストは言葉の情報だけでなく、そこに役者の気持ちを載せて届けることが必要ですよね。そこに個性を感じないんだよね。言葉が聞き取れなくても伝わることってあるんだよ。
それがね。ハートがね。テキストだけでなく、そこに載せる気持ちを伝えようと、どちらかというとそちらの方が大切だという意思が、去年のバンコクでみたイギリスからのツアーカンパニーでもみんなあるんだよね。それが、今宵は感じられなかった。
後半になって、マキャベリティキャッツのナンバーを唄うディミータをやっていたレベッカバレットさんの唄をきいていて、ますます思った。彼女の唄が英語の部分だけリアルになるんです。マキャベティ イズ ノットゼアーっていうだけなんだけど、すげーリアルな言葉になる。彼女だけでなく日本語すべてにそれが言えるんです。ちなみに彼女のダンスにはハートがとてもあって良かったです。
僕にしてみると、必死に声を出したり、滑舌をしっかりしてみたり、演技にメリハリつけたりしても、外国のや20年前の四季のをみた僕からしたら、それをしたらキャッツの肝をはずすことになるということなんです。気持ちね。心。そういう観点からすると、メモリーを唄うグリザベラ、おばさん猫のジェニエニドッツ、役者猫のオールドシュトロノミーが今宵は全滅でした。後半になって、「さっきのティミータと、中国人俳優 金子 信弛さんがやるミストフェリーズがものすごく取り戻してくれた。特にミスとフェリーズはものすごい身体能力をもったダンサーがぎりぎりやってる感が伝わって来てスゴかった。あれです。富田が金メダルの富田がオリンピックで体操の演技をするときの緊張感が伝わってくるんです。
ウィキッドのカンパニーが、スゴくリアルで、ミュージカルにものすごいハートをいれて作品のいちばん伝えたいことを伝えていた。それは、伝えたいところを大きな声で言うわけではもちろんない。リアルな人間関係をリアルな芝居で舞台上でやっているだけのこと。ミュージカルもダンスもそう。それが、今宵の劇団四季キャッツのカンパニーにはあまり感じられなかったのが残念。
しかし、素晴らしい身体能力をもった俳優が山ほど要るなあと思いました。ブロードウェイに挑戦してくれる人が出てくると面白いなとも思いました。身体能力ではもう1歩もひけをとっていないのだから。
五反田キャッツシアター
2008年6月3日
何回目のキャッツだろう。1980年代にロンドンのニューロンドンシアターで見たのが最初。次はブロードウェイのウィンターガーデンシアター。もちろん、劇団四季のキャッツも見た。でも20年くらい前。おそらく品川で見た。そして、実は昨年、バンコクでロンドンからのカンパニーが来ていたので見た。それがホントに久しぶりで、ああ,面白かったと思ったのだ。
4月に劇団四季のウィキッドを見て、ものすごい力に圧倒されて、まったく新しい四季像をもって、今回約20年ぶりに見た。先ずは20年前と違うところ。身体能力がものすごく上がっていた。軽く踊っている。もう、だれもナンバーが終わったときの決めポーズで息が切れていない。スゴいなと思った。身体も良くなったし見栄えもする。そして、これほどまで日本語の言葉をきちんと伝えてくれて、今までもやもやと20年間も引っ張って来た部分も解消。
でもさ、何かダメなのだ。何かね80点をきちんと取ることを考えてしているようで、全力感がないんです。危なさがないんです。だからドキドキ感がない。役者にドキドキ感がないんです。慎重さはあっても。
根本的な問題は、未だにカラオケで歌っていることじゃないかなあ。あれカラオケだよね?生オケじゃないよね?
芝居って、その日のノリでほんの極僅かなものかもしれないけれど、違ってくるのが当たり前。
役者の呼吸やノリを考えて、オケも微妙に変わったりする。だから指揮者がいる。だから生演奏でやる。金が掛かる。でも、それ、それ、それが大切!!!!
生の人間が機械の出す録音に合わせるのじゃダメだよ。それが問題の根本だと思うんだよなあ。
何か合わせることばかりしているからか、音が大きく外れたひとが二人もいた。それ以上に、何か新鮮な気持ちで役をクリエイトしているのではなく、それよりも、段取りに合わせることに集中しているように思えて仕方がない。ウソの笑顔、ウソのテンポって感じ。もちろん、カラオケのテンポで気持ちが毎日がピタッとあって、いまそこで起きているように再現できればいいのだけれど、できないよ。いや、あれだけ段取りが多ければ無理?先ずは失敗しないように、段取りをはずさないようにと守りの芝居になる。攻めじゃなくなる!
もちろん素晴らしいんですよ。でも、一番重要なハートがね。段取りの次の2番目じゃダメなんです。もちろん稽古で目標とするものがあってそれを基準にしてやっていいんだけれど、オケがこのテンポで出てくるって、万分の1も狂わないって分かっているからそれに対する緊張はゼロじゃないですか?合わせる緊張感だよね。もしも、その日の体調や気持ちで万分の1でも昨日と違っていたら、プロの指揮者は気がついて併せたり、併せようとしたり、そこに緊張感が生まれて生になる。生の演技になる。でもね、録音だとそうではなく、機械、録音、記憶に合わせるしか方法がないんだよね。
僕の隣の親子が1幕の終わりに、ああ、中だるみするなあといって帰っていたのですが、それは、それが原因ではないかなあ。何しろ、メモリーにまでそういう思いを持ってしまったから。
それから、あの発声。前述したように日本語はきちんと届きます。でも、きちんとテキストを伝えることにあまりにも専念していないか?テキストは言葉の情報だけでなく、そこに役者の気持ちを載せて届けることが必要ですよね。そこに個性を感じないんだよね。言葉が聞き取れなくても伝わることってあるんだよ。
それがね。ハートがね。テキストだけでなく、そこに載せる気持ちを伝えようと、どちらかというとそちらの方が大切だという意思が、去年のバンコクでみたイギリスからのツアーカンパニーでもみんなあるんだよね。それが、今宵は感じられなかった。
後半になって、マキャベリティキャッツのナンバーを唄うディミータをやっていたレベッカバレットさんの唄をきいていて、ますます思った。彼女の唄が英語の部分だけリアルになるんです。マキャベティ イズ ノットゼアーっていうだけなんだけど、すげーリアルな言葉になる。彼女だけでなく日本語すべてにそれが言えるんです。ちなみに彼女のダンスにはハートがとてもあって良かったです。
僕にしてみると、必死に声を出したり、滑舌をしっかりしてみたり、演技にメリハリつけたりしても、外国のや20年前の四季のをみた僕からしたら、それをしたらキャッツの肝をはずすことになるということなんです。気持ちね。心。そういう観点からすると、メモリーを唄うグリザベラ、おばさん猫のジェニエニドッツ、役者猫のオールドシュトロノミーが今宵は全滅でした。後半になって、「さっきのティミータと、中国人俳優 金子 信弛さんがやるミストフェリーズがものすごく取り戻してくれた。特にミスとフェリーズはものすごい身体能力をもったダンサーがぎりぎりやってる感が伝わって来てスゴかった。あれです。富田が金メダルの富田がオリンピックで体操の演技をするときの緊張感が伝わってくるんです。
ウィキッドのカンパニーが、スゴくリアルで、ミュージカルにものすごいハートをいれて作品のいちばん伝えたいことを伝えていた。それは、伝えたいところを大きな声で言うわけではもちろんない。リアルな人間関係をリアルな芝居で舞台上でやっているだけのこと。ミュージカルもダンスもそう。それが、今宵の劇団四季キャッツのカンパニーにはあまり感じられなかったのが残念。
しかし、素晴らしい身体能力をもった俳優が山ほど要るなあと思いました。ブロードウェイに挑戦してくれる人が出てくると面白いなとも思いました。身体能力ではもう1歩もひけをとっていないのだから。
五反田キャッツシアター
2008年6月3日
指揮 パーヴォヤルヴィ
ブラームス作曲 交響曲1番 交響曲3番
指揮者は威張り腐っていたが大した演奏ではなかった。いま、ヤルヴィという姓をもつ指揮者が3人いる。父親は著名なネーメヤルヴィ。その息子が3人とも活躍しているのだ。エストニア出身でニューヨークで音楽教育を受けた3人兄弟だ。評価も悪くなく今宵のパーヴォは2010年からパリ管弦楽団の音楽監督になるという。欧州の楽壇ではすごく重要なポストだ。
今宵は大ものを二つも一晩に取り上げるという挑戦をしてくれた。確かに、指揮者が作り上げたい世界観は伝わってくる。しかし、オーケストラの楽団員がそれを受け入れていないことも如実に伝わってくる。縁取りは現代的で21世紀のブラームス演奏のひとつの規範を作ろうとしているのは分かる。ピリオド奏法の影響や、全てのパートをクリアに浮かび上がらせる演奏は確かに新しい。しかし、楽団員は、それを単なる仕事としてやっているだけだ。積極的にその世界に浸ろうという空気はない。だから、音楽が死んでいる気がした。
これくらいの演奏なら、楽器の善し悪しはあるが、下手をするとアマチュア交響楽団でも十分できる。それくらいの演奏。もちろん初めてブラームスを生で聴いた人にとっては、ブラームスのサウンドの魅力があったろうが、こちとら、もう山ほどきいたから、そんじゃそこらの演奏じゃ。ね。

2008年6月2日
東京文化会館大ホール
ブラームス作曲 交響曲1番 交響曲3番
指揮者は威張り腐っていたが大した演奏ではなかった。いま、ヤルヴィという姓をもつ指揮者が3人いる。父親は著名なネーメヤルヴィ。その息子が3人とも活躍しているのだ。エストニア出身でニューヨークで音楽教育を受けた3人兄弟だ。評価も悪くなく今宵のパーヴォは2010年からパリ管弦楽団の音楽監督になるという。欧州の楽壇ではすごく重要なポストだ。
今宵は大ものを二つも一晩に取り上げるという挑戦をしてくれた。確かに、指揮者が作り上げたい世界観は伝わってくる。しかし、オーケストラの楽団員がそれを受け入れていないことも如実に伝わってくる。縁取りは現代的で21世紀のブラームス演奏のひとつの規範を作ろうとしているのは分かる。ピリオド奏法の影響や、全てのパートをクリアに浮かび上がらせる演奏は確かに新しい。しかし、楽団員は、それを単なる仕事としてやっているだけだ。積極的にその世界に浸ろうという空気はない。だから、音楽が死んでいる気がした。
これくらいの演奏なら、楽器の善し悪しはあるが、下手をするとアマチュア交響楽団でも十分できる。それくらいの演奏。もちろん初めてブラームスを生で聴いた人にとっては、ブラームスのサウンドの魅力があったろうが、こちとら、もう山ほどきいたから、そんじゃそこらの演奏じゃ。ね。
2008年6月2日
東京文化会館大ホール
モディリアーニ展に行って来た。初めて国立新美術館にも行って来た。その感想。
乃木坂駅ってのは、僕の学生時代には、ホントの遊び人くらいしか用事のない駅だった。乃木大将の家があったり、カフェグレコ本店があったりするくらい。六本木や赤坂で遊んだ人間が作るコミュニティみたいな駅だった。そんな千代田線の駅が一変していた。この美術館は日本で初めて?地下鉄の駅に直結した素晴らしい美術館だった。しかし、東京に公立の美術館をあと幾つ作るのだろう?日本に幾つだ!人はよく道路建設の無駄ばかり言うが、美術館も何とかホールももっと要らない。維持費を考えたら古いものはぶち壊し、民間に売却してしまうべきだと考えている。
まあ、そういうことはおいといて。
やっと世界に誇れる、MOMA級の、ポンピドーセンター級の美術館だなと思った。素晴らしいフォルム。高い天井、広い展示室。カフェなどの充実ぶりも素晴らしい。そして、そこでの企画展示も素晴らしいものだった。どうせ、どこかの大回顧展を買ったのだくらいに思ってみていたら、90%以上が個人所蔵の作品で、一枚一枚丁寧に借り受けて来たのが分かる。中には50年ぶりの展示みたいな作品もあり、そして、モディリアーニの美術像全体が見渡せるようになっていて素晴らしかった。
何か量で押し切る美術展があったりするが、そういうものではなく、きちんとプランされて、見所もあって良かった。
モディリアーニが何に触発されて(アフリカや東南アジアの美術)、あのようなフォルムを書き始め、同時代の美術家の影響を受けまくり、短い35年の人生ではあったが、晩年は、その山ほど受けた影響を一枚一枚はがして行ったら自分が残っていた。画家と画家が対した被写体が浮き上がり、人間に対する深い洞察がそこにあったのだ。
ある絵では、その鼻筋に、うなじに、瞳に、画家の興味の中心があることが明確で、じっくり見ていると、キャンバスの向こうに被写体が見えてくるようだ。そして、ここに100年もしない前にモディリアーニ本人が立って僕が今見ている被写体とは何だろう。何でこの人物は自分を惹き付けるのだろうと思い描く状況だったのだろうなあと思ってみたのだ。
女性像では自信満々のジャンヌエピテルヌ、無垢な少女のユゲットだったり、僕の大好きなスーティンが描かれていたりして、それは、まだ売れていない頃のスーティンでいらだちが出ていたり、モディリアーニの画商には照れ笑いも見られたりして。
大変面白かった。外国人も多く観に来ていたのだが、これだけ素晴らしい展覧会は、世界の美術館でもそう多くが出来るものではないのだから、当たり前だと思った。ただ、日本で美術を見る時に僕が困るのは、来ている他の鑑賞者の日本語がわかってしまうことである。フランスやイタリアでは分からないからとても助かる。
今回も、ああ、この人と不倫してたんだとか、この絵のここを見てご覧よという素人美術評論家とか山ほどいた。それが、ヤケにうるさいのだ。
僕に言わせれば、もっと絵と自分ひとりで向き合って欲しいということだ。
おしゃべりをして、きれいな絵を眺めているだけなの?この素晴らしい美術をデートに使っているだけ?
美術は美術と鑑賞者が対峙しなくてはつまらないと思うのだ。決して恋人との仲を深める起爆剤でも、友情深める接着剤でもない。そういう媒介にするだけだったら自宅で画集を開いて好き勝手やれば!と言いたいのだ。
何々展を見たよというような、有名美術の巡礼者でもないだろう?そんなスタンプを幾つ集めても美術の真髄には近づけないことを知って欲しい。
ああ、別に近づきたくないんだ。そうだ。近づけたいのは恋人との距離なのだから。
2008年5月4日
モディリアーニ展の公式ホームページ
http://modi2008.jp/
スッペ作曲「ボッカチオ」
演出 ヘルムートローナー
指揮 アンドレアスシュラー
独唱 アンティゴネパポウルカス、マルティナドラーク
がっかりした。これだからクラシック音楽はつまらないと言われる。イタリアの艶笑話。いろんな女とどうやってセックスするか、妻は妻で退屈な旦那の目を盗んでどうやるかというエロ話が全てのストーリー、主要なエロ話の登場人物の誰からも性欲の絶対性を感じさせる空気も演技もみられない。ボッカチオ役のズボン役以外は声も酷い。あれなら日本の音大出身者で幾らでも唄える人がいる。また合唱陣もただ突っ立っていたり、ただぐるぐる回ったりでキチンと演技が出来ている人がいない。寝取られる3人組の方がコミカルな演技ができていて魅力的。これじゃ喜歌劇の「劇」部分が成立しないではないか。しかし、こちらも唄で3人があわせるところや言葉が細かく音符で刻まれるところなど技術的な問題多数あり。それでも、まだこちらの方が…。
美術プランもあったもんではない。唯一オーケストラが頑張っていたのが救い。
エノケンが唄った浅草オペラの名曲がちりばめられた名曲で、珍しい作品なので大枚S席(36000円)で見たのだが、エノケンの唄の方が本場の彼らより数段良かった。
あと、台詞部分だけドイツ語でやるのは勘弁して欲しい。
2008年5月31日
東京文化会館大ホール
フロトー作曲「マルタ」
指揮 アンドレアス・シュラー
演出 マイケルマッカフェリー
出演 ヘルベルトリッペルト ほか
フォルクスオパーの面目躍起の公演だった。会場は沸き立ち、単純明快なストーリーにしっとり系とアップテンポな曲、高音を聞かせたり、唄のハーモニーを楽しめるもの、合唱など、さまざまな手法を手を替え品を替えだしてくる手法に観客は飽きるわけもない。それも、庭の千草などいい名曲も入っている。それほど大きな予算を組んでいるわけではないだろうが、場面転換もそこそこあり、衣装や振付け、コーラス、群衆処理などもきちんとされていた。歌手も欧米のオペラハウスのトップクラスとは言わないがこの曲を楽しく聞くには充分の実力者。そして重要な演技力もあって合格点。
そして、何よりもオーケストラがこの作品を熟知しきちんと楽しませる演奏をしてくれたことが成功の要因だった。休憩中に中年の女性が「わたし、こういう単純な話大好き!」と言っていたことが印象的だった。いや、楽しかったです。◎
2008年6月8日
東京文化会館大ホール
作 平田オリザ
演出 成井市郎
出演 坂口芳貞 加藤武 川辺久造 新橋耐子 ほか
とても面白かった。演劇をみる楽しさを味わうことができた。感謝。平田オリザさんの作品の中でももっとも見やすい作品の一つだと思う。時間があっという間に過ぎて行く。文学座のように名うての役者が多くいて、年齢層も広いところに書く平田さん。いつもと同じように、家族やコミュニティの問題。人と人とのことを丁寧に描いている。それを描く背景に選んだのが東京におきた大震災の復興途中というもの。そして、人と人との関係の中からこそ、さまざまな社会や地域や世代の問題が噴出する。
演技に関しても、この大御所揃いの座組の演技に、僕がコメントすることはなにもない。素晴らしい。スゴいのは年齢が上の方のお芝居。上手いのか、味があるのか。それは、盆踊りみたいなシーンがちょこっとあるのだが、そこに象徴的にでていた。大御所は身体のキレは若者に劣るのだろうが、ホントに踊っているし、無駄な動きがない。ところが、若い人には時折、振りつけられた痕跡が少し見え隠れする。ここでこんな踊りするのに、そんな腰を折り曲げて踊るかよ?みたいな突っ込みを入れたくなった。でも、それも大御所と一緒だから目立ったんだと思う。いや、もちろん素晴らしいんです、若手も。
上手い演技から味のある演技、好かれる演技へとつなぐのに必要なものが見えたような気がした。
いづれにせよ、文学座は大成功したこの作品を再演すると思う。いやして頂きたい。
最後に。この上演の成功はこの一回の公演で生まれたわけではない。文学座と青年団のこの数年間の綿密な交流から生まれたものだ。毎年何本も協業して小さな劇場で上演を重ねて来た。混じり合い影響を与えながら積み重ねたものなのだ。丁寧に演劇を作ることの大切さを思い知らされたのである。

2008年6月1日
紀伊国屋サザンシアター
演出 成井市郎
出演 坂口芳貞 加藤武 川辺久造 新橋耐子 ほか
とても面白かった。演劇をみる楽しさを味わうことができた。感謝。平田オリザさんの作品の中でももっとも見やすい作品の一つだと思う。時間があっという間に過ぎて行く。文学座のように名うての役者が多くいて、年齢層も広いところに書く平田さん。いつもと同じように、家族やコミュニティの問題。人と人とのことを丁寧に描いている。それを描く背景に選んだのが東京におきた大震災の復興途中というもの。そして、人と人との関係の中からこそ、さまざまな社会や地域や世代の問題が噴出する。
演技に関しても、この大御所揃いの座組の演技に、僕がコメントすることはなにもない。素晴らしい。スゴいのは年齢が上の方のお芝居。上手いのか、味があるのか。それは、盆踊りみたいなシーンがちょこっとあるのだが、そこに象徴的にでていた。大御所は身体のキレは若者に劣るのだろうが、ホントに踊っているし、無駄な動きがない。ところが、若い人には時折、振りつけられた痕跡が少し見え隠れする。ここでこんな踊りするのに、そんな腰を折り曲げて踊るかよ?みたいな突っ込みを入れたくなった。でも、それも大御所と一緒だから目立ったんだと思う。いや、もちろん素晴らしいんです、若手も。
上手い演技から味のある演技、好かれる演技へとつなぐのに必要なものが見えたような気がした。
いづれにせよ、文学座は大成功したこの作品を再演すると思う。いやして頂きたい。
最後に。この上演の成功はこの一回の公演で生まれたわけではない。文学座と青年団のこの数年間の綿密な交流から生まれたものだ。毎年何本も協業して小さな劇場で上演を重ねて来た。混じり合い影響を与えながら積み重ねたものなのだ。丁寧に演劇を作ることの大切さを思い知らされたのである。
2008年6月1日
紀伊国屋サザンシアター
最新記事
(01/06)
(12/25)
(08/05)
(06/30)
(12/16)
(08/21)
(04/10)
(09/25)
(11/30)
(11/18)
(11/03)
(10/04)
(09/19)
(08/28)
(06/25)
(06/10)
(12/30)
(02/21)
(12/31)
(09/28)
(06/09)
(05/12)
(12/31)
(09/08)
(06/02)
プロフィール
HN:
佐藤治彦 Haruhiko SATO
HP:
性別:
男性
職業:
演劇ユニット経済とH 主宰
趣味:
海外旅行
自己紹介:
演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員
カテゴリー
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
フリーエリア
最新CM
[08/24 おばりーな]
[02/18 清水 悟]
[02/12 清水 悟]
[10/17 栗原 久美]
[10/16 うさきち]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(12/05)
(12/07)
(12/08)
(12/09)
(12/10)
(12/11)
(12/29)
(01/03)
(01/10)
(01/30)
(02/13)
(03/09)
(03/12)
(03/16)
(03/17)
(03/19)
(03/20)
(03/20)
(03/22)
(03/22)
(03/23)
(03/24)
(03/28)
(04/01)
(04/01)
カウンター
