自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
プルーフオブライフ PROOF OF LIFE ラッセルクロウ、メグライアン主演。南米でゲリラに身代金目的に誘拐された男を救出するための人質交渉人の活躍。娯楽作を得意とするテイラーハックフォード監督作だけに、深みよりも面白さ優先。75点 2011年8月21日
マーシャル・ロー -The Siege-テロ続発でNYに戒厳令が施行される話。9・11前の映画と思うと恐ろしい。一時期、日本で上映自粛された問題作だけに知名度は低いが社会派ミステリーの傑作だ。90点 同時多発テロ10周年前に必見。
2011年8月20日
M:i:III 正直いってトムクルーズ自体は旬の終わった俳優だしプロデューサーも兼ね、全編出過ぎだが、再見したらとても良くできた娯楽作品だった。まあ、1作目には適わないけど。ローマ(ガゼルダ)や上海(?)などのロケ映像も楽しい。65点
2011年8月20日
黒澤明「まあだだよ」。公開当時の期待感もなく観るとなかなか面白い。当時は老いた感じがしたものだが、こんなさらっとした話なのに画面から東宝のダイナミズムを感じる(大映映画だが)。で。この作品を小津が撮ったらどうなるのかなと思うのです。ダイナミズムと言ったけれども、俳優の芝居が何か余計にでかい。っていうか黒澤映画。2011年9月6日
マーシャル・ロー -The Siege-テロ続発でNYに戒厳令が施行される話。9・11前の映画と思うと恐ろしい。一時期、日本で上映自粛された問題作だけに知名度は低いが社会派ミステリーの傑作だ。90点 同時多発テロ10周年前に必見。
2011年8月20日
M:i:III 正直いってトムクルーズ自体は旬の終わった俳優だしプロデューサーも兼ね、全編出過ぎだが、再見したらとても良くできた娯楽作品だった。まあ、1作目には適わないけど。ローマ(ガゼルダ)や上海(?)などのロケ映像も楽しい。65点
2011年8月20日
黒澤明「まあだだよ」。公開当時の期待感もなく観るとなかなか面白い。当時は老いた感じがしたものだが、こんなさらっとした話なのに画面から東宝のダイナミズムを感じる(大映映画だが)。で。この作品を小津が撮ったらどうなるのかなと思うのです。ダイナミズムと言ったけれども、俳優の芝居が何か余計にでかい。っていうか黒澤映画。2011年9月6日
ブロードウェイミュージカル「コーラスライン」
「急げばいいってもんじゃない」
世界各地で旧作ミュージカルの再演が行われている。このコーラスラインも21世紀になって再演された。それをブロードウェイで観たのだが、これはそのバージョンなのかな?台詞などを大幅にカットし、上演時間を休憩なしの2時間に収めた超スピードバージョン。まあ、劇中の歌曲やダンスナンバーを早送りで観ているような感じでね。ダメですね。じっくりと築き上げて来たドラマが崩れてしまっている。前回の来日バージョンが素晴らしかっただけにがっかりしました。
@赤坂ACTシアター 2011年8月5日
東京オレンジ2011「Vision Quest」構成・演出 横山仁一
横山さんのやるこの作品は芝居が生ものである事を再認識させられる。そして、作りものでないものの面白さを認識させてくれるのだ。会場は沸きに沸き、役者は活き活きと板の上に立つ。そこは虚構の世界なのだが、一切の嘘がないように思える。
@駅前劇場 2011年8月6日ソワレ
ブルドッキングヘッドロック「毒と微笑み」
作演出・喜安浩平
数年ぶりに観たのだが、喜安さんの作品や手法は、ケラさんに大きく影響され、その影響はもはや溢れ出てしまっているような気がした。僕はキヤスワールドが好きなのだ。ケラさんも好きだけど。達者な俳優達が多くいてもちろん飽きる事はない。
@中野ザポケット 2011年8月8日
子どもに見せたい舞台
「青い鳥」作演出・倉迫康史
倉迫さんのやってるこのシリーズは大好評で公的な支援も得ている。アーチストの創造に税金を投入する事に僕は反対だ。税制上のバックアップはあるべきだが、税金を投入する事は変だなと思うのだ。まあ、自分がもらっていないからかもしれないけれど。しかし、この作品は税金を投入することを容認できる数少ない作品のひとつだ。うちに出た佐藤円などは、数倍もうまく魅力を引き出されていた。
@西すがも創造舍 2011年8月22日
DULL-COLORED POP 「Caesiumberry Jam」
作演出・谷賢一
チェルノブイリ原発事故に触発されて作られた作品。未見の谷賢一の代表作というので拝見。
@池袋シアターグリーン BOX in BOX 2011年8月22日
「奥様お尻をどうぞ」
作演出/ケラリーノサンドロヴィッチ
こんなにバカバカしい作品なのに、今の世の中の空気をきちんと背負って素晴らしい俳優達の見事な演技を観る事ができて嬉しかった事よ。鑑賞当日のツイッターで公述べた。「奥様お尻をどうぞ」神々しいまでの笑いと毒の異次元空間に浸る幸せ。それもリアルに3D。このまま世の中に放出されずに、この羊水に浸っていたい。連れて行った若い役者二人が、面白すぎて凹みますと言っていたが、私は頭がおかしくなりそうです。
@本多劇場 2011年8月24日
ハリーポッターと死の至宝 パート2
ハリーポッターシリーズを見始めたのは10年前で、当時の印象はストーリー展開が早すぎて話が深みがないとか言っていたと思う。それが今や病み付きである。現代人の持つ(それは多分に現代だけではないのだが)人としての複雑な人生に関するさまざまな問いを含有した深みのあるストーリー。それを究極の映像美とファンタジーの世界に織込んだ名作である。そして、演技陣はイギリス演劇界のトップクラスが惜しげもなく投入されている。これからも何度も観るであろう名作の最終章である。
2011年7月17日 渋谷TOHOシネマ 3D
2011年7月29日 バンコク サイアムパラゴン アイマックスシアター
ハリーポッターシリーズを見始めたのは10年前で、当時の印象はストーリー展開が早すぎて話が深みがないとか言っていたと思う。それが今や病み付きである。現代人の持つ(それは多分に現代だけではないのだが)人としての複雑な人生に関するさまざまな問いを含有した深みのあるストーリー。それを究極の映像美とファンタジーの世界に織込んだ名作である。そして、演技陣はイギリス演劇界のトップクラスが惜しげもなく投入されている。これからも何度も観るであろう名作の最終章である。
2011年7月17日 渋谷TOHOシネマ 3D
2011年7月29日 バンコク サイアムパラゴン アイマックスシアター
謎のキューピー 旗揚げ公演
「白いゲルニカ」作演出;謎のキューピー

独特の空気感を劇場に充満させていた。役者に力量の差もあった。立川志らく師匠がゲスト出演、ゴンゾーさんが友情出演。二人のシーンが、物語の本筋とは違うのだが、その独特の世界に混じるとこれまた不思議。80分の上演時間。中野あくとれ 2011年7月8日
双数姉妹「サヨナラ」作演出/小池竹見

明星真由美という劇団を辞めて稼げるようになったスターを招いての公演。小池さんは絶対に新しいものを、人とは違うものをやるという強い意志があって、その原理至上主義になっているように思える。しかし、それは申し訳ないが、ほぼ似たような事をどこかでやっている。正直観るのが痛かった。2011年7月16日@赤坂REDシアター
3.14ch「葉山」作演出・ムランティンタランティーノ

現代口語の何も起こらない芝居かなと思っていたらそうでもない。演劇的な世界がちゃんと用意されていた。先ずは可愛い女子が山ほど出て来た。正直、舞台美術がちょっと雑な感じがしたし、雨の振らせ方とかにアレレ感があった。こういう芝居をふらりと観に行って出会うと嬉しいのかも。2011年7月23日@ワーサルシアター
阿佐ヶ谷スパイダース「荒野に立つ」
作演出・長塚圭史

こんだけすごい俳優を集めて何をやるか?と思ったら、長塚圭史はやはり留学の前後にいろんな作家に影響されて、引き裂かれてしまったような気がして成らない。才能のある人だからいつかは着地点を見つけるだろうが、例えば不条理劇の要素を考えると、先日観た別役実の新作の方が、瑞々しく貫き感を感じるのだ。役者の魅力で今は客はついてきているけれども、いったいどのようになっていくのだろうか?
2011年7月25日@シアタートラム
犬と串「愛・王子博」作演出・モラル

作品のテーマに始まって、美術、音楽、衣装に至るまで入念に準備された若々しくも若々しくない作品。王道のテーマは、現在の閉塞感が漂う時代の空気をきちんと受け止めていて、震災を舞台にしても、その設定を利用しているだけで、何も震災の本質と向かっていない他の多くの作品と根本的に違うものがあった。
2011年7月27日@王子小劇場
「白いゲルニカ」作演出;謎のキューピー
独特の空気感を劇場に充満させていた。役者に力量の差もあった。立川志らく師匠がゲスト出演、ゴンゾーさんが友情出演。二人のシーンが、物語の本筋とは違うのだが、その独特の世界に混じるとこれまた不思議。80分の上演時間。中野あくとれ 2011年7月8日
双数姉妹「サヨナラ」作演出/小池竹見
明星真由美という劇団を辞めて稼げるようになったスターを招いての公演。小池さんは絶対に新しいものを、人とは違うものをやるという強い意志があって、その原理至上主義になっているように思える。しかし、それは申し訳ないが、ほぼ似たような事をどこかでやっている。正直観るのが痛かった。2011年7月16日@赤坂REDシアター
3.14ch「葉山」作演出・ムランティンタランティーノ
現代口語の何も起こらない芝居かなと思っていたらそうでもない。演劇的な世界がちゃんと用意されていた。先ずは可愛い女子が山ほど出て来た。正直、舞台美術がちょっと雑な感じがしたし、雨の振らせ方とかにアレレ感があった。こういう芝居をふらりと観に行って出会うと嬉しいのかも。2011年7月23日@ワーサルシアター
阿佐ヶ谷スパイダース「荒野に立つ」
作演出・長塚圭史
こんだけすごい俳優を集めて何をやるか?と思ったら、長塚圭史はやはり留学の前後にいろんな作家に影響されて、引き裂かれてしまったような気がして成らない。才能のある人だからいつかは着地点を見つけるだろうが、例えば不条理劇の要素を考えると、先日観た別役実の新作の方が、瑞々しく貫き感を感じるのだ。役者の魅力で今は客はついてきているけれども、いったいどのようになっていくのだろうか?
2011年7月25日@シアタートラム
犬と串「愛・王子博」作演出・モラル
作品のテーマに始まって、美術、音楽、衣装に至るまで入念に準備された若々しくも若々しくない作品。王道のテーマは、現在の閉塞感が漂う時代の空気をきちんと受け止めていて、震災を舞台にしても、その設定を利用しているだけで、何も震災の本質と向かっていない他の多くの作品と根本的に違うものがあった。
2011年7月27日@王子小劇場
ジュリエット/リアン・ベンジャミン<英国ロイヤルバレエ>
ロメオ/セザール・モラレス<英国バーミンガム・ロイヤルバレエ>
マキューシオ/八幡顕光 ティボルト/輪島拓也 ベンヴォーリオ/菅野英男
振付 : K.マクミラン 音楽 : S.プロコフィエフ 監修 : D.マクミラン
舞台美術・衣裳 : P.アンドリュース 指揮 : 大井 剛史 管弦楽 : 東京フィルハーモニー交響楽団


「日本のバレエ団が克服しなくてはいけないこと」
プロコフィエフの音楽は昔から好きだった。生の舞台をみたのは5年以上前のこと、ロンドンのロイヤルバレエの公演だった。音楽をきいたのはもう20年以上前、ロンドン交響楽団の来日公演、マイケルティルソントーマスの指揮だったと記憶している。そして、今回はマクラミンの振付け、2人の主役もロイヤルバレエ団とバーミンガムロイヤルバレエ団と本当に英国づくしだなあと思いつつ鑑賞。
多くの振付け演出作品を見ている訳ではないので、感想ということで書かせてもらうが、マクラミンの振付けはバレエの華麗なテクニックを前面に出すのではなく、このロメオとジュリエットという作品をバレエで表現した時の内面の表現をとても重視した作品に思えた。つまりテクニックが不要とは言わないが、演技力がとても必要とっされているのだ。二人の主役は見事である。リアンベンジャミンは若く純真な14歳の少女の一途の恋心を見事に演じていた。可愛いのだ。セザールモラレルは先日みたバーミンガムロイヤルバレエ団の来日の時とは違って今度は若い青年の思いをうまく表現していた。純粋でそれだけ狂気に近い生き方なのである。技術もあるのだろうけれども、それが前面に出て来ない。対する新国立劇場バレエ団もソリストは十分に対抗していた。例えば、一幕で相手をからかうように踊る男性は誰か分からないのだけれどもテクニックにユーモアもある。例えば2幕の第3場、街の広場で起きる悲劇。ティボルトがさされ、マキューシオも死すシーンでは、ティボルトの福田圭吾は、死ぬ悲壮感がなく体操のような動きだった。一方でティボルト役の輪島拓也は、悔しさや生への渇望を残しつつ死ぬところが見事。それを嘆くキャピレット夫人(?)の湯川麻美子も見事だった。
3人の娼婦を踊った寺田亜沙子ほかの3人もダイナミズムがあった。問題はコールドバレエや演技力の必要とされる役だと思う。例えば、ロレンス神父の石井四郎は、堂々とした若い二人が命を託す神父には全く見えない。乾物屋の親父くらいにしか見えないのだ。ヴェローナ大公の内藤博も街の権力者として一生懸命手を広げたり演じるのだが、威厳が全くない。まあ、若い人が演じなくてはならない悲劇と言えば悲劇なのだけれど、それだけか。キャピュレット卿を踊った森田健太郎は以前は主役級を踊っていた人だが、今回は踊りよりも演技力の必要とされる役。他の人よりは重心も低く上手く演じているが、きっと世界のトップのカンパニーに入るとヘンテコになってしまうだろう。
これは、先日観た東京バレエ団の「白鳥の湖」でも感じたことなのだが、バレエの舞台にもっと40代50代の威厳とか重みのある人が立つようにならないと、せっかくのドラマが盛り上がらないと思う。これは日本のバレエ界の大きな欠点だ。
一方で東京バレエ団が克服したのに対して、新国立劇場バレエ団に残された大きな課題はコールドバレエの水準だと思う。先ずは揃わない。音楽をきちんと聞いているのかと思うくらいに揃わない。これは、カウントで踊る人の悲劇だ。カウントはもちろん大切だが、音楽が身に滲みるほど入っていなくてはならない。何百回も音楽を聴かなくてはいけない。きっとそれをしていない。
それから、優雅さやエレガンスな身体の動きがない。型をなぞっているけれども、それが動きだけであって、内面から溢れた動きになっていない。これは東京バレエ団ではないことである。今宵のコールドの水準は20年以上前の日本のバレエ団の水準から進歩していないと感じさせた。
バレエの世界はヨーロッパの世界であり、日本の通常の世界ではあり得ない心や動きが多くある。これを克服する為には欧米での経験が多く必要だと思うのだけれども、そうはいっても無理で、現実には、欧米のバレエ団の公演をどれだけ観たかで決まってしまうのだと思う。東京バレエ団は、世界の超一流のバレエ団を招聘するNBSが積極的にバレエ団の団員に観る機会を与えているし、世界の一級の踊り手と共演することも、毎年のように何ヶ月も欧米での公演を重ねて、欧米の経験、欧米の観客の批評を得てきている。だからか、東京バレエ団のコールドは見事である。
来年2012年のパリオペラ座のプログラムを見ていたら、来年もパリで6公演を行うようである。きっとまた、ベジャールの作品を持って行くのだろうが、そろそろ欧米の作品を向こうで披露してもいいレベルになっている。東京バレエ団が「ジゼル」や「白鳥の湖」などでどのような評価を得るのか聞きたいものだ。新国立劇場バレエ団はそういう機会がないのが可哀想でならない。優雅さや心からの演技は指導で身に付く物ではない。心から自発的に出て来ないとダメなのだ。
日本のバレエの踊り手、特に新国立劇場の踊り手は身銭を払って、もっと世界の一流のバレエを観るべきだ。日本のバレエの会場には、この人はバレエはやってないだろうという人ばかりで(自分も含めて)埋め尽くされている。しかし、本当に観なくてはいけないのは、このバレエ団の人達だ。何とか観て欲しい。山ほど!山ほどだ!
それがないと、日本のバレエは東京バレエ団ばかりが先にいって他はおいていかれるだろう。
最後に、今宵の東京フィルハーモニー管弦楽団の演奏は見事の一言だった。控えめながら曲の急所を決めて行き、微妙に緩急をつけた音楽の流れも、弦のピッチも、とにかくオケが自信に満ちあふれ良くなっていた。歌っていた。
たとえ舞台が散々だったとしてもオーケストラの演奏をきいているだけで十分満足できる演奏だった。指揮者は全く知らない人なので、休憩中にプログラムを見せてもらったら、大井剛史という1974年生まれの若手で、未だにアマチュアオケも振る人らしい。注目して行きたい。
2011年7月1日 新国立劇場オペラバレス
ロメオ/セザール・モラレス<英国バーミンガム・ロイヤルバレエ>
マキューシオ/八幡顕光 ティボルト/輪島拓也 ベンヴォーリオ/菅野英男
振付 : K.マクミラン 音楽 : S.プロコフィエフ 監修 : D.マクミラン
舞台美術・衣裳 : P.アンドリュース 指揮 : 大井 剛史 管弦楽 : 東京フィルハーモニー交響楽団
「日本のバレエ団が克服しなくてはいけないこと」
プロコフィエフの音楽は昔から好きだった。生の舞台をみたのは5年以上前のこと、ロンドンのロイヤルバレエの公演だった。音楽をきいたのはもう20年以上前、ロンドン交響楽団の来日公演、マイケルティルソントーマスの指揮だったと記憶している。そして、今回はマクラミンの振付け、2人の主役もロイヤルバレエ団とバーミンガムロイヤルバレエ団と本当に英国づくしだなあと思いつつ鑑賞。
多くの振付け演出作品を見ている訳ではないので、感想ということで書かせてもらうが、マクラミンの振付けはバレエの華麗なテクニックを前面に出すのではなく、このロメオとジュリエットという作品をバレエで表現した時の内面の表現をとても重視した作品に思えた。つまりテクニックが不要とは言わないが、演技力がとても必要とっされているのだ。二人の主役は見事である。リアンベンジャミンは若く純真な14歳の少女の一途の恋心を見事に演じていた。可愛いのだ。セザールモラレルは先日みたバーミンガムロイヤルバレエ団の来日の時とは違って今度は若い青年の思いをうまく表現していた。純粋でそれだけ狂気に近い生き方なのである。技術もあるのだろうけれども、それが前面に出て来ない。対する新国立劇場バレエ団もソリストは十分に対抗していた。例えば、一幕で相手をからかうように踊る男性は誰か分からないのだけれどもテクニックにユーモアもある。例えば2幕の第3場、街の広場で起きる悲劇。ティボルトがさされ、マキューシオも死すシーンでは、ティボルトの福田圭吾は、死ぬ悲壮感がなく体操のような動きだった。一方でティボルト役の輪島拓也は、悔しさや生への渇望を残しつつ死ぬところが見事。それを嘆くキャピレット夫人(?)の湯川麻美子も見事だった。
3人の娼婦を踊った寺田亜沙子ほかの3人もダイナミズムがあった。問題はコールドバレエや演技力の必要とされる役だと思う。例えば、ロレンス神父の石井四郎は、堂々とした若い二人が命を託す神父には全く見えない。乾物屋の親父くらいにしか見えないのだ。ヴェローナ大公の内藤博も街の権力者として一生懸命手を広げたり演じるのだが、威厳が全くない。まあ、若い人が演じなくてはならない悲劇と言えば悲劇なのだけれど、それだけか。キャピュレット卿を踊った森田健太郎は以前は主役級を踊っていた人だが、今回は踊りよりも演技力の必要とされる役。他の人よりは重心も低く上手く演じているが、きっと世界のトップのカンパニーに入るとヘンテコになってしまうだろう。
これは、先日観た東京バレエ団の「白鳥の湖」でも感じたことなのだが、バレエの舞台にもっと40代50代の威厳とか重みのある人が立つようにならないと、せっかくのドラマが盛り上がらないと思う。これは日本のバレエ界の大きな欠点だ。
一方で東京バレエ団が克服したのに対して、新国立劇場バレエ団に残された大きな課題はコールドバレエの水準だと思う。先ずは揃わない。音楽をきちんと聞いているのかと思うくらいに揃わない。これは、カウントで踊る人の悲劇だ。カウントはもちろん大切だが、音楽が身に滲みるほど入っていなくてはならない。何百回も音楽を聴かなくてはいけない。きっとそれをしていない。
それから、優雅さやエレガンスな身体の動きがない。型をなぞっているけれども、それが動きだけであって、内面から溢れた動きになっていない。これは東京バレエ団ではないことである。今宵のコールドの水準は20年以上前の日本のバレエ団の水準から進歩していないと感じさせた。
バレエの世界はヨーロッパの世界であり、日本の通常の世界ではあり得ない心や動きが多くある。これを克服する為には欧米での経験が多く必要だと思うのだけれども、そうはいっても無理で、現実には、欧米のバレエ団の公演をどれだけ観たかで決まってしまうのだと思う。東京バレエ団は、世界の超一流のバレエ団を招聘するNBSが積極的にバレエ団の団員に観る機会を与えているし、世界の一級の踊り手と共演することも、毎年のように何ヶ月も欧米での公演を重ねて、欧米の経験、欧米の観客の批評を得てきている。だからか、東京バレエ団のコールドは見事である。
来年2012年のパリオペラ座のプログラムを見ていたら、来年もパリで6公演を行うようである。きっとまた、ベジャールの作品を持って行くのだろうが、そろそろ欧米の作品を向こうで披露してもいいレベルになっている。東京バレエ団が「ジゼル」や「白鳥の湖」などでどのような評価を得るのか聞きたいものだ。新国立劇場バレエ団はそういう機会がないのが可哀想でならない。優雅さや心からの演技は指導で身に付く物ではない。心から自発的に出て来ないとダメなのだ。
日本のバレエの踊り手、特に新国立劇場の踊り手は身銭を払って、もっと世界の一流のバレエを観るべきだ。日本のバレエの会場には、この人はバレエはやってないだろうという人ばかりで(自分も含めて)埋め尽くされている。しかし、本当に観なくてはいけないのは、このバレエ団の人達だ。何とか観て欲しい。山ほど!山ほどだ!
それがないと、日本のバレエは東京バレエ団ばかりが先にいって他はおいていかれるだろう。
最後に、今宵の東京フィルハーモニー管弦楽団の演奏は見事の一言だった。控えめながら曲の急所を決めて行き、微妙に緩急をつけた音楽の流れも、弦のピッチも、とにかくオケが自信に満ちあふれ良くなっていた。歌っていた。
たとえ舞台が散々だったとしてもオーケストラの演奏をきいているだけで十分満足できる演奏だった。指揮者は全く知らない人なので、休憩中にプログラムを見せてもらったら、大井剛史という1974年生まれの若手で、未だにアマチュアオケも振る人らしい。注目して行きたい。
2011年7月1日 新国立劇場オペラバレス
ヴェルディ作曲「オテロ」

Marco Armiliato/Conductor Andrei Serban/Stage director Peter Pabst/Sets
Aleksandrs Antonenko/Otello、Sergei Murzaev/Jago、Michael Fabiano/Cassio
Francisco Almanza/Roderigo、Renée Fleming / Desdemona、Nona Javakhidze/Emilia Paris Opera Orchestra and Chorus


パリオペラ座は先年来日し「トリスタンとイゾルテ」「青ひげ公の城」「」を上演した。非常にモダンな演出であった。パリオペラ座バレエは、現代のバレエと古典の名作をバランス良く日本に持ってきてくれるが、パリのオペラ座は来日自体がまだ1回だけなのである。何年に一度はパリにいく機会があり、バレエは「白鳥の湖」と「バヤデール」「ベジャールの夕べ」と観た事があったが、オペラは「マハガニー市の興亡」というクルトワイルの渋いオペラを観ただけだった。で、今回パリに行って1日だけオペラを観ることのできる日があってガルニエで古典的な「コシファントゥッテ」、そして、バスチーユでモダンな「オテロ」をやっていた。チケットがとれる方で観ようと思ってボックスオフィスに行ったら、どっちも最高席でとれるのである。迷ったあげく、ルネフレミングが歌うというので、「オテロ」となった。
来日時に観た「トリスタンとイゾルデ」と同じように、舞台上にイメージ映像を重ねて行く。例えば、今回は冒頭の嵐のシーンで、波の映像だったりするわけで、正直うるさい。それだけでなく、稲妻や嵐の効果音まで入れるのだ。うるさい。
ということで映像はうるさいのだが、舞台セットは簡素なもので、観客としては音楽と歌手の演技に集中できるものだったからいいのだろう。しかし、モダンな演出になったかと思えば、非常に古典的なものが入ってきたり、京劇の影響が出ていたりとバラエティ豊かというか、バラバラな感じなのである。衣装のことはあまりよく分からないが、こちらもモダンだったり、原作に忠実な感じだったり、時代や場所が少しずれるようなものも混ざっているように思えた。
作品の普遍性を出したいのかなあと思ったくらいに、何かね。
しかし、音楽はゴージャスそのものだった。イヤーゴを歌ったムラレフは演技も見事で堂々としたもの。最後はみんな死んでイヤーゴだけ生き残るという演出でありましたけど、この悪役ぶりじゃ生き残るねという感じだ。ロシアの歌手に悪役やらせたら本当にいいなあ。オテロのアントネコは徐々に調子をあげたが、未熟で嫉妬に走ってしまうという子供っぽい部分ばかりが見えていた。ルネフレミングはきっとキャリアの終わりに近いだろうが、長く歌う事もないからだろう。柳の歌を頂点に非常にコントロールされた、しかし女性らしい見事な声を聞かせてくれた。
合唱もよかったが、オーケストラの音がゴージャスだった。ヴェルディでもシェークスピア原作の作品として重厚な音をだした、ムーティ/スカラ座の来日公演。メトでも観ているが印象は強くなく、今までの最高はムーティ/スカラとともに、20年以上前にロンドンのロイヤルオペラで観た、キリテカナワ/ドミンゴ/クライバーのそれだった。今宵の公演はそれと十分比較できる質の高い物だった。パリオペラ座の管弦楽がとにかく明るくヴェルディの音楽を楽しく奏でていたのが印象的だった。
2011年6月28日 パリオペラ座(バスチーユ)
Marco Armiliato/Conductor Andrei Serban/Stage director Peter Pabst/Sets
Aleksandrs Antonenko/Otello、Sergei Murzaev/Jago、Michael Fabiano/Cassio
Francisco Almanza/Roderigo、Renée Fleming / Desdemona、Nona Javakhidze/Emilia Paris Opera Orchestra and Chorus
パリオペラ座は先年来日し「トリスタンとイゾルテ」「青ひげ公の城」「」を上演した。非常にモダンな演出であった。パリオペラ座バレエは、現代のバレエと古典の名作をバランス良く日本に持ってきてくれるが、パリのオペラ座は来日自体がまだ1回だけなのである。何年に一度はパリにいく機会があり、バレエは「白鳥の湖」と「バヤデール」「ベジャールの夕べ」と観た事があったが、オペラは「マハガニー市の興亡」というクルトワイルの渋いオペラを観ただけだった。で、今回パリに行って1日だけオペラを観ることのできる日があってガルニエで古典的な「コシファントゥッテ」、そして、バスチーユでモダンな「オテロ」をやっていた。チケットがとれる方で観ようと思ってボックスオフィスに行ったら、どっちも最高席でとれるのである。迷ったあげく、ルネフレミングが歌うというので、「オテロ」となった。
来日時に観た「トリスタンとイゾルデ」と同じように、舞台上にイメージ映像を重ねて行く。例えば、今回は冒頭の嵐のシーンで、波の映像だったりするわけで、正直うるさい。それだけでなく、稲妻や嵐の効果音まで入れるのだ。うるさい。
ということで映像はうるさいのだが、舞台セットは簡素なもので、観客としては音楽と歌手の演技に集中できるものだったからいいのだろう。しかし、モダンな演出になったかと思えば、非常に古典的なものが入ってきたり、京劇の影響が出ていたりとバラエティ豊かというか、バラバラな感じなのである。衣装のことはあまりよく分からないが、こちらもモダンだったり、原作に忠実な感じだったり、時代や場所が少しずれるようなものも混ざっているように思えた。
作品の普遍性を出したいのかなあと思ったくらいに、何かね。
しかし、音楽はゴージャスそのものだった。イヤーゴを歌ったムラレフは演技も見事で堂々としたもの。最後はみんな死んでイヤーゴだけ生き残るという演出でありましたけど、この悪役ぶりじゃ生き残るねという感じだ。ロシアの歌手に悪役やらせたら本当にいいなあ。オテロのアントネコは徐々に調子をあげたが、未熟で嫉妬に走ってしまうという子供っぽい部分ばかりが見えていた。ルネフレミングはきっとキャリアの終わりに近いだろうが、長く歌う事もないからだろう。柳の歌を頂点に非常にコントロールされた、しかし女性らしい見事な声を聞かせてくれた。
合唱もよかったが、オーケストラの音がゴージャスだった。ヴェルディでもシェークスピア原作の作品として重厚な音をだした、ムーティ/スカラ座の来日公演。メトでも観ているが印象は強くなく、今までの最高はムーティ/スカラとともに、20年以上前にロンドンのロイヤルオペラで観た、キリテカナワ/ドミンゴ/クライバーのそれだった。今宵の公演はそれと十分比較できる質の高い物だった。パリオペラ座の管弦楽がとにかく明るくヴェルディの音楽を楽しく奏でていたのが印象的だった。
2011年6月28日 パリオペラ座(バスチーユ)
4ヶ月ぶりにジャズのライブ。20年以上前にマンハッタンのビレッジにあるブルーノートで聞いたなあ。

「ベースはベース」
ロンカーターと言う名前は不思議だ。カーターとロン(ロナルドレーガン)と70年代から80年代の2人の大統領の名前である。ロンカーターはまさしくその時期に頂点を極めたミュージシャンとひとりだろう。僕も80年代の終わりにニューヨークできいている。しかし、その印象は強くない。ベースだからだろう。ピアノやギターやペットとも違って、ベースなのだ。今宵もギターとベースで、それもベースがメロディを担って、「踊り明かそう」をボサノバでやってりするのだが、心が引かれると言った具合にはならない。むしろベースが一歩引いてピアノとギターにスポットライトを譲った演奏でのベースの方が魅力的に聞こえた。ベースはベースなのだ。
2011年6月19日 ブルーノート東京
「ベースはベース」
ロンカーターと言う名前は不思議だ。カーターとロン(ロナルドレーガン)と70年代から80年代の2人の大統領の名前である。ロンカーターはまさしくその時期に頂点を極めたミュージシャンとひとりだろう。僕も80年代の終わりにニューヨークできいている。しかし、その印象は強くない。ベースだからだろう。ピアノやギターやペットとも違って、ベースなのだ。今宵もギターとベースで、それもベースがメロディを担って、「踊り明かそう」をボサノバでやってりするのだが、心が引かれると言った具合にはならない。むしろベースが一歩引いてピアノとギターにスポットライトを譲った演奏でのベースの方が魅力的に聞こえた。ベースはベースなのだ。
2011年6月19日 ブルーノート東京
オデット/オディール:小出領子 ジークフリート王子:後藤晴雄
王妃:松浦真理絵 悪魔ロットバルト:柄本武尊 道化:小笠原亮
指揮:井田勝大 演奏:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ロベルトボッレをメインに今回の公演を組み、中日に後藤晴雄と小出領子をメインにしたプログラムを組んだが、ボッレは原発問題で降りてしまう。となると、公演自体のメインはこの中日になってしまった。小出さんのオディール/オデットが今日が初役らしく注目されたのだ。ネットの情報によると実生活でも夫婦らしくそりゃ話題になるよなという感じ。僕が東京バレエ団を観たのは1986年4月の「ザ・カブキ」の初演。東京文化会館に外国人がものすごく多く来てるのに驚いた物だ。ベジャールの全幕物の初演だったので注目されたのだろう。それ以来、東京バレエ団といえば、ベジャール中心にみてきた。僕のイメージはアジアのベジャールバレエ団。
それが昨年、いわゆるグランドバレエのジャンルに入る「オネーギン」を観た。作品が珍しかった。バレエは世界的に上演される作品は限られているので、今回のがしたら次はいつ観られるのだろうとも思ったわけ。チャイコフスキーの3大バレエ以外の作品ということでも興味があった。これが思いのほか良かった。そして、考えてみたら東京バレエ団は古典も上演しているのに、これはアンバランスだと思って見に行った訳です。
「白鳥の湖」。最初に観たのは大韓航空機事件があったばかりの1983年の9月。来日中のボリショイバレエ団で初めて見た。まだソビエト時代。グリゴローヴィッチという振付家の下での上演だった。(ちなみに初めてバレエを観たのは高校2年くらいの時で、キエフバレエ。くるみ割り)。いわゆる白いチュチュを着たロシア美女が大挙して黙って躍るわけです。その美しさとエロさに目を奪われたわけです。それ以外に「白鳥の湖」を観たのは限られています。ロイヤルバレエ団の来日公演でシルヴィギエムがオデットを踊ったものを家族で見に行ったし、パリに行った時にガルニエでパリオペラ座のそれを観た。主なものはその3回。あと何回か観ているけれど。それだけ。で、今宵の東京バレエ団。
思っていたよりも素晴らしかった。東京バレエ団美女が増えたなあという感じ。こんなフェミニンなバレエをこの団体で観た事がないから凄く新鮮だった。第一幕のコールドバレエ団の水準の高さに驚いた。別の公演ではオデットとジークフリートを踊るようなダンサーがコールドバレエを踊っていたりする。高橋竜太とか物凄い技術を持った人が、公演全体を通してコールドバレエしかやってなかったりする。いやあ、その水準にみんな併せようと必死になるわけだ。その上、東京バレエ団は世界中に公演旅行に行っているし、世界的なダンサーと共演する事が日常茶飯事だから、どんどん水準が上がるんだろうね。
もう重箱の隅をつつくようなことしか見つからない。3幕を中心として良かった。
2幕で有名な四話の白鳥の踊りなんだけど、今まで観た物ではもっとダイナミックな踊りなんです。頭を下げたり、あげたり、横を向いたり。何かね、ほとんど動かない。それが優雅さとか繊細な表現に見えるのかというとちょっと逃げているような感じがした。その点、そのすぐ後で踊る矢島まいなどが入った三羽の白鳥たちはダイナミズムがあった、小出領子はオディールとオデットの演じ分けが素晴らしく、表情も豊か。もっと身体が柔軟だったらなあとか、冒頭は回転の時にちょっと軸がずれている感じがしたけれども、まあ、素人なんで適当です。小柄ながら素晴らしかった。後藤のジークフリート王子だけれども、まあ世界中の他のジークフリートと同じように、フェミニンな王子なのである。もっと現代的な男っぽいジークフリートを作ってもいいのになと思ってしまう。何か女々しいんです。仕草とか。それがバレエだと言われればそうなんだろうけど。ディズニー映画の「シンデレラ」とか「白雪姫」に出てくる王子さまなんだよね。でもオディール(ブラックスワン)に浮気するわけじゃないですか。何かもっとね、違う人間像を作り出してもいいのになと思ってしまう。
僕が今宵感心したのは、道化を踊った小笠原亮です。背丈は小さいし、ノーブル感も全くない人なので演じられる役柄は限られているでしょうが、ものすごい技術力と演技力でした。冒頭の着地でちょこっと決まらなかったけれども、あとはもう凄い。1幕も良かったけれども、3幕のナポリでの小笠原の凄さ。止めと動きがピシピシ音が出るように決まり、その鋭さがお見事。他の日には道化を演じる松下裕次のチャルダッシュも良かった。視線まできちんと計算され尽くされていた。スペインでは再び矢島まいが踊り観ていてウキウキする。そして木村和夫と柄本弾が踊ったが、今日は木村の真摯で真面目な踊りが凄かった。柄本さん、ちょっと背が低いし顔がでかいなあと思った。まあこれからスターになる人であることは間違いないけれど。二階堂由衣は素晴らしかったです。
まあ、いろいろと言いましたが世界水準の踊りです。でもね、ちょっと美術と衣装は頂けなかった。最初の紗幕の絵の酷いこと。書き割り?の下手な事。ロイヤルバレエ団とか素晴らしいです。白鳥はこれからも何回も上演するんだろうからもう少し良い物をと思ってしまう。3幕のシャンデリアとか目に入るとがっかりしてしまう。
それから衣装。女性のものはまだしも男の衣装の色合いの悪いこと、デザインの陳腐なこと。道化の赤なんか、ダンサーに失礼だと思うくらい安っぽい。
最後に強いて問題点を言えば、王妃役の松浦さんでしょうか。若すぎる。やっぱりもっと歳をとった、現役時代には大スターだったと風格のある人に演じてもらいたいものです。王妃の優雅さとか演じるんじゃダメなんだと思ったです。湧き出てくる物じゃないと。東京シティフィルは大健闘。
 初役を成功させた小出領子。
初役を成功させた小出領子。
【第1幕】
家庭教師: 佐藤瑶
パ・ド・トロワ:乾友子、吉川留衣、松下裕次
ワルツ(ソリスト):西村真由美、高木綾、田中結子、加茂雅子、小川ふみ、二階堂由依
【第2幕/第4幕】
四羽の白鳥:高村順子、村上美香、吉川留衣、河合眞里
三羽の白鳥:西村真由美、乾友子、矢島まい
【第3幕】 司会者:宮崎大樹
チャルダッシュ (第1ソリスト):西村真由美-松下裕次
(第2ソリスト):村上美香、岸本夏未、氷室友、岡崎隼也
ナポリ(ソリスト): 河合眞里-小笠原亮
マズルカ(ソリスト): 奈良春夏、田中結子、宮本祐宜、長瀬直義
花嫁候補たち:乾友子、佐伯知香、阪井麻美、渡辺理恵、川島麻実子、大塚怜衣
スペイン:高木綾、矢島まい-木村和夫、柄本弾
2011年6月18日 ゆうぽうと簡易保険ホール
王妃:松浦真理絵 悪魔ロットバルト:柄本武尊 道化:小笠原亮
指揮:井田勝大 演奏:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
ロベルトボッレをメインに今回の公演を組み、中日に後藤晴雄と小出領子をメインにしたプログラムを組んだが、ボッレは原発問題で降りてしまう。となると、公演自体のメインはこの中日になってしまった。小出さんのオディール/オデットが今日が初役らしく注目されたのだ。ネットの情報によると実生活でも夫婦らしくそりゃ話題になるよなという感じ。僕が東京バレエ団を観たのは1986年4月の「ザ・カブキ」の初演。東京文化会館に外国人がものすごく多く来てるのに驚いた物だ。ベジャールの全幕物の初演だったので注目されたのだろう。それ以来、東京バレエ団といえば、ベジャール中心にみてきた。僕のイメージはアジアのベジャールバレエ団。
それが昨年、いわゆるグランドバレエのジャンルに入る「オネーギン」を観た。作品が珍しかった。バレエは世界的に上演される作品は限られているので、今回のがしたら次はいつ観られるのだろうとも思ったわけ。チャイコフスキーの3大バレエ以外の作品ということでも興味があった。これが思いのほか良かった。そして、考えてみたら東京バレエ団は古典も上演しているのに、これはアンバランスだと思って見に行った訳です。
「白鳥の湖」。最初に観たのは大韓航空機事件があったばかりの1983年の9月。来日中のボリショイバレエ団で初めて見た。まだソビエト時代。グリゴローヴィッチという振付家の下での上演だった。(ちなみに初めてバレエを観たのは高校2年くらいの時で、キエフバレエ。くるみ割り)。いわゆる白いチュチュを着たロシア美女が大挙して黙って躍るわけです。その美しさとエロさに目を奪われたわけです。それ以外に「白鳥の湖」を観たのは限られています。ロイヤルバレエ団の来日公演でシルヴィギエムがオデットを踊ったものを家族で見に行ったし、パリに行った時にガルニエでパリオペラ座のそれを観た。主なものはその3回。あと何回か観ているけれど。それだけ。で、今宵の東京バレエ団。
思っていたよりも素晴らしかった。東京バレエ団美女が増えたなあという感じ。こんなフェミニンなバレエをこの団体で観た事がないから凄く新鮮だった。第一幕のコールドバレエ団の水準の高さに驚いた。別の公演ではオデットとジークフリートを踊るようなダンサーがコールドバレエを踊っていたりする。高橋竜太とか物凄い技術を持った人が、公演全体を通してコールドバレエしかやってなかったりする。いやあ、その水準にみんな併せようと必死になるわけだ。その上、東京バレエ団は世界中に公演旅行に行っているし、世界的なダンサーと共演する事が日常茶飯事だから、どんどん水準が上がるんだろうね。
もう重箱の隅をつつくようなことしか見つからない。3幕を中心として良かった。
2幕で有名な四話の白鳥の踊りなんだけど、今まで観た物ではもっとダイナミックな踊りなんです。頭を下げたり、あげたり、横を向いたり。何かね、ほとんど動かない。それが優雅さとか繊細な表現に見えるのかというとちょっと逃げているような感じがした。その点、そのすぐ後で踊る矢島まいなどが入った三羽の白鳥たちはダイナミズムがあった、小出領子はオディールとオデットの演じ分けが素晴らしく、表情も豊か。もっと身体が柔軟だったらなあとか、冒頭は回転の時にちょっと軸がずれている感じがしたけれども、まあ、素人なんで適当です。小柄ながら素晴らしかった。後藤のジークフリート王子だけれども、まあ世界中の他のジークフリートと同じように、フェミニンな王子なのである。もっと現代的な男っぽいジークフリートを作ってもいいのになと思ってしまう。何か女々しいんです。仕草とか。それがバレエだと言われればそうなんだろうけど。ディズニー映画の「シンデレラ」とか「白雪姫」に出てくる王子さまなんだよね。でもオディール(ブラックスワン)に浮気するわけじゃないですか。何かもっとね、違う人間像を作り出してもいいのになと思ってしまう。
僕が今宵感心したのは、道化を踊った小笠原亮です。背丈は小さいし、ノーブル感も全くない人なので演じられる役柄は限られているでしょうが、ものすごい技術力と演技力でした。冒頭の着地でちょこっと決まらなかったけれども、あとはもう凄い。1幕も良かったけれども、3幕のナポリでの小笠原の凄さ。止めと動きがピシピシ音が出るように決まり、その鋭さがお見事。他の日には道化を演じる松下裕次のチャルダッシュも良かった。視線まできちんと計算され尽くされていた。スペインでは再び矢島まいが踊り観ていてウキウキする。そして木村和夫と柄本弾が踊ったが、今日は木村の真摯で真面目な踊りが凄かった。柄本さん、ちょっと背が低いし顔がでかいなあと思った。まあこれからスターになる人であることは間違いないけれど。二階堂由衣は素晴らしかったです。
まあ、いろいろと言いましたが世界水準の踊りです。でもね、ちょっと美術と衣装は頂けなかった。最初の紗幕の絵の酷いこと。書き割り?の下手な事。ロイヤルバレエ団とか素晴らしいです。白鳥はこれからも何回も上演するんだろうからもう少し良い物をと思ってしまう。3幕のシャンデリアとか目に入るとがっかりしてしまう。
それから衣装。女性のものはまだしも男の衣装の色合いの悪いこと、デザインの陳腐なこと。道化の赤なんか、ダンサーに失礼だと思うくらい安っぽい。
最後に強いて問題点を言えば、王妃役の松浦さんでしょうか。若すぎる。やっぱりもっと歳をとった、現役時代には大スターだったと風格のある人に演じてもらいたいものです。王妃の優雅さとか演じるんじゃダメなんだと思ったです。湧き出てくる物じゃないと。東京シティフィルは大健闘。
【第1幕】
家庭教師: 佐藤瑶
パ・ド・トロワ:乾友子、吉川留衣、松下裕次
ワルツ(ソリスト):西村真由美、高木綾、田中結子、加茂雅子、小川ふみ、二階堂由依
【第2幕/第4幕】
四羽の白鳥:高村順子、村上美香、吉川留衣、河合眞里
三羽の白鳥:西村真由美、乾友子、矢島まい
【第3幕】 司会者:宮崎大樹
チャルダッシュ (第1ソリスト):西村真由美-松下裕次
(第2ソリスト):村上美香、岸本夏未、氷室友、岡崎隼也
ナポリ(ソリスト): 河合眞里-小笠原亮
マズルカ(ソリスト): 奈良春夏、田中結子、宮本祐宜、長瀬直義
花嫁候補たち:乾友子、佐伯知香、阪井麻美、渡辺理恵、川島麻実子、大塚怜衣
スペイン:高木綾、矢島まい-木村和夫、柄本弾
2011年6月18日 ゆうぽうと簡易保険ホール
青年団リンク ガレキの太鼓「いないいない」
作・演出:舘そらみ
出演 木崎友紀子(青年団) 梶野春菜 北川裕子 篠崎友(とくお組) 鈴木浩司(時間堂)林竜三(青☆組) 他
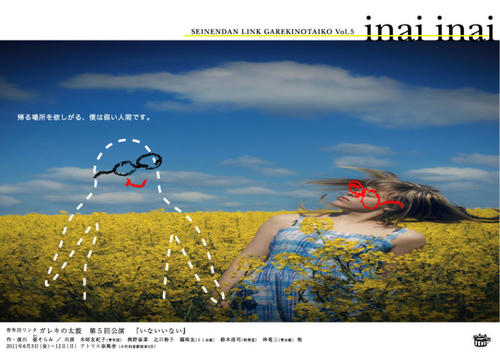
つい、こないだまで学生だった劇団の青年団リンク「昇格後」の初公演。
上演時間95分。「アンネの日記」を思わせる設定で美術やアイデアは面白い。そして、何と行っても役者が見事だった。北川裕子、篠崎友、鈴木浩司…。もうちょっと短くていいかも。
アトリエ春風舎 2011年6月4日
花組芝居「番町皿屋敷」
作演出・加納幸和
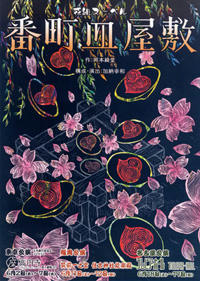
「圧倒的な成功」
正直申し上げると、ここまでは期待しておりませんでした。しかし、花組芝居の作品のこの数年の作品の中で圧倒的な成功を収めた作品になったのではないでしょうか?能舞台で繰り広げられるネオ歌舞伎。もちろん加納幸和さんならではの遊びもふんだんに盛り込まれていますが、歌舞伎を少しでも知っているものには、さらに面白くて面白くて。
舞台はシンプルですが美しい。桜や定形幕がきりっとした空間を作り、小劇場では考えられない衣装にメイク。芝居と見事に調和した下座音楽。しかし、何よりも俳優たちの見事な演技。決めるところと遊ぶところが見事に演じ分けられる。磯村さんが弁慶で出てくるや、声から言い回しから成田屋(団十郎さん)のようになっているところから、谷山さんの見事な二役。この人は大俳優になるんでしょうなあ。
美斉津、丸川に、加納さんにも負けていない見事な女形の堀越涼。ベテランの北沢さん、中堅の松原綾央も負けていません。しかし、小林大介は、前から芝居が上手いと評判でしたが、今回はまた一つの壁を越えたところまで行った感じがしますね。何しろ重心が低い。堂々としていて、崩すところ遊ぶところも知っている。二瓶さんももちろんツボを抑え、いや、大野さんまで良いんだからこりゃ参りますよ。
全ては加納さんの演技指導あっての賜物だとは思いますが、あまりにもお見事で参ってしまいました。ひとこと申し上げるとすれば、加納さんのそれが風合いだとは思うのですが、ちょっとやり過ぎ、引っぱりすぎなところがあったかなあとも思います。あと、カーテンコールはもっとさらっとやった方がいいのにと思いました。ああ、芝居の余韻が消えて行く〜と思いました。もちろん花組ファミリーと自覚されるご贔屓には嬉しい物なのでしょうが。
一分の隙もない公演というのはこういうことを言うのでしょう。余りにも見事でぶっ倒れそうになりました。
2011年6月7日 座・高円寺
北区つかこうへい劇団「ALLTHAT 飛龍伝90」
出演/高野愛・小川智之・北田理道、渡辺昇
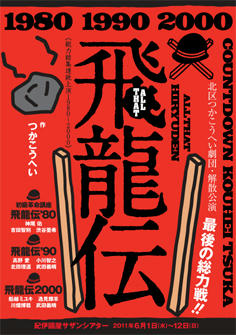
「夏の終わりの花火大会のような」
北区つかこうへい劇団の見納めとして出かけました。前から七列目のセンターという最上の席であったこともありがたい。お声をかけて、配席までしてくださったK氏に感謝。つかこうへいさんが亡くなっても、ここに生きているなと思いました。それも、いい意味で力が抜けている感じもして、さらに北区つかこうへい劇団は進化したとも思ったのです。北田理道さんは幾多の名優が演じた難しい役柄を見事に演じていた。入魂の演技でありながら、ただパワーだけで押し切らない。小川さんは、見事な二枚目です。ベテランの武田義晴さん、とめ貴志さんなどが健在でぶちかましていたのも嬉しかった。渡辺昇はいい意味で僕がよく見た1990年代のつかこうへい劇団の俳優のようだった。高野愛はきりりとして立ち姿が美しく、台詞回しが良い。もうすぐ伝説になる劇団の公演を見られて本当に良かった。それは、夏の終わりの花火大会のように華やかで美しくちょっと寂しい、散り際の美しさがあった。感謝。
2011年6月7日 紀伊国屋サザンシアター
青年団リンク 二騎の会「第四倉庫」
作:宮森さつき 演出:多田淳之介
出演 秋山建一 島田曜蔵 村井まどか 菅原直樹

数年ぶりにみた多田作品。まあ役者がうまいこと。美術がスタイリッシュ。脚本はもう少し削ることも可能だよなあと思いつつも、その部分こそがいいのかなと思ったり。少なくとも30人弱の客席に爆睡者が何人もいた。客を選ぶ作品とはこういうものだろう。多田淳之介、相変わらず好きなことやっているのだと、羨ましいと思った。
2011年6月13日 こまばアゴラ劇場
作・演出:舘そらみ
出演 木崎友紀子(青年団) 梶野春菜 北川裕子 篠崎友(とくお組) 鈴木浩司(時間堂)林竜三(青☆組) 他
つい、こないだまで学生だった劇団の青年団リンク「昇格後」の初公演。
上演時間95分。「アンネの日記」を思わせる設定で美術やアイデアは面白い。そして、何と行っても役者が見事だった。北川裕子、篠崎友、鈴木浩司…。もうちょっと短くていいかも。
アトリエ春風舎 2011年6月4日
花組芝居「番町皿屋敷」
作演出・加納幸和
「圧倒的な成功」
正直申し上げると、ここまでは期待しておりませんでした。しかし、花組芝居の作品のこの数年の作品の中で圧倒的な成功を収めた作品になったのではないでしょうか?能舞台で繰り広げられるネオ歌舞伎。もちろん加納幸和さんならではの遊びもふんだんに盛り込まれていますが、歌舞伎を少しでも知っているものには、さらに面白くて面白くて。
舞台はシンプルですが美しい。桜や定形幕がきりっとした空間を作り、小劇場では考えられない衣装にメイク。芝居と見事に調和した下座音楽。しかし、何よりも俳優たちの見事な演技。決めるところと遊ぶところが見事に演じ分けられる。磯村さんが弁慶で出てくるや、声から言い回しから成田屋(団十郎さん)のようになっているところから、谷山さんの見事な二役。この人は大俳優になるんでしょうなあ。
美斉津、丸川に、加納さんにも負けていない見事な女形の堀越涼。ベテランの北沢さん、中堅の松原綾央も負けていません。しかし、小林大介は、前から芝居が上手いと評判でしたが、今回はまた一つの壁を越えたところまで行った感じがしますね。何しろ重心が低い。堂々としていて、崩すところ遊ぶところも知っている。二瓶さんももちろんツボを抑え、いや、大野さんまで良いんだからこりゃ参りますよ。
全ては加納さんの演技指導あっての賜物だとは思いますが、あまりにもお見事で参ってしまいました。ひとこと申し上げるとすれば、加納さんのそれが風合いだとは思うのですが、ちょっとやり過ぎ、引っぱりすぎなところがあったかなあとも思います。あと、カーテンコールはもっとさらっとやった方がいいのにと思いました。ああ、芝居の余韻が消えて行く〜と思いました。もちろん花組ファミリーと自覚されるご贔屓には嬉しい物なのでしょうが。
一分の隙もない公演というのはこういうことを言うのでしょう。余りにも見事でぶっ倒れそうになりました。
2011年6月7日 座・高円寺
北区つかこうへい劇団「ALLTHAT 飛龍伝90」
出演/高野愛・小川智之・北田理道、渡辺昇
「夏の終わりの花火大会のような」
北区つかこうへい劇団の見納めとして出かけました。前から七列目のセンターという最上の席であったこともありがたい。お声をかけて、配席までしてくださったK氏に感謝。つかこうへいさんが亡くなっても、ここに生きているなと思いました。それも、いい意味で力が抜けている感じもして、さらに北区つかこうへい劇団は進化したとも思ったのです。北田理道さんは幾多の名優が演じた難しい役柄を見事に演じていた。入魂の演技でありながら、ただパワーだけで押し切らない。小川さんは、見事な二枚目です。ベテランの武田義晴さん、とめ貴志さんなどが健在でぶちかましていたのも嬉しかった。渡辺昇はいい意味で僕がよく見た1990年代のつかこうへい劇団の俳優のようだった。高野愛はきりりとして立ち姿が美しく、台詞回しが良い。もうすぐ伝説になる劇団の公演を見られて本当に良かった。それは、夏の終わりの花火大会のように華やかで美しくちょっと寂しい、散り際の美しさがあった。感謝。
2011年6月7日 紀伊国屋サザンシアター
青年団リンク 二騎の会「第四倉庫」
作:宮森さつき 演出:多田淳之介
出演 秋山建一 島田曜蔵 村井まどか 菅原直樹
数年ぶりにみた多田作品。まあ役者がうまいこと。美術がスタイリッシュ。脚本はもう少し削ることも可能だよなあと思いつつも、その部分こそがいいのかなと思ったり。少なくとも30人弱の客席に爆睡者が何人もいた。客を選ぶ作品とはこういうものだろう。多田淳之介、相変わらず好きなことやっているのだと、羨ましいと思った。
2011年6月13日 こまばアゴラ劇場
最新記事
(01/06)
(12/25)
(08/05)
(06/30)
(12/16)
(08/21)
(04/10)
(09/25)
(11/30)
(11/18)
(11/03)
(10/04)
(09/19)
(08/28)
(06/25)
(06/10)
(12/30)
(02/21)
(12/31)
(09/28)
(06/09)
(05/12)
(12/31)
(09/08)
(06/02)
プロフィール
HN:
佐藤治彦 Haruhiko SATO
HP:
性別:
男性
職業:
演劇ユニット経済とH 主宰
趣味:
海外旅行
自己紹介:
演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員
カテゴリー
カレンダー
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新CM
[08/24 おばりーな]
[02/18 清水 悟]
[02/12 清水 悟]
[10/17 栗原 久美]
[10/16 うさきち]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(12/05)
(12/07)
(12/08)
(12/09)
(12/10)
(12/11)
(12/29)
(01/03)
(01/10)
(01/30)
(02/13)
(03/09)
(03/12)
(03/16)
(03/17)
(03/19)
(03/20)
(03/20)
(03/22)
(03/22)
(03/23)
(03/24)
(03/28)
(04/01)
(04/01)
カウンター
