自ら演劇の台本を書き、さまざまな種類のパフォーミングアーツを自腹で行き続ける佐藤治彦が気になった作品について取り上げるコメンタリーノート、エッセイ。テレビ番組や映画も取り上げます。タイトルに批評とありますが、本人は演劇や音楽の評論家ではありません。個人の感想や思ったこと、エッセイと思って読んで頂ければ幸いです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010年10月13日
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団は、目前に迫っている日本ツアーに際し、更なる変更のお知らせをしなければなりません。病気のため、日本ツアーを降板した小澤征爾氏に代わり、アンドリス・ネルソンス氏と二人で「ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2010」を指揮する予定だったエサ=ペッカ・サロネン氏は、自身のコントロールの及ばない事情のため、急遽予定されていた一連の演奏会をキャンセルせざるを得なくなりました。
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団は、我々が深い信頼を寄せる三人の指揮者、ジョルジュ・プレートル、フランツ・ウェルザー=メスト、アンドリス・ネルソンスの各氏が、川崎、西宮、宮崎および東京の演奏会の開催を可能にしてくださったことに心より感謝申しあげます。
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 楽団長
クレメンス・ヘルスベルク
サロネンがキャンセル。いやはや今年は最後の最後までどうなるか分かりませんが、86才のジョルジュプレートルが来日することが決まるやいなや、11月10日のチケットはプレミアムチケットとなりました。ネットでも高く売られていたり。いやはや。曲目も、ベートーヴェンの3番、英雄が入ったことで人気が出たんでしょう。その反面、割りを食ったのが、次代のホープとしてもてはやされた1978年生まれのアンドリスネルソンス。そのチケットの暴落が始まりました。仕方がないです。新世界やモーツアルトという人気曲目をいれて小澤キャンセル後にそこそこ人気がでたのですが、首都圏での演奏会がもう一回増えてしまったからです。サロネンはブルックナーやマーラーでしたから。
11月1日、2日、5日と3回となり暴落中です。クラシック音楽の演奏会に3万円以上だして聴いてもいいやと思う人がどれくらいいるかが如実に分かりますね。大していないんです。
20世紀の巨匠音楽が次々と世を去った今。実は見渡してみると、マリアカラスとの50年代からの名演が残っているプレートルや、ピアニストのチッコリーニなどフランス人には素晴らしい巨匠が残っていてくれるのですね。
2010年11月1日(月)19:00開演(18:20開場) 指揮:アンドリス・ネルソンス
モーツァルト:交響曲第33番 変ロ長調 K319
アンリ・トマジ:トロンボーン協奏曲(トロンボーン:ディートマル・キューブルベック)
ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 B178「新世界より」
アンコール
ブラームス(ドヴォルザーク編):ハンガリー舞曲第20番ホ短調 第21番ホ短調
2010年11月9日(火)19:00開演 指揮:フランツウェルザーメスト
ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と愛の死
ブルックナー 交響曲第9番
2010年11月10日(水)19:00開演(18:20開場) 指揮:ジョルジュ・プレートル
シューベルト:交響曲第2番 変ロ長調 D125
ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調 op. 55 「英雄」
※マーラー:交響曲第9番 ニ長調 から上記2曲に変更になりました
アンコール ブラームス :ハンガリー舞曲第1番 ト短調
J.シュトラウスⅡ:トリッチ・トラッチ・ポルカ
小沢征爾が指揮するはずだったところが降板。かり出された二人の指揮者。僕はサロネンとウィーンフィルの演奏を2009年のザルツブルグ音楽祭できいている。あのときもブルックナーの交響曲6番。そしてベルグだった。ベルグがあまりにも良くて、ブルックナーの印象があまり強くない。ああ、ウィーンフィルのサウンドだよなあ〜くらい。さて、どんな演奏になるのか愉しみだ。
モーツアルトの交響曲はこの若い指揮者が何をどうしてもびくともしない。それがウィーンフィルの伝統だ。このモーツアルトは非常に美しい。色彩感溢れるモーツアルトだった。ネルソンズはまるで若い頃の小沢征爾のように飛び跳ねるように指揮をする。決してウィーンフィルをこうしてやろうという野心はない。僕はそういう野心をもって欲しい。伝統を知らないからこそ起こせる音楽ってのが若者にはできるのだ。ドゥメダルが何で人気なのかってそこじゃないですか。自分自身の指揮者すごろくのことに興味を持つのではなく、モーツアルトやウィーンフィルと対峙して欲しかった。トマジの音楽は20世紀のフランスの作曲家なのだけれど、旋律がきちんとあって聞きやすい。トロンボーンも魅力にも溢れまた聞いてみたい曲だった。新世界は本当に美しい演奏だった。考えてみると、ウィーンはボヘミアのはずれにあるようなものだし、ウィーンフィルの音色を楽しんだ。しかしね、何か素朴さとかは感じられないんだよね。3曲とも原色で描かれた感じ。陶器の味わいって古いものにあるじゃないですか。100年前の職人によって丁寧に作られ、100年間大切に使われてきた陶器にある味わい。同じヘレンドやウェッジウッドでもそう。それがここにはない。最新の高級な陶器かもしれないけれど、そこに何かね、ないような感じがした。2010年11月1日 サントリーホール
11月9日 フランツウェルザーメストの指揮による演奏会を最初に聞いたのはいつだったか。きっと10年くらい前で、まだ20世紀の巨匠が何人か活躍している時代だったと思う。感心もせず、放ったらかしにしていた。それが、チューリッヒ歌劇場の2007年の来日公演で「椿姫」と「ばらの騎士」を振ったのをきいて、演出はヘンテコなものだったけれど、管弦楽が素晴らしく、へえ!と感心したのである。それが、今年の秋からはウィーン国立歌劇場の音楽監督だし、2011年のニューニャーコンサートのシェフも勤めるという。
今宵聞いた音楽は大変満足のいくものだった。どこそこのホルンの響かせ方が良かったとか、弦のピッチが絶妙だったとかそういう専門的なことは分からないけれども、音楽の核心に迫ろうとしているのが良く分かった。それは、ドイツーオーストリア音楽の中心地であるウィーンの音楽の伝統に身を委ねているということでもある。2010年11月9日 サントリーホール
そして、プレートル。ネットの記録によると前回の来日は1998年のパリ管弦楽団との演奏会らしい。それは僕もきいている。確か大宮のソニックシティ大ホールまで聞きにいったと記憶しているんだけれど、どうだったかなあ。パリ管はそれこそ1980年ごろにバレンボイムで来日したときから度々きいているんだけれども、プレートルのそれがあまりにも良くてびっくりしたことがある。氏はマリアカラスとの伝説的録音が有名でオペラ指揮者と認識されてんだよな。日本では。
僕は見てもいないけれど、2008年と10年のニューイヤーコンサートが話題になり、今回、最後にプレートルの名前が出て来て東京中の音楽ファンは驚がくしたみたい。ネットでも高嶺がつくプレミアムチケットになった。
パリ管との12年前の演奏会では指揮棒を細かく揺らしていたのを覚えているんだけれども、今宵はまるであのカールベームの最晩年の来日の時のようにに、指揮棒に無駄な動きは一切ない。手のひらで表情をつけたり、腕を高々と挙げ音楽の流れの極みを指示するといった。シューベルトの交響曲第2番は演奏会のために予習する為に始めてきちんと聞いたんだけれど、何てチャーミングな曲なんだろう。すっかり好きになってしまった。英雄交響曲は一生ものの演奏だった。それは、音楽の芯をがっちりつかんで揺らさないウィーンフィルの演奏だった。拡張高く過去から現在に演奏され、それが将来にも引き継がれる音楽であることを体得させる演奏だった。2010年11月10日 サントリーホール
PR
これは事件だ!
ニコラウス・アーノンクール指揮
ウィーンコンツェントゥスムジクス 来日演奏会
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
オーケストラ : ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮: ニコラウス・アーノンクール
サントリーホール S¥28,000 A¥23,000 B¥18,000 C¥13,000 D¥9,000
プラチナ券¥33,000
J.S.バッハ : ミサ曲 ロ短調 BWV232
ソプラノ1: ドロテア・レッシュマン
ソプラノ2: エリーザベト・フォン・マグヌス
アルト: ベルナルダ・フィンク
テノール: ミヒャエル・シャーデ
バス: フローリアン・ベッシュ
合唱: アーノルト・シェーンベルク合唱団
2010年10月24日 午後6時開演 NHKホール
ハイドン : オラトリオ「天地創造」
ソプラノ: ドロテア・レッシュマン
テノール: ミヒャエル・シャーデ
バス: フローリアン・ベッシュ
合唱: アーノルト・シェーンベルク合唱団
2010年10月29日 午後7時開演 サントリーホール
モーツァルト : 交響曲第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
モーツァルト : セレナード第9番 ニ長調 K.320「ポストホルン」
2010年11月2日 午後7時開演 東京オペラシティコンサートホール

僕が9年ほど前に、ドイツを旅行中にベルリンフィルハーモニーを現地できいたとき、指揮者がアーノンクールでした。モーツアルトの曲などをやったのかな。よく覚えていません。マチネのコンサートで名前はきいていたこの伝説の指揮者の生演奏がきけるということで喜んで出かけたのです。先ずはどんな顔のひとなのか、次の映像をごらん下さい。
スゴい顔してますよね。これがアーノンクールです。もう80才です。何十年も既存のクラシック音楽の反逆児でもありました。音楽演奏の新しい潮流を作ったひとですが、それは新奇なのではなく、原点回帰でもあります。最初にきいたとき、ききなれた古典派の音楽がどれだけ新しく聞こえたか。ローマのシステーナ礼拝堂に2006年に20年ぶりくらいに往きましたが、古い汚れがすべて洗い落とされて、見違えるようなものになっていた。同じ作品とは思えないような壁画でした。それと同じような経験が音楽でできるのです。アーノンクールは飛行機嫌いで日本に対する誤解もあり来日は何十年もありませんでした。それが、2006年に日本に来日し奇跡の演奏会と伝説となりました。もう一度来日してくれることになったのです。宣伝では最後の来日となっています。聞き逃すわけにはいきません。
生まれて初めて、高校の時にレコードできいて衝撃を受けたハイドン「天地創造」を生演奏できけるだけでなくバッハの「ロ短調ミサ」もきくことにしました。いま予習中です。チケット代は高いですが、これは行かなくてはいけないコンサートです。
バッハ作曲 ミサ曲ロ短調
NHK音楽祭。NHKホールの巨大な空間に宗教音楽とは似つかないものなんだけれども、満員の観客は素晴らしい音楽体験をする悦びに浸っていた。バッハの音楽が活き活きと現代に動き出し、溢れる光を放つ。ホルンの調子がちょこっと悪かったのだけれども、全体を一貫する音楽の魅力はいったいどこから来ているのだろう。他の指揮者の音楽と演奏方法や楽譜へのアプローチがどう違うのだろう。
ほぼ10年ぶりのアーノンクールは、光り輝いていた。万雷の拍手とはこういうやつだなあ。久々に座った3階席でのコンサート。遥か遠くの演奏者を斜に構えながら聴き始めた自分を惹き込んだ81才の革命児に圧倒された。2010年10月24日 NHKホール
ハイドン作曲 天地創造
アーノンクールの演奏するこの曲を聴いているとハイドンのそのほかの交響曲やピアノソナタなどを聴いている時には感じられないロマン派の匂いが時々してくるから不思議だ。神が天地創造をする前などは、宇宙のビックバンを感じさせる無常観溢れる演奏。アーノンクールは右手で細かくリズムを刻み、身体をくねらせてグルーブ感を盛り上げる。素晴らしい合唱に、ソリスト。僕の人生の中でこれ以上の天地創造は聴けないんだろうなあと思いつつ、生涯一回の邂逅に身を委ねた。例のロマン派は生演奏だとさらにはっきりと突き刺さるように浮き上がる。他の奏者はどうしていたのだろう。無視したのか、読み飛ばしたのか、ハイドンが意図してやったとは思っていなかったんだろうか?僕はハイドンがいなくちゃ、ベートーヴェンもモーツアルトもあそこに辿り着けなかったかもしれないと思いつつきいた。この素晴らしい演奏に、会場から盛んの拍手。しかし、高額の席に関しては6割の入り。こんな素晴らしい演奏を大量の空席で決行した主催者側にもう少し考えて頂きたいと思う。28000円のチケット代はやはり高過ぎるのだ。もう少し値ごろ感のある価格にできなかったのか。
そして、NHK音楽祭に天地創造を持っていき、サントリーの天地創造は一回ということであれば、もう少し入ったのではないか?そう、むしろ ロ短調ミサをサントリーで2回やるほうが懸命だったような感じです。まあ、そんな下世話な話はおいておいて、素晴らしい演奏にブラボー。
2010年10月29日。サントリーホール
モーツアルトプロ
前日にウィーンフィルでモーツアルトの交響曲33番を聞いていた。同じウィーンのオケなのに、どうしてこう違うんだろう。こちらのモーツアルトには音楽の、いや生きる悦びが溢れている。音は快活に活動しほら音楽ってこんなに素敵じゃないか!って話しかける。ピリオド奏法が何かは分からないが、あの音楽を奏でる為には、楽員がみんな心を併せ、同じ呼吸をしていないと、きっと難しいだろうなと思う。非常に絶妙な息の併せ方が必要なのだ。それが微妙なニュアンスで伝わる。バイオリンとチェロ、木管は違う音を奏でるのに根っこが一緒なのが分かる。そして、録音では聞こえなかった楽器の音色が聞こえてくる。どこまでも幸福な音楽の時であった。アンコールピースが終わったと同時に、もうこのアーノンクールの演奏は聴けないんだと思うと無性に寂しくなった。体調が良くなく開演の1時間半前まで辞めようと思っていたが無理した。コンサートにタクシーで乗り付けるなんて事は僕の今までの記憶ではないけれど。ああ、そうして良かった。
2010年11月2日 東京オペラシティコンサートホール
ニコラウス・アーノンクール指揮
ウィーンコンツェントゥスムジクス 来日演奏会
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
オーケストラ : ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス
指揮: ニコラウス・アーノンクール
サントリーホール S¥28,000 A¥23,000 B¥18,000 C¥13,000 D¥9,000
プラチナ券¥33,000
J.S.バッハ : ミサ曲 ロ短調 BWV232
ソプラノ1: ドロテア・レッシュマン
ソプラノ2: エリーザベト・フォン・マグヌス
アルト: ベルナルダ・フィンク
テノール: ミヒャエル・シャーデ
バス: フローリアン・ベッシュ
合唱: アーノルト・シェーンベルク合唱団
2010年10月24日 午後6時開演 NHKホール
ハイドン : オラトリオ「天地創造」
ソプラノ: ドロテア・レッシュマン
テノール: ミヒャエル・シャーデ
バス: フローリアン・ベッシュ
合唱: アーノルト・シェーンベルク合唱団
2010年10月29日 午後7時開演 サントリーホール
モーツァルト : 交響曲第35番 ニ長調 K.385 「ハフナー」
モーツァルト : セレナード第9番 ニ長調 K.320「ポストホルン」
2010年11月2日 午後7時開演 東京オペラシティコンサートホール
僕が9年ほど前に、ドイツを旅行中にベルリンフィルハーモニーを現地できいたとき、指揮者がアーノンクールでした。モーツアルトの曲などをやったのかな。よく覚えていません。マチネのコンサートで名前はきいていたこの伝説の指揮者の生演奏がきけるということで喜んで出かけたのです。先ずはどんな顔のひとなのか、次の映像をごらん下さい。
スゴい顔してますよね。これがアーノンクールです。もう80才です。何十年も既存のクラシック音楽の反逆児でもありました。音楽演奏の新しい潮流を作ったひとですが、それは新奇なのではなく、原点回帰でもあります。最初にきいたとき、ききなれた古典派の音楽がどれだけ新しく聞こえたか。ローマのシステーナ礼拝堂に2006年に20年ぶりくらいに往きましたが、古い汚れがすべて洗い落とされて、見違えるようなものになっていた。同じ作品とは思えないような壁画でした。それと同じような経験が音楽でできるのです。アーノンクールは飛行機嫌いで日本に対する誤解もあり来日は何十年もありませんでした。それが、2006年に日本に来日し奇跡の演奏会と伝説となりました。もう一度来日してくれることになったのです。宣伝では最後の来日となっています。聞き逃すわけにはいきません。
生まれて初めて、高校の時にレコードできいて衝撃を受けたハイドン「天地創造」を生演奏できけるだけでなくバッハの「ロ短調ミサ」もきくことにしました。いま予習中です。チケット代は高いですが、これは行かなくてはいけないコンサートです。
バッハ作曲 ミサ曲ロ短調
NHK音楽祭。NHKホールの巨大な空間に宗教音楽とは似つかないものなんだけれども、満員の観客は素晴らしい音楽体験をする悦びに浸っていた。バッハの音楽が活き活きと現代に動き出し、溢れる光を放つ。ホルンの調子がちょこっと悪かったのだけれども、全体を一貫する音楽の魅力はいったいどこから来ているのだろう。他の指揮者の音楽と演奏方法や楽譜へのアプローチがどう違うのだろう。
ほぼ10年ぶりのアーノンクールは、光り輝いていた。万雷の拍手とはこういうやつだなあ。久々に座った3階席でのコンサート。遥か遠くの演奏者を斜に構えながら聴き始めた自分を惹き込んだ81才の革命児に圧倒された。2010年10月24日 NHKホール
ハイドン作曲 天地創造
アーノンクールの演奏するこの曲を聴いているとハイドンのそのほかの交響曲やピアノソナタなどを聴いている時には感じられないロマン派の匂いが時々してくるから不思議だ。神が天地創造をする前などは、宇宙のビックバンを感じさせる無常観溢れる演奏。アーノンクールは右手で細かくリズムを刻み、身体をくねらせてグルーブ感を盛り上げる。素晴らしい合唱に、ソリスト。僕の人生の中でこれ以上の天地創造は聴けないんだろうなあと思いつつ、生涯一回の邂逅に身を委ねた。例のロマン派は生演奏だとさらにはっきりと突き刺さるように浮き上がる。他の奏者はどうしていたのだろう。無視したのか、読み飛ばしたのか、ハイドンが意図してやったとは思っていなかったんだろうか?僕はハイドンがいなくちゃ、ベートーヴェンもモーツアルトもあそこに辿り着けなかったかもしれないと思いつつきいた。この素晴らしい演奏に、会場から盛んの拍手。しかし、高額の席に関しては6割の入り。こんな素晴らしい演奏を大量の空席で決行した主催者側にもう少し考えて頂きたいと思う。28000円のチケット代はやはり高過ぎるのだ。もう少し値ごろ感のある価格にできなかったのか。
そして、NHK音楽祭に天地創造を持っていき、サントリーの天地創造は一回ということであれば、もう少し入ったのではないか?そう、むしろ ロ短調ミサをサントリーで2回やるほうが懸命だったような感じです。まあ、そんな下世話な話はおいておいて、素晴らしい演奏にブラボー。
2010年10月29日。サントリーホール
モーツアルトプロ
前日にウィーンフィルでモーツアルトの交響曲33番を聞いていた。同じウィーンのオケなのに、どうしてこう違うんだろう。こちらのモーツアルトには音楽の、いや生きる悦びが溢れている。音は快活に活動しほら音楽ってこんなに素敵じゃないか!って話しかける。ピリオド奏法が何かは分からないが、あの音楽を奏でる為には、楽員がみんな心を併せ、同じ呼吸をしていないと、きっと難しいだろうなと思う。非常に絶妙な息の併せ方が必要なのだ。それが微妙なニュアンスで伝わる。バイオリンとチェロ、木管は違う音を奏でるのに根っこが一緒なのが分かる。そして、録音では聞こえなかった楽器の音色が聞こえてくる。どこまでも幸福な音楽の時であった。アンコールピースが終わったと同時に、もうこのアーノンクールの演奏は聴けないんだと思うと無性に寂しくなった。体調が良くなく開演の1時間半前まで辞めようと思っていたが無理した。コンサートにタクシーで乗り付けるなんて事は僕の今までの記憶ではないけれど。ああ、そうして良かった。
2010年11月2日 東京オペラシティコンサートホール
『トロイアの女たち』
2010年9月7日(火)~ 20日(月)
作 ■ エウリピデス 訳 ■ 山形治江 演出 ■ 松本祐子
出演■ 倉野章子、藤堂陽子、山本道子、つかもと景子、塩田朋子、奥山美代子、 佐藤麻衣子、頼経明子、松岡依都美、吉野実紗/増岡裕子、木下三枝子 /坂口芳貞、石田圭祐、細貝光司、清水圭吾
『カラムとセフィーの物語』
2010年10月1日(金)~14日(木)
原作 ■ マロリー・ブラックマン 脚色 ■ ドミニク・クック
訳 ■ 中山夏織 演出 ■ 高瀬久男
出演■ 山本郁子、山崎美貴、鬼頭典子、添田園子、渋谷はるか、鈴木亜希子、下池沙知、千田美智子/大滝寛、押切英希、沢田冬樹、鈴木弘秋、林田一高、亀田佳明、上川路啓志、柳橋朋典、藤側宏大

「トロイアの女たち」
観に行って良かった。ベニサンピットがなくなってしまって、このような設えの小空間を信濃町でみることができたのはとても嬉しいなあと思う。美術がとても美しかった。あと、照明。渋い色使いであるが細かく繊細、時に大胆。
さてお芝居自体である。ギリシア古典を演じる時には、なぜか独特の台詞回しがある。何年か前に新国立劇場にギリシアから来日して確か「王女メディア」をやった時はそんな風には感じなかったし、外国ではギリシアもののお芝居を(オペラはあるけれど)見たことがないので良く分からないのだが、日本でやる時には、朗々と語り上げる独特の台詞回しがある。
今回の公演で坂口芳貞(タルテュビオス)が圧倒的に面白いのは、それを一度捨てているからである。普通に演じたらどうなるだろうかというところか始まっている。それは、例えば、メネラオスの石田圭祐やアンドロマケの塩田朋子、ヘレネの松岡依都美、また後半のヘカベの倉野章子にもいえる。結果として鈴木忠志的な感じになるとしても、型から始まっていない、もしくは、そこに頼らないからである。ただし、コロスはそういうわけにはいかなかったように思えて仕方がない。
古典劇の面白さはコロスの正否にかかっているといってもいいと思う。そこが面白いと芝居が断然湧いてくるのである。今回のコロスはせっかく年齢も体型も雰囲気も違う女性を集めた文学座の精鋭チームである。こんな贅沢なコロスが他でできるかというくらいである。山本道子、藤堂陽子、佐藤麻衣子とおなじみも少なくない。この8人の演技の方向性があまりにも一緒過ぎて面白みにギアが入らない。また、例のギリシア劇の型の中にいすぎるものだから、何か世界でも一番上手い演劇少女たちをみているような気までした。コロスはあくまでもハーモニーが面白い。旋律をみんなで歌うのではなく四部合唱、いやこんな8人なら8音が聞こえて来て、それがひとつのハーモニーを作るようなコロスであって欲しいと思うのだが如何でしょう。あと、唄が入ったときのテンションがそれまでとつながらなさ過ぎで変テコになる。そして今宵は台詞を多くの人が噛んでしまっていた。記念Tシャツ2000円がとても良質。喜んで購入。上演時間95分。2010年9月17日
『カラムとセフィーの物語』
文学座の圧倒的勝利宣言。2時間45分の上演時間をきいて、開演前にうんざりした人は少なくないのではないか?不勉強で作者も内容もほとんど知らないに近い状況で、ただただ、文学座がアトリエで上演するのが楽しみで出かけていったのだ。ほとんど素舞台に近い状況で、今回はビブラホン(木琴)ふたつを中心に生演奏。現代の問題が凝縮されたような物語はスピーディーである。現代の話であり普遍的。愛憎が生まれ均衡が崩れる。誤解を癒すものは大きな自己犠牲でしかなかったり。家族や社会の問題も含まれる。役者は技術と魅力にあふれ、高瀬久男の演出は余計なものを徹底的に削ぎ落としたドライなもの。うーーーん、唸ってしまう。きっと、そんなに多くの注目も集めず、今年のベスト10の芝居にも入らないだろうけれど、こんな素晴らしい芝居を劇団として上演できる文学座。その勝利宣言でもあるような舞台だ。老舗だけれど最前線、最高峰。すごい。すごいや。杉村春子さんを始めとする鬼籍に入られた方々がきっと微笑みと歯ぎしりをもって見つめているだろう。2010年10月12日
2010年9月7日(火)~ 20日(月)
作 ■ エウリピデス 訳 ■ 山形治江 演出 ■ 松本祐子
出演■ 倉野章子、藤堂陽子、山本道子、つかもと景子、塩田朋子、奥山美代子、 佐藤麻衣子、頼経明子、松岡依都美、吉野実紗/増岡裕子、木下三枝子 /坂口芳貞、石田圭祐、細貝光司、清水圭吾
『カラムとセフィーの物語』
2010年10月1日(金)~14日(木)
原作 ■ マロリー・ブラックマン 脚色 ■ ドミニク・クック
訳 ■ 中山夏織 演出 ■ 高瀬久男
出演■ 山本郁子、山崎美貴、鬼頭典子、添田園子、渋谷はるか、鈴木亜希子、下池沙知、千田美智子/大滝寛、押切英希、沢田冬樹、鈴木弘秋、林田一高、亀田佳明、上川路啓志、柳橋朋典、藤側宏大
「トロイアの女たち」
観に行って良かった。ベニサンピットがなくなってしまって、このような設えの小空間を信濃町でみることができたのはとても嬉しいなあと思う。美術がとても美しかった。あと、照明。渋い色使いであるが細かく繊細、時に大胆。
さてお芝居自体である。ギリシア古典を演じる時には、なぜか独特の台詞回しがある。何年か前に新国立劇場にギリシアから来日して確か「王女メディア」をやった時はそんな風には感じなかったし、外国ではギリシアもののお芝居を(オペラはあるけれど)見たことがないので良く分からないのだが、日本でやる時には、朗々と語り上げる独特の台詞回しがある。
今回の公演で坂口芳貞(タルテュビオス)が圧倒的に面白いのは、それを一度捨てているからである。普通に演じたらどうなるだろうかというところか始まっている。それは、例えば、メネラオスの石田圭祐やアンドロマケの塩田朋子、ヘレネの松岡依都美、また後半のヘカベの倉野章子にもいえる。結果として鈴木忠志的な感じになるとしても、型から始まっていない、もしくは、そこに頼らないからである。ただし、コロスはそういうわけにはいかなかったように思えて仕方がない。
古典劇の面白さはコロスの正否にかかっているといってもいいと思う。そこが面白いと芝居が断然湧いてくるのである。今回のコロスはせっかく年齢も体型も雰囲気も違う女性を集めた文学座の精鋭チームである。こんな贅沢なコロスが他でできるかというくらいである。山本道子、藤堂陽子、佐藤麻衣子とおなじみも少なくない。この8人の演技の方向性があまりにも一緒過ぎて面白みにギアが入らない。また、例のギリシア劇の型の中にいすぎるものだから、何か世界でも一番上手い演劇少女たちをみているような気までした。コロスはあくまでもハーモニーが面白い。旋律をみんなで歌うのではなく四部合唱、いやこんな8人なら8音が聞こえて来て、それがひとつのハーモニーを作るようなコロスであって欲しいと思うのだが如何でしょう。あと、唄が入ったときのテンションがそれまでとつながらなさ過ぎで変テコになる。そして今宵は台詞を多くの人が噛んでしまっていた。記念Tシャツ2000円がとても良質。喜んで購入。上演時間95分。2010年9月17日
『カラムとセフィーの物語』
文学座の圧倒的勝利宣言。2時間45分の上演時間をきいて、開演前にうんざりした人は少なくないのではないか?不勉強で作者も内容もほとんど知らないに近い状況で、ただただ、文学座がアトリエで上演するのが楽しみで出かけていったのだ。ほとんど素舞台に近い状況で、今回はビブラホン(木琴)ふたつを中心に生演奏。現代の問題が凝縮されたような物語はスピーディーである。現代の話であり普遍的。愛憎が生まれ均衡が崩れる。誤解を癒すものは大きな自己犠牲でしかなかったり。家族や社会の問題も含まれる。役者は技術と魅力にあふれ、高瀬久男の演出は余計なものを徹底的に削ぎ落としたドライなもの。うーーーん、唸ってしまう。きっと、そんなに多くの注目も集めず、今年のベスト10の芝居にも入らないだろうけれど、こんな素晴らしい芝居を劇団として上演できる文学座。その勝利宣言でもあるような舞台だ。老舗だけれど最前線、最高峰。すごい。すごいや。杉村春子さんを始めとする鬼籍に入られた方々がきっと微笑みと歯ぎしりをもって見つめているだろう。2010年10月12日
今年は既にカーネギーホールでのショパンプログラムもきいてるし、去年も聞いている上に、この秋はミシェルベロフやルプーなど気になるピアニストが続々来日するので、今年はパスと思っていたら、何とバッハプログラムがあるというので、またもや見参。
プログラム
ベートーヴエン ピアノソナタ 30、31、32番 2010年10月23日
J.S.バッハ : 平均律クラヴィーア曲集第1巻 BWV846~869 (全曲)11月3日(筆者病気で行けず)

一番安いPブロックでも12000円かあ。そう思いながら久々の人民席に座ってポリーニのベートーベン。正直言うと、ベートーベンのソナタの末尾を飾る傑作について僕は聴き込んでいるわけではない。しかし、ひとつ言えることは、このベートーベンでのポリーニのそれは、もはやひとりの作曲家も調節して音楽の美しさ、響きにどこまでも身を委ねて弾いているということである。それは、非常に高次元でベートーベンというよりも、ポリーニであり、ポリーニというよりも音楽であり、音であるのだ。ピアノを叩くときのハンマー音と弦の響きが混ざり合いとても不思議な世界を創りだしていた。
この美しさは誰にでも分かる。何だろう。モナリザのような絶対的な音楽の世界観をポリーニは確率していたのだ。数年前から僕はポリーニの現代音楽を聴いてもちっとも苦痛でも嫌でもなくなったのだが、それもポリーニマジックだからなのだと思った。もう20年を相当越えて世界のトップピアニストでいるけれども、僕の若い時にはポリーニに対抗できるピアニストがまだ何人もいた。
ルドルフゼルキン、スヴャトラフリヒテル、ミケランジェリ、ホロヴィッツ、クラウディオアラウ、エミールギレリス、僕はそういった巨匠の生演奏を聴けたことをいま本当に良かったと思っているのだ。10月23日
3人のピアニストによるベートーヴェンのピアノソナタ32番第1楽章
先ずはポリーニ
ルドルフゼルキン
スヴャトラフリヒテル
プログラム
ベートーヴエン ピアノソナタ 30、31、32番 2010年10月23日
J.S.バッハ : 平均律クラヴィーア曲集第1巻 BWV846~869 (全曲)11月3日(筆者病気で行けず)
一番安いPブロックでも12000円かあ。そう思いながら久々の人民席に座ってポリーニのベートーベン。正直言うと、ベートーベンのソナタの末尾を飾る傑作について僕は聴き込んでいるわけではない。しかし、ひとつ言えることは、このベートーベンでのポリーニのそれは、もはやひとりの作曲家も調節して音楽の美しさ、響きにどこまでも身を委ねて弾いているということである。それは、非常に高次元でベートーベンというよりも、ポリーニであり、ポリーニというよりも音楽であり、音であるのだ。ピアノを叩くときのハンマー音と弦の響きが混ざり合いとても不思議な世界を創りだしていた。
この美しさは誰にでも分かる。何だろう。モナリザのような絶対的な音楽の世界観をポリーニは確率していたのだ。数年前から僕はポリーニの現代音楽を聴いてもちっとも苦痛でも嫌でもなくなったのだが、それもポリーニマジックだからなのだと思った。もう20年を相当越えて世界のトップピアニストでいるけれども、僕の若い時にはポリーニに対抗できるピアニストがまだ何人もいた。
ルドルフゼルキン、スヴャトラフリヒテル、ミケランジェリ、ホロヴィッツ、クラウディオアラウ、エミールギレリス、僕はそういった巨匠の生演奏を聴けたことをいま本当に良かったと思っているのだ。10月23日
3人のピアニストによるベートーヴェンのピアノソナタ32番第1楽章
先ずはポリーニ
ルドルフゼルキン
スヴャトラフリヒテル
10月1日 男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 山田洋次監督 竹下景子マドンナ
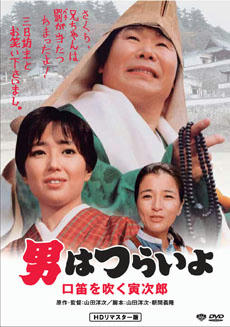
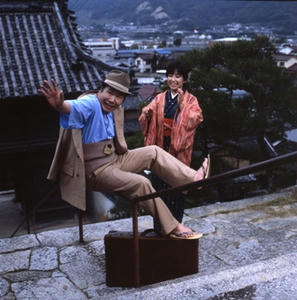
竹下景子さんは、嫁にしたいタレントナンバーワンの座を何年もキープした女優であり、才人で1970年代から80年代にかけてバラエティ番組にも積極的に出演した。当時は女優さんでそのような番組に出ることはなかったので大変珍しかった。現代的だと思われた。もちろん、いまのバラエティと違って「クイズダービー」に象徴されるようなウィットの富んでる番組だけであったけれども。
男はつらいよ32作にあたるこの作品は大変良く出来た作品のひとつで、寅次郎の恋愛と若い恋愛が耕作する初期の物といっていいだろう。後年はそれは吉岡秀隆と後藤久美子の恋愛ストーリーに集約されていくのである。この回では、中井貴一と杉田かおるのそれである。この作品では、最後に竹下景子は寅次郎に積極的に告白までするのだが、寅次郎から身をひいてしまうという。寅次郎が竹下景子を捨てるという話で終わる。衝撃的でもある。吉備路、岡山県の高梁(たかはし)での物語で、ヒロシ(前田吟)の兄弟が勢揃いするのでファンに取っても面白い。真面目でプレタリアートなヒロシの兄妹が劇団民藝の梅田さんという大俳優であるところも面白い。それに対する俳優はみんな世俗的な人ばかり。例えば、長門勇、穂積隆信、松村達雄。レオナルド熊や石倉三郎も少しだけ出てくる。山田洋次監督の嗜好性が出ているなあと思った次第。もちろんおなじみの笠智衆(りゅうちしゅう)も出て来て、中井貴一の父は松竹映画の黄金時代の名優(佐田啓二)だったこともあるのか。小津映画へのトリビュートでこの作品は終わる。すなわち、瀬戸内海のレオナルド熊の家の物干し台に舞う洗濯物のショットで終わるのだ。また、小津映画を見たくなるような終わり方もいいな。
口笛を吹く寅次郎の予告編がなかったので、40周年記念の予告編を載せておきます。
10月2日 ミュンヘン スティーブンスピルバーグ監督
スピルバーグ監督が「シンドラーのリスト」に続いて創り上げたユダヤ人もの。小学生のころ、まだ日本のバレーボールが何色のメダルを取るのか!と興味津々でテレビに釘付けになっていたときに起きた実際の事件、それはミュンヘンオリンピックでのイスラエル選手団人質事件であり、黒い9月というパレスチナ人グループの世界を震かんさせたテロの初期のものであり、その後、イスラエルのスパイ組織、裏警察?組織であるモサドによる報復暗殺まで続く事件である。その報復暗殺を中心に描いたのがこの作品。結構グロイシーンも山ほどあるし、緊迫感が2時間半続くので疲れるが、見応えがあることは間違いない。著名な俳優を極力排したのも成功。素晴らしい美術、カメラワーク、照明などにも注目して欲しい。このミュンヘンの事件や、先に書いた「クイズショウ」などはどちらもテレビを通じた事件でもあるが、どちらもユーチューブで実際の映像をみることができるのも興味深い。この作品を僕はバンコク滞在中に映画館(バンコクの映画館は立派で安い)見たのだが今回改めてみていろいろと分かった。字幕が少し不親切。
10月3日 スティング ジョージロイヒル監督
アメリカ映画を代表する粋な映画。とにかく出てくる人たちが脇役に至るまで魅力的でかっこいい。素晴らしい美術、カメラワーク、スコットジョプリンのラグタイムな音楽、衣装。1930年代のシカゴにあった高架線の鉄道(地下鉄)は今でもそのままあって、シカゴにいくたびにこの映画を思い出す。若い人に昔の映画だけど見てごらんといって100人が100人ともメチャクチャ面白かった!と言ってくれて僕はにんまりするのであります。無駄なことがひとつもないけれど、遊びが山ほどあるそれで、遊びと思っていることは人物を描写するのにものすごく重要で、テンポもよく、重層的なストーリーでありながら最後はひとつに集約していく。うーむ、これこそ。映画の醍醐味ですね。ジョージロイヒル監督は「明日に向って撃て!」という傑作を、ポールニューマンとレッドフォードの二人で撮っていますが、その成功が二人を監督への信頼に高めたんだろうな。まあ、見たことない人はとにかく見て下さい。人生が楽しくなります。
10月7日 ミニミニ大作戦 ゲイリーグレン監督
マイケルケイン主演の1960年代の名画のリメイクである。総制作費130億円ということで、完璧な布陣である。マークウォールバーク、シャリーズセロン、エドワートノートン、ドナルドサザーランド。脇役も素晴らしい。舞台は、ベネチアに始まり、ヨーロッパアルプス、フィラディルフィア、ロスアンゼルスと見ているだけでも豪華である。小気味のよいテンポ、素晴らしいアクション、それに併せての音楽も素晴らしい。決してつまらないことはない。ところが今回で何回目なのだろう、おそらく10回目くらいの鑑賞なのだが、つまらなくなってきた。人間の描き方が紋切り型で、薄っぺらいのである。素晴らしい俳優の存在感で何とか保っているが、脚本に決定的な何かが欠けている。普通は細かいエピソードや癖やこだわりとか、何かで創り上げていく人間像が決定的に薄っぺらいのだ。何だろう。
見ている自分がこの作品で楽しんでいちゃマズいんじゃないかと思えてきたのだ。
見て決して損はない一級娯楽作品である。しかし、例えば「ダイハード」であったような単なるアクション映画で終わらない深みや感動はない。一切ない。
10月21日 インサイドマン スパイクリー監督
日本ではどれだけヒットしたのか知らないけれども、これだけ面白い映画が産まれるのは数年に一度じゃないかなあ。見事は脚本、メインプロットも、サイドストーリーも面白く、ニューヨークの金融街の匂いがぷんぷんする映画である。また、役者もスゴく、デンゼルワシントン、クライブオーウェン、ジョディフォスターをメインに、クリストファープラマーやウイリアムデフォーなど。いやいや、小さな役をやっている人もみんな個性豊かで俳優の面白さはフェリーに映画のようです。最初は日本公開前に機内で見ておったまげ、DVDを買ってまた見ているというわけです。スパイクリーの最高傑作ではないかなあ。必見の娯楽映画。粋です。2007年のアメリカ映画。
10月22日 コラテラル マイケルマン監督
2004年の映画でおそらくトムクルーズ最後のオモシロ映画ではないだろうか?マイケルマン監督はテレビドラマからの叩き上げの監督であるが、監督の腕もそうだが、見事なのは脚本とキャメラ。空撮でこれほど美しいロスアンジェルスを見たのは久しぶりだし、一晩の話なので主に夜ばかりなんだけれど、キャメラが美しい。そして、脚本。見事ですねえ。一切の無駄がないのに、それが出演者の心情やキャラクターを見事に物語る。うーーん、面白い。ジェイミーフォックスがいいですねえ。これは必見の娯楽映画です。
10月23日日 風とライオン ジョンミリアス監督
ショーンコネリー、キャンディスバーゲン主演の1975年の映画。「地獄の黙示録」の脚本を書いたジョンミリアス監督。いかにも「アラビアのロレンス」の成功よ再び、でも予算は少なめで。。という映画であるが、無邪気な内容でなかなか面白い。日本公開当時、映画見まくっていた時代であったけれども全く興味を示さなかったけれどもね。ジョンヒューストンなど脇役もいい。そして、モロッコの建造物や自然を楽しめる一大叙事詩です。
10月24日 チャンス Being there ハルアシュビー監督
ピーターセラーズ晩年の傑作。シャリーマクレーン、ジャックウォーデンなど名優を揃えた。知る人ぞしる名作。テレビでうつらうつらしながら見ていただけで、もう10年近く前に買ったDVDをやっと見た。心に沁み入る作品とはこのことで、コメディの傑作であり、人生を深く考えさせる作品なのだ。ピーターセラーズは笑わせようなどとは決してしていない、ただただ、チャンスとよばれる男を演じ続けるだけなのだが、心底面白い。作品ごとにどかーんと変わる役者として、昔はロバートデニーロを良く驚嘆の存在として挙げられたものだが、僕はどちらかというとこのピーターセラーズをあげたいのだ。ピンクパンサーのクルーゾー警部、名探偵登場の謎の中国人、007カジノロワイヤル、博士の異常な愛情、ロリータなどのキューブリック作品のそれと同一人物とは思えないだろう。
竹下景子さんは、嫁にしたいタレントナンバーワンの座を何年もキープした女優であり、才人で1970年代から80年代にかけてバラエティ番組にも積極的に出演した。当時は女優さんでそのような番組に出ることはなかったので大変珍しかった。現代的だと思われた。もちろん、いまのバラエティと違って「クイズダービー」に象徴されるようなウィットの富んでる番組だけであったけれども。
男はつらいよ32作にあたるこの作品は大変良く出来た作品のひとつで、寅次郎の恋愛と若い恋愛が耕作する初期の物といっていいだろう。後年はそれは吉岡秀隆と後藤久美子の恋愛ストーリーに集約されていくのである。この回では、中井貴一と杉田かおるのそれである。この作品では、最後に竹下景子は寅次郎に積極的に告白までするのだが、寅次郎から身をひいてしまうという。寅次郎が竹下景子を捨てるという話で終わる。衝撃的でもある。吉備路、岡山県の高梁(たかはし)での物語で、ヒロシ(前田吟)の兄弟が勢揃いするのでファンに取っても面白い。真面目でプレタリアートなヒロシの兄妹が劇団民藝の梅田さんという大俳優であるところも面白い。それに対する俳優はみんな世俗的な人ばかり。例えば、長門勇、穂積隆信、松村達雄。レオナルド熊や石倉三郎も少しだけ出てくる。山田洋次監督の嗜好性が出ているなあと思った次第。もちろんおなじみの笠智衆(りゅうちしゅう)も出て来て、中井貴一の父は松竹映画の黄金時代の名優(佐田啓二)だったこともあるのか。小津映画へのトリビュートでこの作品は終わる。すなわち、瀬戸内海のレオナルド熊の家の物干し台に舞う洗濯物のショットで終わるのだ。また、小津映画を見たくなるような終わり方もいいな。
口笛を吹く寅次郎の予告編がなかったので、40周年記念の予告編を載せておきます。
10月2日 ミュンヘン スティーブンスピルバーグ監督
スピルバーグ監督が「シンドラーのリスト」に続いて創り上げたユダヤ人もの。小学生のころ、まだ日本のバレーボールが何色のメダルを取るのか!と興味津々でテレビに釘付けになっていたときに起きた実際の事件、それはミュンヘンオリンピックでのイスラエル選手団人質事件であり、黒い9月というパレスチナ人グループの世界を震かんさせたテロの初期のものであり、その後、イスラエルのスパイ組織、裏警察?組織であるモサドによる報復暗殺まで続く事件である。その報復暗殺を中心に描いたのがこの作品。結構グロイシーンも山ほどあるし、緊迫感が2時間半続くので疲れるが、見応えがあることは間違いない。著名な俳優を極力排したのも成功。素晴らしい美術、カメラワーク、照明などにも注目して欲しい。このミュンヘンの事件や、先に書いた「クイズショウ」などはどちらもテレビを通じた事件でもあるが、どちらもユーチューブで実際の映像をみることができるのも興味深い。この作品を僕はバンコク滞在中に映画館(バンコクの映画館は立派で安い)見たのだが今回改めてみていろいろと分かった。字幕が少し不親切。
10月3日 スティング ジョージロイヒル監督
アメリカ映画を代表する粋な映画。とにかく出てくる人たちが脇役に至るまで魅力的でかっこいい。素晴らしい美術、カメラワーク、スコットジョプリンのラグタイムな音楽、衣装。1930年代のシカゴにあった高架線の鉄道(地下鉄)は今でもそのままあって、シカゴにいくたびにこの映画を思い出す。若い人に昔の映画だけど見てごらんといって100人が100人ともメチャクチャ面白かった!と言ってくれて僕はにんまりするのであります。無駄なことがひとつもないけれど、遊びが山ほどあるそれで、遊びと思っていることは人物を描写するのにものすごく重要で、テンポもよく、重層的なストーリーでありながら最後はひとつに集約していく。うーむ、これこそ。映画の醍醐味ですね。ジョージロイヒル監督は「明日に向って撃て!」という傑作を、ポールニューマンとレッドフォードの二人で撮っていますが、その成功が二人を監督への信頼に高めたんだろうな。まあ、見たことない人はとにかく見て下さい。人生が楽しくなります。
10月7日 ミニミニ大作戦 ゲイリーグレン監督
マイケルケイン主演の1960年代の名画のリメイクである。総制作費130億円ということで、完璧な布陣である。マークウォールバーク、シャリーズセロン、エドワートノートン、ドナルドサザーランド。脇役も素晴らしい。舞台は、ベネチアに始まり、ヨーロッパアルプス、フィラディルフィア、ロスアンゼルスと見ているだけでも豪華である。小気味のよいテンポ、素晴らしいアクション、それに併せての音楽も素晴らしい。決してつまらないことはない。ところが今回で何回目なのだろう、おそらく10回目くらいの鑑賞なのだが、つまらなくなってきた。人間の描き方が紋切り型で、薄っぺらいのである。素晴らしい俳優の存在感で何とか保っているが、脚本に決定的な何かが欠けている。普通は細かいエピソードや癖やこだわりとか、何かで創り上げていく人間像が決定的に薄っぺらいのだ。何だろう。
見ている自分がこの作品で楽しんでいちゃマズいんじゃないかと思えてきたのだ。
見て決して損はない一級娯楽作品である。しかし、例えば「ダイハード」であったような単なるアクション映画で終わらない深みや感動はない。一切ない。
10月21日 インサイドマン スパイクリー監督
日本ではどれだけヒットしたのか知らないけれども、これだけ面白い映画が産まれるのは数年に一度じゃないかなあ。見事は脚本、メインプロットも、サイドストーリーも面白く、ニューヨークの金融街の匂いがぷんぷんする映画である。また、役者もスゴく、デンゼルワシントン、クライブオーウェン、ジョディフォスターをメインに、クリストファープラマーやウイリアムデフォーなど。いやいや、小さな役をやっている人もみんな個性豊かで俳優の面白さはフェリーに映画のようです。最初は日本公開前に機内で見ておったまげ、DVDを買ってまた見ているというわけです。スパイクリーの最高傑作ではないかなあ。必見の娯楽映画。粋です。2007年のアメリカ映画。
10月22日 コラテラル マイケルマン監督
2004年の映画でおそらくトムクルーズ最後のオモシロ映画ではないだろうか?マイケルマン監督はテレビドラマからの叩き上げの監督であるが、監督の腕もそうだが、見事なのは脚本とキャメラ。空撮でこれほど美しいロスアンジェルスを見たのは久しぶりだし、一晩の話なので主に夜ばかりなんだけれど、キャメラが美しい。そして、脚本。見事ですねえ。一切の無駄がないのに、それが出演者の心情やキャラクターを見事に物語る。うーーん、面白い。ジェイミーフォックスがいいですねえ。これは必見の娯楽映画です。
10月23日日 風とライオン ジョンミリアス監督
ショーンコネリー、キャンディスバーゲン主演の1975年の映画。「地獄の黙示録」の脚本を書いたジョンミリアス監督。いかにも「アラビアのロレンス」の成功よ再び、でも予算は少なめで。。という映画であるが、無邪気な内容でなかなか面白い。日本公開当時、映画見まくっていた時代であったけれども全く興味を示さなかったけれどもね。ジョンヒューストンなど脇役もいい。そして、モロッコの建造物や自然を楽しめる一大叙事詩です。
10月24日 チャンス Being there ハルアシュビー監督
ピーターセラーズ晩年の傑作。シャリーマクレーン、ジャックウォーデンなど名優を揃えた。知る人ぞしる名作。テレビでうつらうつらしながら見ていただけで、もう10年近く前に買ったDVDをやっと見た。心に沁み入る作品とはこのことで、コメディの傑作であり、人生を深く考えさせる作品なのだ。ピーターセラーズは笑わせようなどとは決してしていない、ただただ、チャンスとよばれる男を演じ続けるだけなのだが、心底面白い。作品ごとにどかーんと変わる役者として、昔はロバートデニーロを良く驚嘆の存在として挙げられたものだが、僕はどちらかというとこのピーターセラーズをあげたいのだ。ピンクパンサーのクルーゾー警部、名探偵登場の謎の中国人、007カジノロワイヤル、博士の異常な愛情、ロリータなどのキューブリック作品のそれと同一人物とは思えないだろう。
庄司智春 ピンネタライブ

久しぶりにお笑いライブにいった。庄司智春氏は人気コンビ品川庄司の右側の青年である。ツイッターでちょっとだけ品川庄司のお二人とやりとりをしたのだ。というのも、4月のバラエティの番組でご一緒し、別に会話を交わしたわけでもないのだが、その佇まいに何かね面白さを感じたのです。10年ほど前は若くアイドル的な存在的だったお二人だが、この5年の間にそれぞれが進化しよしもとの中堅を担う存在になった。ツイッターでのやり取りがお二人とも非常に誠実でちょっとテレビで見せていない芸人としての姿を見て見たくなった。
庄司智春さんが新宿のブラッツという100人も入れば満杯になる劇場でピンネタライブをやるという。それも前売1200円、当日1500円。劇場費もでないライブ。いったいどんな感じなんだろう。行くかどうかも迷っていたが、当日劇場に電話をすると当日券も出ますとのことなので、入れるかもと思っていったらガラガラだった。30人ほどの観客のうち20人くらいはきっとファンの女の子なのだろう。どんなことでも笑う。関係者も何人かいて。正直いって、自分を含めてピュアな意味でのお客さんって何人いたんだろうと思う感じ。つまり、そういう状況でライブをやるというのはすごく大変だ。ちゃんとしたお客とのコミュニケーションができない。ひとりで虚空に向って芸を見せるのと同じだ。それを見られている。ひとりで空間に佇み演じ続けなくてはならない。ものすごく孤独なのである。大阪の吉本に若い頃、東京から観に行ったことがある。大阪で仕事があれば見ていた。大阪の吉本のお客さんはとても厳しい。今は知らないので厳しかった。面白くないと笑わない、それどころが容赦ないヤジだ。すごいところだった。それは、グランド花月だけでなく、梅田もそうだし、2丁目劇場もそうだった。その厳しさと同じ空気が昨日のライブではあった。
何をしても笑う客、それは、ウソ笑い。笑いたくて笑っている笑いはプロの演技者には間違いなく通じる。友達のように声をかける熱狂ファンの女の子、わあっ、大変だこりゃ。そんな中でテレビの仕事で忙しくしている男がどれだけのことをやるのかと思っていたら、すごく丁寧に作っていたライブだった。ツイッターでのやり取りのように誠実だった。
ネタを自分でつくり、4人くらいの作家さんとネタを練り、映像作品も揃えてのライブだった。
例えば映像作品の「デート」「デート2」はほとんど一発撮りである。編集点が少ししかなく、ありゃ大変な長廻し。家庭の中にある家具などをタレントに見立てていく作品は、重ねて行くのだが、最後のオチがぼやけてるなあと思ったけれども、勢いで見せてしまう。両方とも、途中でネタの全体構造は曝けだされる。それを最後までやり通して笑いに換えるのはとてつもない技術を要す。
例えば、切り替えを「はい」というひと言で決めるやり方は決して新しくないのだが、決して古くなく感じない。それは、きちんと演じているからだ。
コンビニやFFの新商品を食べてコメントを言うのはテレビでできないネタだが面白い。ふわっと本音が漏れてくるところできちんと笑いに昇華されていた。クイズ番組の問題をメチャクチャ分かりやすいものにする。客はこんなことでも笑うかというところで笑う。見事な突っ込みのところとどうでもいいところの笑いが同じで、わあ、残酷だなあと思う。見事なところで爆笑にならない。孤独だ。
最後のトークコーナーはちょっとグタグタで、あれはファンに対するサービスなのかなあ。そこだけ挑戦している感じがしなかった。芸として演じていなかった部分が多く残念。
大きな赤字を負って、決してすぐには見返りもない孤独な時間をどれだけ重ねたかで次の飛躍がある世界なのだろう。ちょっと自分のことも振り返りつつ、何かちょこっと生きざまも見えた素敵なライブだった。2010年10月13日 新宿シアターブラッツ
久しぶりにお笑いライブにいった。庄司智春氏は人気コンビ品川庄司の右側の青年である。ツイッターでちょっとだけ品川庄司のお二人とやりとりをしたのだ。というのも、4月のバラエティの番組でご一緒し、別に会話を交わしたわけでもないのだが、その佇まいに何かね面白さを感じたのです。10年ほど前は若くアイドル的な存在的だったお二人だが、この5年の間にそれぞれが進化しよしもとの中堅を担う存在になった。ツイッターでのやり取りがお二人とも非常に誠実でちょっとテレビで見せていない芸人としての姿を見て見たくなった。
庄司智春さんが新宿のブラッツという100人も入れば満杯になる劇場でピンネタライブをやるという。それも前売1200円、当日1500円。劇場費もでないライブ。いったいどんな感じなんだろう。行くかどうかも迷っていたが、当日劇場に電話をすると当日券も出ますとのことなので、入れるかもと思っていったらガラガラだった。30人ほどの観客のうち20人くらいはきっとファンの女の子なのだろう。どんなことでも笑う。関係者も何人かいて。正直いって、自分を含めてピュアな意味でのお客さんって何人いたんだろうと思う感じ。つまり、そういう状況でライブをやるというのはすごく大変だ。ちゃんとしたお客とのコミュニケーションができない。ひとりで虚空に向って芸を見せるのと同じだ。それを見られている。ひとりで空間に佇み演じ続けなくてはならない。ものすごく孤独なのである。大阪の吉本に若い頃、東京から観に行ったことがある。大阪で仕事があれば見ていた。大阪の吉本のお客さんはとても厳しい。今は知らないので厳しかった。面白くないと笑わない、それどころが容赦ないヤジだ。すごいところだった。それは、グランド花月だけでなく、梅田もそうだし、2丁目劇場もそうだった。その厳しさと同じ空気が昨日のライブではあった。
何をしても笑う客、それは、ウソ笑い。笑いたくて笑っている笑いはプロの演技者には間違いなく通じる。友達のように声をかける熱狂ファンの女の子、わあっ、大変だこりゃ。そんな中でテレビの仕事で忙しくしている男がどれだけのことをやるのかと思っていたら、すごく丁寧に作っていたライブだった。ツイッターでのやり取りのように誠実だった。
ネタを自分でつくり、4人くらいの作家さんとネタを練り、映像作品も揃えてのライブだった。
例えば映像作品の「デート」「デート2」はほとんど一発撮りである。編集点が少ししかなく、ありゃ大変な長廻し。家庭の中にある家具などをタレントに見立てていく作品は、重ねて行くのだが、最後のオチがぼやけてるなあと思ったけれども、勢いで見せてしまう。両方とも、途中でネタの全体構造は曝けだされる。それを最後までやり通して笑いに換えるのはとてつもない技術を要す。
例えば、切り替えを「はい」というひと言で決めるやり方は決して新しくないのだが、決して古くなく感じない。それは、きちんと演じているからだ。
コンビニやFFの新商品を食べてコメントを言うのはテレビでできないネタだが面白い。ふわっと本音が漏れてくるところできちんと笑いに昇華されていた。クイズ番組の問題をメチャクチャ分かりやすいものにする。客はこんなことでも笑うかというところで笑う。見事な突っ込みのところとどうでもいいところの笑いが同じで、わあ、残酷だなあと思う。見事なところで爆笑にならない。孤独だ。
最後のトークコーナーはちょっとグタグタで、あれはファンに対するサービスなのかなあ。そこだけ挑戦している感じがしなかった。芸として演じていなかった部分が多く残念。
大きな赤字を負って、決してすぐには見返りもない孤独な時間をどれだけ重ねたかで次の飛躍がある世界なのだろう。ちょっと自分のことも振り返りつつ、何かちょこっと生きざまも見えた素敵なライブだった。2010年10月13日 新宿シアターブラッツ
久しぶりのジャズ、久しぶりのブルーノート。ラムゼイルイスはもう20年くらい前にニューヨークで一度生を聞いているはず。来日するたびに行こうかなと思いきや忙しかったり何なりで。
今回のライブはドラムとべースと3人で、新作「カラーズ」のワールドプレミアを兼ねたライブ。それが素晴らしかった。季節をめぐりながら、エコロジーを考えるとあって、いろいろの表題もつけられた音楽。そして、ラムゼイルイスの音楽人生をも俯瞰するようなさまざまな音楽のジャンル。ジャズ、モダンジャズ、ヒップホップ、ブールス、ファンク。さまざまな音楽が融合しひとつの作品となっていました。ただね、表題に併せて背面にラムゼイルイスの指示で映像が流されるのですが、それがうるさくてうるさくて。音楽だけで十分です。
すごいのは、久しぶりに1980年代のアルバムなんかもきいてみたのだけれど、音楽が進化、いや深化しているんですね。素晴らしいライブでまた、ジャズもちょこちょこ行こうかなと思った次第。
ブルーノート東京 9月29日
18年ぶりの来日らしい。18年前は行かなかった。確か、フィガロ、コシ、ドンジョバンニのモーツアルト3部作という鉄板興行で大コケしたはず。そりゃ、そうだ。酷いんだもん。当時、ロイヤルオペラは民営化の流れのなかで1980年代までの栄光から墜ちたオペラハウスだったかからだ。その後、僕は、ロンドンに出かけたときも、民営化で大幅値上げされた一等席3万円を越える価格で、わざわざこの価格なら東京できけばいいし、もっといいオペラをきけるよなと思ったりしたものだ。一度、バレエのロミオとジュリエットをロンドンで見たときの演奏などは、これは日本のアマチュアオケのほうがましじゃないかなと思うような有様だった。ロイヤルオペラハウスは1990年代に改装して、受付とカフェは素晴らしくなったのだが、演奏は荒れた。特別な公演の時は素晴らしい演奏をすることもあるのだけれど、アレレなことが多い。パッパーノは次世代の期待の指揮者である。いったいどんな演奏をするのか愉しみである。
2010年9月11日@上野文化会館
マスネ作曲 歌劇「マノン」@上野文化会館
アントニオパッパーノ指揮 ロランベリー演出 シャンタルトーマス美術
マノンレスコー/アンナネトレプコ デグリュー/マシューボレンザーニ ほか
英国ロイヤル・オペラ 2010年日本公演 「マノン」全5幕
指揮:アントニオ・パッパーノ
演出:ロラン・ペリー
美術:シャンタル・トーマス
ギヨー・ド・モルフォンテーヌ:ギ・ド・メイ
ド・ブレティニ:ウィリアム・シメル
プセット:シモナ・ミハイ
ジャヴォット:ルイーゼ・イネス
ロゼット:カイ・リューテル
宿屋の主人:リントン・ブラック
レスコー:ラッセル・ブラウン
警官:ドナルドソン・ベル、ジョン・ベルナイス
マノン・レスコー:アンナ・ネトレプコ
騎士デ・グリュー:マシュー・ポレンザーニ
伯爵デ・グリュー:ニコラ・クルジャル
ロイヤル・オペラ合唱団 / ロイヤル・オペラハウス管弦楽団
◆上演時間◆
第1幕(転換)第2幕:15:00 - 16:20
休憩 25分
第3幕(場面転換あり):16:45 - 17:45
休憩 25分
第4幕(転換)第5幕:18:10 -18:55
※下線で示したキャストは、当初発表させていただいたキャストが変更になったものです。
当初、「マノン」の伯爵デ・グリュー役で出演を予定しておりましたクリストフ・フィシェッサーは、喉頭炎のために出演できなくなりました。
代わって、伯爵デ・グリューはニコラ・クルジャルが演じます。
なにとぞご了承のほどをお願い申し上げます。
また、警官役はプログラムの記載より変更となっております。
以下は来日前にあったロンドン公演での盗撮もの。違法ですから、すぐに観られなくなると思います。でも日本公演もほぼ同じセットです。主役を歌ってるのはネトレプコ。
蘇生したロイヤルオペラハウスの記念碑的公演。
直前に、とてもいい条件で1階席のS席チケットを手に入れる事ができて、急遽観に行くことにした。正直いってマスネという作曲家のオペラでワクワクした経験が一度もない。最初にマスネのオペラをみたのは1980年代終わりのメトロポリタンオペラハウス、亡くなったアルフレードクラウスの生を聞いたのが最初かな。おそらく「ウェルテル」。しかし、退屈で退屈で。「マノン」も見てはいる。でも退屈で、ほとんど覚えていないのだ。何で今回見に至ったのかは分からない。積極的に観に行ったわけではない。
オケピットから最初の音が聞こえてきた時に、ああスゴいのが観られるぞと思ったくらい。パッパーノに導かれたオケは90年代に沈滞していたオペラハウスのイメージを一掃するような明るく活き活きとした音楽を鳴り響かせた。よくきいてみるとマスネの音楽はやはり変化に乏しく、曲調も単調で面白い物ではない。しかし、スコアの中から現代と結びつける物を探し出し、それを客に上手く伝えることができればきっとやはり歴史に残って行く作品なのだろう。パッパーノの指揮はまさにそれだった。
措置や演出は単調だし、奇をてらった物ではない。まあ、それはそれでいい。安っぽい美術も予算もあるだろうから仕方ない。それでも、さすがはシャンタルトーマスの担当だけ会って、衣装は本当に素晴らしい物だった。20列目くらいから見ていても生地や仕立てが違う事がはっきり分かる。そして、群衆シーンなどになると、微妙に異なる色合いの衣装の人たちがうまく立っていてとてもキレイだったりした。
歌手もネトレプコはますます磨きがかかり、ボレンザーニやプレティニをやったシメル。モルフォンテーヌのメイなど水準も非常に高かった。しかし、演じる方も必死に最上のものを届けようとしていた。しかし、それを可能にしたのは、パッパーノが導いて、メリハリがあり、絶妙のフレージング、テンポのとりかたが現代的で、細かいところもピッチがあっていたオケが勝者だと思った。
2010年9月11日(上演時間4時間)
ヴェルディ「椿姫」
動画 ロイヤルオペラのジェーンエア演出の動画
このたびの英国ロイヤル・オペラ「椿姫」におけるアンジェラ・ゲオルギューの降板、それをうけて代役をつとめたエルモネラ・ヤオが、初日、3日目の公演で途中降板して、第2幕からアイリーン・ペレスに代わるという予期せぬ事態になったことに対し、観客の皆さまに深くお詫び申し上げます。
エルモネラ・ヤオの不調をうけ、ロイヤル・オペラ側から「椿姫」最終公演のヴィオレッタ役の発表がありました。オペラ・ディレクター、エレイン・パドモワのコメントを下に載せましたが、「マノン」の最終公演を終えたばかりのアンナ・ネトレプコが、22日のヴィオレッタ役を演じることになりました。(最終出演者は22日の会場での発表とさせていただきます。)
なにとぞ、このような事情をご理解のうえ、ご了承のほどお願い申し上げます。
財団法人日本舞台芸術振興会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
英国ロイヤル・オペラの18年ぶりの日本ツアーも、明日最終日を迎えます。
今回の「椿姫」においては、大変残念ながらアンジェラ・ゲオルギューが愛娘の手術に立ち会うことを余儀なくされ降板せざるを得なくなってしまいました。彼女の降板の意志はたいへん固く、それからすぐに私たちは代役探しに奔走いたしました。そしてエルモネラ・ヤオを確保することできました。ところが、彼女は初日と3日目の公演で、突発性のアレルギーによる音声障害によって、第1幕のみで降板するハプニングに見舞われました。両公演にお越しいただいた皆さまには、このような予期せぬ事態になりましたことを、心よりお詫びしたいと思います。
当初、ロイヤル・オペラとしてはゲオルギューの降板をうけて、あらゆる可能性を考え、アンナ・ネトレプコを含め、さまざまな歌手にあたりました。当然、ネトレプコは今回「マノン」に出演していますので、全公演には出演できません。しかし、通常中2日休んで出演しているところを、「マノン」の最終公演を無事歌い終えた後に調子がよければ、(中1日しかなくても)「椿姫」最終公演のみ歌えるかもしれないとのことでした。ですから、我々も最終決定を今まで待たなくてはなりませんでした。
ロイヤル・オペラとしては、二度にわたるエルモネラ・ヤオの途中降板をうけ、再びネトレプコに打診しておりましたところ、ネトレプコから明日のヴィオレッタを歌うという確認をもらいましたので、ここに皆さまにお知らせしたいと思います。
ネトレプコはすでに2年前ロンドンにおいて、このリチャード・エア演出の「椿姫」に出演し、大成功を収めています。
日本の観客の皆さまのご理解をお願い申し上げます。明日の英国ロイヤル・オペラの日本公演の最終公演をお楽しみいただければ幸いです。
英国ロイヤル・オペラハウス
オペラ・ディレクター
エレイン・パドモワ
アンナネトレプコの評価を決定づけた2005年ザルツブルグ音楽祭のネトレプコのヴィオレッタ
英国ロイヤル・オペラ 2010年日本公演「椿姫」全3幕
指揮:アントニオ・パッパーノ
演出:リチャード・エア
ヴィオレッタ・ヴァレリー:アンナ・ネトレプコ
フローラ・ベルヴォワ:カイ・リューテル
ドビニー侯爵:リン・チャンガン
ドゥフォール男爵:エイドリアン・クラーク
医師グランヴィル:リチャード・ウィーゴールド
ガストン子爵:パク・ジミン
アルフレード・ジェルモン:ジェームズ・ヴァレンティ
アンニーナ:サラ・プリング
ジュゼッペ:二―ル・ギレスピー
ジョルジョ・ジェルモン:サイモン・キーンリサイド
使いの男:シャルベル・マター
フローラの召使い:ジョナサン・コード
ロイヤル・オペラ合唱団 / ロイヤル・オペラハウス管弦楽団
◆上演時間◆第1幕:17:00 - 17:40 休憩 30分 第2幕(場面転換あり):18:10 - 19:20 休憩 25分 第3幕:19:45 - 20:20 2010年9月22日@NHKホール
ネトレプコの栄光の日
僕と椿姫
4月に歌舞伎座が閉館する時に大騒ぎになった。ホロヴィッツの初来日の時に大騒ぎになった。公演が始まる前に観客の興奮が盛り上がり異様な空気になる公演がある。18年ぶりのロイヤルオペラの来日公演、最終公演の9月22日の椿姫はまさにそのような公演となった。今回の椿姫4公演のうち3公演は本来の出演予定だったゲオルギューの格下の歌手がさらに降板するというハプニングがあった。
ネットの時代で、世界中で起きていることがメディアの情報を通さずに観客同士のネットワークでガセネタも含まれながら瞬時に世界に広まる時代である。8月後半から「マノン」のネトレプコがキャンセルするだろうという噂がネットに広まっていた。実際は8月下旬に「椿姫」のゲオルギューの降板が発表された。病弱の娘のそばにいてやりたいという理由だったのだが、親の死に目にあわずとも舞台に穴をあけないというのと真逆。それも、ゲオルギューは愛娘のそばにいたのではなく、旦那のオペラ歌手アラーニャとバカンスを楽しんでいることが報道されもした。NHKホールで54000円のS席という高額のチケットを「ゲオルギュー」が出るのならと購入した人はどう思っただろう。交換返金不可なのである。これなら、もう亡くなったマリアカラス霊界から出演予定!ともできるわいな!少なくとも悪意があれば相当あくどい商売もできる。
1970年代に読売日本交響楽団が巨匠カールベームを定期演奏会に呼ぶとして騒然となった。老齢のカールベームは予想通りキャンセルとなり、カールベームをきくために定期会員になった人が大騒ぎになった。しかし、読売日本交響楽団は、代役として幻の指揮者と言われていたジョルジュチェリビダッケが登板。大評判となった。僕は遠巻きに見ていただけだが、いやあ、面白い。ドラマです。観客も喜怒哀楽含めたドラマに巻き込まれるのも公演の楽しみと考えたいものです。
さて、今回の18年ぶりの来日公演。僕は春にニューヨークのメトロポリタンオペラの一等席でゲオルギューとヴァレンティの「椿姫」をきき、初めて椿姫の魅力を感じた物だ。今まできいてきたもののなかで主なものはもう15年前のリッカルドムーティとスカラ座の豪華絢爛な来日公演、当時はムーティのお気に入りで注目を浴びたティツィアーナ・ファブリッチーニという人だったらしい(全く覚えていない。2回のうち1回は亡くなった母を連れて行ったのだが、がっかりしていた。)。線が細く声はきれいだけれども何か心に迫って来ないというのが印象。つまり詰らなk立ったのだ。2回きいたんだけどね。ローマ歌劇場初来日のときは名古屋の愛知芸術劇場まで遠征して聞きに行った。開場に併せて名古屋だけでの公演だったのだ。なんか良く分からない鏡を山ほどつかった演出で、確か指揮はネロサンティ(あと、「トスカ」もやったはず)で、これもイマイチ。椿姫って、冒頭の乾杯の歌が終わったら、あとは退屈だなあと思ったのです。モンテカルロ歌劇場やフェニーチェ歌劇場の来日公演も、豪華絢爛、ゼッフェレリ演出のメトロポリタンオペラ(現地)でも見たのだが、途中で寝てしまう始末。
もうこのオペラは自分に合わないからいいやと避けていたのですが、数年前に芝居のためにミュージカルの発声を主に生業にしている人に発声を習ったら、先生に一環として第二幕のバリトンの名アリア「プロバンスの海と陸」をやれとなり、曲をきくヘソができましたな。2007年にスイスのチューリッヒ歌劇場の来日公演で初めて集中して聞けたのです。指揮:フランツ・ウェルザー=メスト、ヴィオレッタ:エヴァ・メイ アルフレード:ピョートル・ベチャーラ ジェルモン:レオ・ヌッチできいてなるほどねとなったのです。最初にスカラ座の生をきいてから12年、やっと聞けたって感じですね。
2010年4月にニューヨークに観劇のために出かけたとき、あんまり面白い舞台の出し物がなくて、「椿姫」があるけれど、どうしようと、230ドル(2万円くらい)で1階の半ばのど真ん中の素晴らしい席があったので、きいたらば、先述のようにもう脳天にきましたな。ゲオルギューの歌唱と演技のすばらしさ、舞台は豪華絢爛だしね。バレンティというテナーは歴史に残るような歌手ではないかもしれないがヴィオレッタを演じたゲオルギューがやりやすそうで、聞いてる方も何ら不都合はなかったので楽しみにしていたのです。
2010年9月22日「椿姫」
ゲオルギューが降板しアンナ何とかという格下の歌手を54000円、いや2万円の席だろううが聞いている人は、自分を納得させる為に必死だったと思う。僕は仕事もあり、チケットは勝っていたものの行くのをやめようか、3時間の休憩時間にしようか悩んでいましたな。とにかく代役が酷いときいていたのです。ところが前日にネトレプコが登板するとなり、これはどんな歌唱を聴かせるのか楽しみになりました。しかし徹夜。3階席だし、これは寝ちゃうかもしれないなあと思いつつ座席につきました。ところが、パッパーノの指揮はまたまた躍動。こりゃ聞く人の下半身に来る演奏。肌で感じる演奏であります。コーラスと時々づれるのですが、なんのその。脇役のアジア系の歌手がでかい声は出すけれど下品な歌唱をしましたが、ネトレプコの歌唱は、NHKホールにも関わらずピアニシモから高音まで安定した歌唱。強い声なのに、キンキンしていないんですよ。いやあ、いいですね。そして、色気があるのです。ジェーンエアの演出は分かりやすくシンプルです。シルエットを使った1幕と終幕も美しい。いや、何よりも大勢の人たちの人の動かし方が素晴らしいのです。
ネットではジェルモンのキーンサイトの評判がいいのですが、「プロヴァンスの陸と海」ではイタリア語がきれいに歌えていないことと、アリアの最後の高音も避けてちょっとがっかり。しかし、ネトレプコが美しく色気があり、それが歌唱と相まって最高の公演になりました。もちろん練ることもなく、そのあとの仕事も滞ることありませんでした。行って良かった。きっと語り継がれる公演になったでしょう。こりゃ、内容についてはほとんど触れていませんね。まあ、いいや。とにかくパッパーノによってロイヤルオペラは再生し、ネトレプコがマノンとヴィオレッタの公演で日本のオペラファンを席巻した来日公演でした。次の来日は5年後くらいかな?ロンドンに行くことがあったら、またロイヤルオペラハウスでもオペラを楽しもうと思いました。オペラハウスは本当に生きものです。良くなったり悪くなったり。一度の経験で評価を決定づけるのは危険だなと思いました。
最新記事
(01/06)
(12/25)
(08/05)
(06/30)
(12/16)
(08/21)
(04/10)
(09/25)
(11/30)
(11/18)
(11/03)
(10/04)
(09/19)
(08/28)
(06/25)
(06/10)
(12/30)
(02/21)
(12/31)
(09/28)
(06/09)
(05/12)
(12/31)
(09/08)
(06/02)
プロフィール
HN:
佐藤治彦 Haruhiko SATO
HP:
性別:
男性
職業:
演劇ユニット経済とH 主宰
趣味:
海外旅行
自己紹介:
演劇、音楽、ダンス、バレエ、オペラ、ミュージカル、パフォーマンス、美術。全てのパフォーミングアーツとアートを心から愛する佐藤治彦のぎりぎりコメントをお届けします。Haruhiko SATO 日本ペンクラブ会員
カテゴリー
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
フリーエリア
最新CM
[08/24 おばりーな]
[02/18 清水 悟]
[02/12 清水 悟]
[10/17 栗原 久美]
[10/16 うさきち]
最新TB
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(12/05)
(12/07)
(12/08)
(12/09)
(12/10)
(12/11)
(12/29)
(01/03)
(01/10)
(01/30)
(02/13)
(03/09)
(03/12)
(03/16)
(03/17)
(03/19)
(03/20)
(03/20)
(03/22)
(03/22)
(03/23)
(03/24)
(03/28)
(04/01)
(04/01)
カウンター
